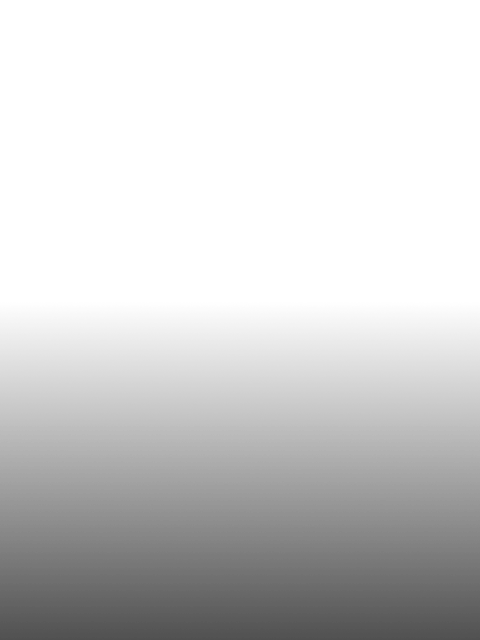前編:ジィージル出会い編(大丈夫、ホモじゃないよ!!!)
長くなったので前後分けます。後編はまとまり次第投げに来ます。
「だから、何度も言わせんなよ、その気はないって言ってるだろ」
もう何度目だ、こうやって花街で袖を引かれるのは。それも一夜の誘いではない。こんな痩せっぽっちな子供が女を買うような金を持っているはずもない。店に並べというのだ。小奇麗に飾られた艶やかで淫らな女と同じぐらい高値のつく、色物の花にしようという心づもりで、こうして身寄りのない子供に声をかけているのだ。まだ無理やり攫ってしまわないだけ、随分良心的だと言えた。為政者は政治に関心を失い、この国はひどく傾いていた。そんな中、取締もろくに行き届かない花街で人道的な取引をもちかけてくるなど、店の歴史に自信があるか、懐に余裕がある商売上手といったところか。だがしかし、女を物のように売り買いする人間に対する少年の不信は大きかった。男を買おうという者の気もしれない。今日もこうして計算高い手を突っぱねて、目尻のきつい大きな蒼い目で女衒を睨む。その勝気で初心な表情は整った顔立ちを歳よりもやや幼く見せ、今から店に仕込んでも何年かは使い物になりそうだと思わせてしまうことを少年は知る由もない。だが美しい花は枯れるのも早いということを考えないほど、少年は愚かではなかった。ここでいくらか稼ぎが良くなっても、二十代も半ばの歳になれば売り物にならなくなる。そうすれば体を売るしか稼ぎ方を知らない者の末路など決まっている。惨めな凋落と破滅だ。そんな死に方をするなら、綺麗なまま野垂れ死んでやると、少年は不器用な高潔さを胸に、まだ引き止めようとする女衒を無理やり振り切る。揶揄の言葉と嘲笑を背に受けながらうつむき加減で唇を噛んで大股で裏通りを飛び出したところ、前を見ていなかったことも手伝って、脇道から出てきた男と派手にぶつかってしまった。たたらを踏んで、叩きつけそうになった悪態をすんでのところで飲み込んで見上げた人間はまだ歳若く、随分背の高い男であった。
「すみません」
下手に絡まれたくないという思いもあり早口に謝って脇をすり抜けようとすると、その青年が肩を軽く掴んで引き止めてくる。
「ねえ君さっき…」
「なんの用だよ…!」
また声をかけられる。一日で二度という事実は少年の事を荒立たせたくないという気持ちを吹き飛ばす。肩に置かれた手を乱暴に叩き落として振り返り、なにか罵ってやらなくては気が済まないと振り仰いだ青年の目を見て、少年は小さく息を飲んだ。
突然声を荒らげた子供に少し呆れ気味の驚きの表情を浮かべて面白がるように唇を緩ませたその青年の瞳の色は、否応なく血の色を連想させるほどの純粋な真紅。体の色素を持たない白子に赤い目が希に現れるというのは聞き知ってはいたが、本物の紅い瞳を目にするのは初めてであった。少年の凝視を感じ取ったのか、男は悪戯っぽく瞬くと長身をかがめた。
「この目が珍しいかい?」
軽薄で人懐っこそうな笑みが唇に張り付いていたが、細められた目に浮かぶのは妙に空々しい熱のない表情、あるいは空虚さ。その寒々しさに少年はたじろいだ。
「みんな大抵、初めはそういう反応をするね」
そう言ってどこか自虐的な調子でまるで人ごとのように言い捨てる投げやりさに気圧されたことが悔しく、少年は背筋を伸ばして男を真っ向から見上げた。そうしてみるとだらしなく気崩れてはいるものの身につけている物は仕立ての良さそうな上着や手触りの良さそうなシャツなど、明らかに貴族か、あるいはそれに準ずる裕福な上流市民出身であることを示していた。客引きでも女衒でもないなら、この町の客だ。肩にかかるほど伸ばされた明るく線の細い金髪と、目鼻立ち一つ一つは穏やかで柔和な作りだが少しばかり粗野な表情も相まって、まるで結婚詐欺師のようだなと少年は内心ひとりごちる。
「で、何の用だよ。俺は売りはやってない」
「買いに来たってのはわかるんだねぇ」
「あんたみたいなのがこの街ですることって言ったらそれぐらいだろ、お貴族さん」
「喧嘩っ早いかと思ったら、存外に人を見る目もあるようだね」
えらいえらい、と馴れ馴れしく頭を撫でる手を少年に忌々しげに叩き落されて、青年は苦笑いを零した。
「だけど不正解。君みたいに小さい子に手を出すほど外道じゃあないよ。さっきの勧誘みたいなの、よくされるのかい」
どうやら見られていたらしい。不躾な質問に少年はぶすくれる。どうせ細くて白くて男らしくないとでも思われているのだろう。
「時々。でも全部断ってる」
つっけんどんに答えにも、青年の熱を映さない態度は変わらない。
「君みたいなのは高値がつくから、売る気がないならこんなところ、出て行った方がいいだろうね。何処の店もああいう紳士的なやり方とは限らないから」
「今のこの国じゃどこに行ったってろくな仕事なんてないよ。特にこんな痩せたガキができることなんか何もない。こうやって人が沢山いるところのほうがまだマシだ」
言い募るうちに妙に腹立たしい気持ちになってくる。腹が空けば気が立つが、それ以上に成長期だというのに栄養が足りないせいか背が伸び悩んでいる自分と、目の前の男の惚れ惚れするほど恵まれた体格を比べて、いったいこの男と自分の境遇を分けたのはなんだったのかという実のない疑問に苛立ちが湧き起こる。
「悪いけど、あんたの同情じゃ腹は膨れないんだよ。あんたはこうやって名前も知らないガキに同情おしつけてりゃ満足かもしれないけどな、まだ金のほうがありがたいよ」
特に急ぐ用もないせいもあって、強く話を遮ってこの場を立ち去る理由が見つからなかったせいか、言うつもりのないことまで口をつく。せめて仕事があれば良かったが、それさえも心もとないというのに、この遊び呆けていることを許された身分の青年と同じようにここに立ち止まって時間を無為にしている。青年はそんな複雑な心境を知ってか知らずか、おもむろに上着のポケットに手を突っ込むと、一枚の硬貨を引っ張り出して、二人のそばに積まれた木箱の上に静かに置いた。その色に少年は思わず目を奪われる。
金貨だった。
少年がそれなりに安定した幸せな家庭で暮らしていた頃でさえ、そうそうお目にかかれるものでなはい、最も重い金貨だった。
「じゃあ名前を聞いても?」
金のことには触れず、青年はそう聞いた。道を尋ねるような気軽さだった。それに少年は無理矢理視線を金貨から引き剥がし、剣呑な目で睨めつけた。
「断る。教える義理がない。それにこんなもんいらない」
「そっか」
それだけ呟いたが、青年は金貨を引っ込めることはぜず、相変わらず冷めた目で飢えた野良犬のような少年を見下ろしていた。青年が何かを思いついたように口を開きかけたとき、表通りから女の声が掛かる。
「ねえ、ジィーベン、何をしてるの?」
その婀娜っぽいふしだらな声に少年は盛大に顔を顰めた。あからさまな表情に思わずといったふうに青年は苦笑して、女の声にすぐに戻ると返してから、身をかがめて少年に抑えた声で囁く。
「貴族街外れの3番地、若いのを探してる偏屈がいる。身売りは無しだけど、多分他のどんな仕事よりもずっと厳しい。だけど君みたいな子が、相応しいかもしれないね」
青年はそれだけ一方的に伝えると、ふたたび少年のくしゃくしゃの黒髪を乱雑に撫でるとぽんと軽く叩いて、払いのけられるよりも早く身を引くと、ひらりと手を振って待たせている女のもとへと去っていく。
残されたのは煤けて色あせた木箱の上に、不似合いな金貨。鋳造からそう年の経っていないであろう、縁も刻まれた皇帝の横顔もくっきりとした黄金。それ一枚で、少年は食いつなげる、誰のものでもなくなって、今はただ石ころのように転がる贅沢。あの青年にとってはおそらく人肌で、少年にとっては暖炉で、この寒々しい夜を凌ぐことのできる金色の気まぐれ。
だがそれを手に取るのは、少年にとっては敗北に思われた。何に負けるわけでもない、ただ道端の石を拾うような事でも、決定的な敗北であるように感じられた。それから目をそらし、立ち去ろうとするが、足がひどく重かった。歯を食いしばり、脳裏に焼き付いた空虚な紅い瞳の残像を追い払い、少し裏路地を進む。振り返ると、まだそこにある。いずれ誰かが見つけて、信じてもいない神に幸運を感謝して、なんの葛藤もなく持ち去るのだろうか。そう考えると、こうして未練を感じる自分を棚に上げて腹立たしさを覚えた。ふと少年の胸に、預かっておくだけだ、という考えがよぎる。それも所詮言い訳に過ぎなかったが、次に会った時に落し物だと言って返せばいい。いや、叩きつければいい。同情なんて糞くらえだと、そう言って笑ってやろう。
くだらない意地だと自嘲する自分を感じながらも、それは随分名案に思われて、少年は足早に取って返すと金貨を素早くつかみ、誰にも見られないようシャツのポケットに押し込んだ。
ずっしりと重い感触が胸に伝わったが、その場を立ち去る足取りは幾分勇み足であった。
貴族街外れの3番地。少年は金貨一枚よりもずっと価値のある者を青年によって与えられたことを、まだ知らなかった。
《前編完》
フォロワさんでRPG詰め所


 *REVOLVER
*REVOLVER