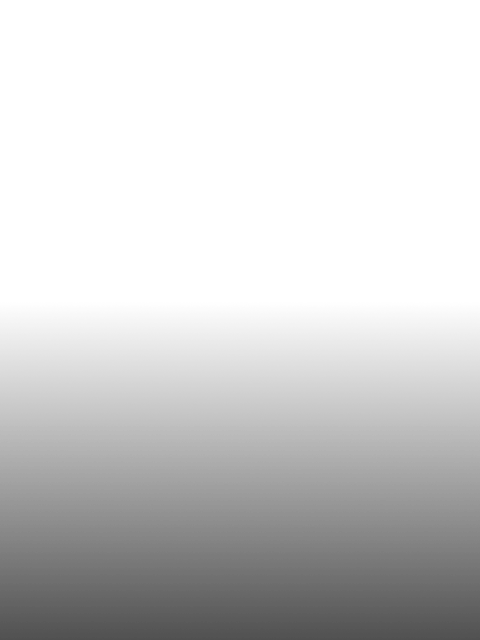マイナーピースはチェックを狙う
(特務隊の戦闘スタイルとかお仕事とかの雰囲気小説です。例の後編はまた今度…)
「馬鹿なことを…」
ジルキオは嘆息する。槍を向け自分を取り囲む私兵達と勝ち誇った表情で兵をけしかける男を、片目を眇めて眺める。敵意なきことを示すために剣を預けたため全くの丸腰で、これ以上ないほどの危機的状況だというのにまるで他人事のような態度ですらあった。
「犬を始末して、その先はどうするおつもりです?仮に私を殺せてもて、露見するのに一日とかからないでしょう。その先のことはお考えになっていますか、パーヴァス卿…」
言葉に嘘は一つもない。既にパーヴァス卿は翻意ありと中央から目をつけられているのだ。革命に不満を持つ前体制派の一派である彼のきな臭い動向を危険視して内密に逮捕命令が下されたが、反乱を実行に移す前ということもあり表向きは調査同行依頼のためと称して接触した。しかし話し合いもそこそこにこの有様である。政敵の重要人物ながらこの軽はずみな行動には呆れて憐憫の念すら湧く。馬脚を現すにしても考え無しにも程があった。
「命乞いと交渉はもっとうまくやるべきだったな黒犬…!残飯漁りが似合いの貧民が身の丈に合わぬことをするからだ」
優位を確信してるがゆえの同情めいた傲慢さが言葉の端々に臭う。先帝の庇護に甘んじてプライドだけ肥え太らせた男の肥大しきった慢心に、ジルキオの涼しい面差しに不快の色が過ぎる。
「命乞い…それをするべきは貴方でしょうに」
先代の特務隊隊長が死亡し跡を継いだばかりの、齢もまだ30に遠いジルキオは先代の威を借る若輩者と軽視される向きが強く、こうして舐められることもままあった。組織の頭が変わっても、公爵の猟犬たる特務隊の鼻も牙も鈍らないということを知らない者はあまりに多い。
「これは警告です卿よ。与えられた機会は有効にお使いなさい。もう一度だけ、お願い申し上げます。我々特務隊に『ご協力』を。貴方にしか語れぬことがございますので」
無数の切っ先を向けられてなお全く動じず、辛抱強い静かな口ぶりで説得を繰り返す。戦わずに済むならそれに越したことはない。だがそんな姿勢を虚勢ととったか弱腰と見たか、パーヴァス・ハクスリー爵は嬲り殺しを夢想するかの如き表情で、蛇が舌を鳴らすような嘲笑を歯列から漏らしてはっきりと首を振った。
「貴様らに語る言葉など持ち合わせてはおらんわ、盗人公爵の犬め!」
「…そうですか、残念です」
その一言が結ばれるよりも早く、ほとんど無防備にすら見えたジルキオの手が目にも止まらぬ速さで突きつけられた槍の柄を捕らえて兵の一人を引き倒し、倒れ込んできたその兵の腹に石突きを叩き込む。返す手でもう一人の腕を掴んで捻り上げて足を払い、瞬く間に膝をつかせると腰に下げられた片手剣を奪って手早く喉をなで斬りにした。
二人が地に伏せるまでの間になんとか動揺から立ち返って次の一手を警戒する他の兵たちから距離を取り、油断のない目で間合いを計る。包囲したまま攻めあぐねている兵が六名、さらに広間に詰めているものもめいめい得物を取りじりじりと距離を詰めてくる。今は二十人ばかりだがすぐに増援が駆けつけるだろう。
突然の反攻に泡を食ってパーヴァスが広間の勝手口側からまろぶように逃げ出していくのと同時に、控えさせていた部下二人が交渉決裂を察知して正面扉から突入してくる。
「ボス、無事ですか!?」
「手間取りすぎだエヴァレット、剣を!クローディア!パーヴァス卿を捕えろ、生かしてだ!」
「了解です」
簡潔に一声返事を残して、栗色の髪をひとつに結った細身の女がパーヴァスを追ってゆく。鳥のように身軽で猫のように音もなく駆け抜ける彼女は、その魔術の才でジルキオの命令と期待を裏切ったことはなかった。今度も間違いなくそうなるだろう。
同時に部屋に飛び込んできたもう一人の青年が右手に血に濡れた剣を引っさげ、左手にひと振りの優雅な長剣を抱えて駆け寄ってくる。彼は新手の登場に矛先を変えた兵たち数人を無造作に薙ぎ払いながら人使いの荒い隊長に抗議した。
「これでも急いだんですよー、全力で!」
ジルキオはどことなく間延びした部下の青年の言葉を無視して、粗悪な片手剣を投げ捨てると自身の手に馴染んだ鋭いレイピアを受け取る。
「下はどうなっている」
「とりあえず押さえました、軍から借りた連中と一緒に封鎖にあたっています」
「申し分ない、あとは彼らの相手をするだけだ」
広間には特務隊隊長の実力を目の当たりしても戦意を失わない兵が踏みとどまり、それどころか騒ぎを聞きつけて駆けつけてくる者でその数は増えてゆく。
形勢は相変わらず人数で劣る特務隊が不利に思われたが、ジルキオは切っ先を下げるようにレイピアを構え、兵たちの次の動きを余裕の佇まいで待った。エヴァレットは使い込まれた剣をやや高く構え、隊長の一手と敵の顔色を伺っていた。その表情には場違いな愉快そうな色が微かに滲む。焦れるような睨み合いの拮抗はすぐに崩れた。
一人の兵が間合いの優位を確信して果敢に繰り出した槍をジルキオは半身を捻って躱し、左手の甲で柄を押しのけて相手の懐に躍り込む。その大きな一歩の踏み込みで一瞬のうちに不利な間合いを踏み越え、勢いのままにレイピアを相手の胸へと突き入れた。よく手入れされた刃は容易く肉を貫き、鈍い感触を腕へと伝える。びくんと痙攣して崩れ落ちた肉体を蹴り飛ばして剣を引き抜き、さらに手近なもう一人も片付けた。
全体の連携が取れておらず、重大な局面で冷静さを失っている兵たちの動きを見て、実戦経験なしと判断する。近年大きな戦もなく、革命派の一方的な粛清と貴族私有の騎士団解体が断行され、兵力の国軍一極集中体制へと再編成されたことで、中央の新体制派と地方へ飛ばされた旧体制派との間の力関係は急速に天秤を傾けつつあった。その影響が如実に現れた嘆かわしいほどの練度。もう何人か始末して脅せば戦意を挫けるだろうと読む。
無謀にも突っかかってくる者の斬撃は真っ向から受け止めず、細身の刀身で羽で触れるように軽く受け流す。相手の隙を誘い、無駄な手数は一切挟まず、確実に急所を貫き、それでもまだ立ち上がろうと足掻く者の背を念入りに軍靴で踏みにじる。できるだけ残虐に見せ、揺さ振りをかけて動揺を生み、一気に心を折る。このような無慈悲な行いを容易くやってのけるためにしばしば死の前兆と忌み嫌われる黒犬になぞらえられる冷酷な男は、しかし、ほとんど美しいといっても良いほどの剣筋を誇っていた。
今また左足を引いて上体を逸らし攻撃を避ける、その危ういバランスを保つために上がる左手の指先から、狂い無くレイピアを振るう右手、次の一歩へ淀みなく繋がる足さばきに至るまで、まるで一曲の音楽のように心地よい緊張感に満ち自然な連なりを描く。修練と実戦の中で何度も繰り返し磨き上げた楽章に相手を引き込み、自分の独壇場で流れるように殺戮する。たった二人に対して束になってかかっても傷一つ負わせられないどころか仲間が次々と倒れていく事実に、さすがに数で勝る兵たちにも動揺の色が見え始める。
「隊長、そろそろじゃないですかね」
「ああ、頃合か」
ざっくばらんだが柔軟で機敏な剣筋で補佐していたエヴァレットも形勢が傾いたのを感じたのかジルキオに声をかける。適切な読みに頷き返してやりながら一旦切っ先を下ろしてぴんと背筋を伸ばすと、きっぱりとした蒼い目で生き残っている兵たちを眺め渡した。
「これが最後通告です、投降しなさい。今ここで武器を捨て我々に帰順したものの命は保証しましょう」
「死にたくないでしょ、うちの隊長、殺るときは殺るよ」
エヴァレットも剣を担いで相槌を打つ。
何かを成すのに、誰よりも早く行動するのは難しいことだが、誰かが言い出さねばならない。しかし誰も剣を捨てようとはしない。兵同士はお互いの顔色を伺い、互いの圧力に動けずにいた。
とその時、ほかよりも立派な制服の男が一団から躍り出ると、剣を腹の辺りで構え、死に物狂いで突進してきた。
「公爵の犬に売る魂などありはしないぞ!!」
凶暴な感情に男の表情は歪み、ぎらぎらとした目と無感情な蒼い瞳の視線が交錯する。だが勝負は一瞬だった。ジルキオは猪突猛進な一撃をあくまで冷静に、闘牛士のようにひらりと躱して手首を返し柄頭で顎を強打した。頭を突き抜けた強烈な衝撃に膝から崩れ落ちた男の肩に間髪入れずにレイピアを突きたて、叩きつけるように床に押し倒す。呆然と大の字に転がり口から血を流す男の投げ出された腕を踏みつけ傲然と立ちふさがると、ジルキオは燃えるような氷の目で男の愕然とした顔を見下ろした。
「…貴方が兵隊長殿ですね?貴方の可愛い部下たちにひとこと、命を大事にするよう伝えて頂けませんか?」
肩から豊かな黒髪が流れ落ち、ジルキオの冷たい表情をぞっとするような色に翳らせる。慇懃な言葉を紡ぐ薄く控えめな口元だけ妙に女じみた形をしていたが、それは優しさを連想させることはなく、むしろ底冷えした端正な面差しを一層恐ろしげに見せていた。
床に伸びた兵隊長は悔しげに唇を噛んでジルキオを睨みつけたが、肩に突き立てられた剣をぐいと押し込まれてうめき声をあげ、憎々しげな表情を隠そうともせず、砕かれた顎を難儀して動かしてやっとのことで投降を命じた。
「みな、武器を捨てて、犬野郎にしたがえ」
兵たちは顔を見合わせたが、苦々しい顔で次々に武器を足元に投げ捨て、その場に膝をついて投降の意思を示した。
それを見届けるとジルキオは兵隊長の肩から無造作に剣を引き抜いて足をのける。思わず見とれてしまうような優しげな作り笑いが彼の鋭い目尻に張り付いた。
「勇敢なご判断とご協力に感謝致しますよ、兵隊長殿」
完全な敗北を悟って抵抗を一切やめた兵隊長と投降した兵たちをエヴァレットに任せ、ジルキオはパーヴァス卿追跡に放ったクローディアを追いかける。広間を出て廊下を抜け、足早に階下へと向かうと、クローディアが階段を下りきったすぐ近くで凛とした背を見せて佇んでいた。その足元に目をやれば芋虫のように転がされたパーヴァス卿の姿もあった。単純だが有用な捕縛魔術で拘束されていることをひと目で見てとって、大股で近づく。
「クローディア、ご苦労。随分静かだが、塞いだのか?」
「ええ、女性の前で口を開かせるには少々躾がなっていませんでしたので」
ジルキオにも劣らぬ冷淡な声に煩わしげな忌々しさを漂わせて彼女は柳眉を顰めた。捕縛して拘束する間、口汚い女性蔑視論にでも付き合わされたのだろう。気の毒なことだ、と転がされたパーヴァス卿に視線をやる。クローディアは気に食わない相手に優しくするほど淑やかな性質ではなかった。
「まったく、困りますね、パーヴァス卿、貴方のご立派なご両親の品位まで疑われるような振る舞いは」
クローディアに合図して沈黙の魔術を解かせると、パーヴァス卿は顔を真っ赤にして押し込められていた罵倒を撒き散らした。
「その父を殺したのは貴様だろう犬め!あの成り上がりのエセ公爵の靴を舐めて尻尾を振ったんだろう!いいや、振ったのは尻尾だけじゃなさそうだなメス犬が!その上女に権力を与えるなど惰弱で恥知らずな!何処の馬の骨ともしれない貴様のような乞食がのさばるようでは帝国は御終いだ!」
四肢を折り曲げて縛り上げられた体をよじって一息にまくし立てるパーヴァス卿を、ジルキオは顔色一つ変えずに見下ろす。そばで小さく「下衆が」と吐き捨てて戒めの魔術をきつく締め上げるクローディアを手で制して片膝をつき、拘束の痛みに呻き声をあげながらもまだ何か飛び切りの侮蔑を必死に考えているのであろうパーヴァス卿の憤怒の形相を覗き込んだ。
「そうですね、貴方の知っている帝国はもう御終いです。ここから先は、私たちの帝国となる。貴方の言葉など、もう我々に届きはしないのですよ、パーヴァス卿」
革命勃発より5年。先帝の遠戚に連なる、前時代の有力貴族の復権の要とも言える男がついに執政派の猟犬に追い詰められた瞬間であった。
フォロワさんでRPG詰め所


 *REVOLVER
*REVOLVER