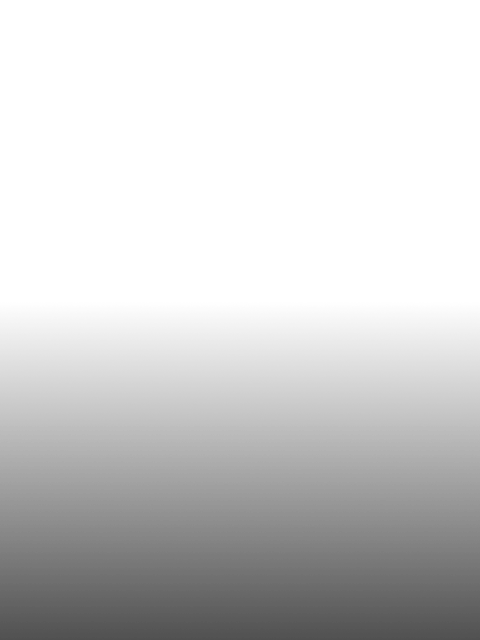闘技場脱出直前
そこはまるで牢獄のような、最底辺に位置する剣奴の部屋。ひどく高い位置に設けられた格子窓からは日の光が差し込んでいて、宙に舞う砂埃を照らしている。その先の日の当たる場所に、二人の少年はいる。ヴラドは粗末な藁の寝床の脇に座って、かつて「金色の蛇」と呼ばれ、栄光のすべてを手にしていた闘士の亡骸を見下ろしている。ヴラドはゆっくりと彼の身体の下へ手を差し込み、そっと抱きかかえた。
――「いまをもって、俺とおまえは兄弟だ。なあ、こんなくだらねえことでお前は死ぬな。ひとりでも生き延びろ。安心しろよ、俺が死んでこの体が腐り果ててクソ以下の存在になっても、地獄の底からお前を見ててやる。お前を愛してる。絶対に忘れるなよ。俺を、忘れないでいてくれ」
これがルカの最期の言葉である。
生まれて十数年、食事と人殺し以外に使ったことのなかった生傷だらけの両腕に、初めて抱く人間。それは枯れ枝のように痩せこつれ、たった今自分の兄となった人間の亡骸。強く抱きしめると、ぽきりとどこかの骨が折れる音がした。しばらくの間をおいて、ヴラドは彼をゆっくりと床におろした。闘技場へ向かおう。次の試合がいつも通りの熱気と狂気をもって始められるだろう。今回ばかりは処刑という方が正しいかもしれない。
「もういいのかよ?ありゃ、死んじまったか」
ドアの前で見張りをさせられていた太ったごろつきが話しかけてきた。
部屋を覗き込んで大きな溜息をつく。
「しっかし金色の蛇ともあろう闘士がこんなみじめな最期だとはなァ…ラガルト様もむごいお方よ。しかしヴラド、お前もこれからどうすんだ。試合に出たところで無駄死にするだけだぞ。なあ、おれの知り合いの連れにジャックって逃がし屋がいる。今からでも遅くはねえ!そいつに頼んで…」
ウラドは何も答えず、ごろつきの肩を二度叩いてその場を立ち去り、闘技場へと向かった。
「行っちまいやがった。…ルカ坊よぉ、お前の弟も直ぐにそっちへ行っちまうかもしれんぜ」
「…かれは試合に出るのですね」
「ああ…ん?…うわぁ!」
太った男は大仰に驚いて尻餅をついた。いつの間にか背後に眼帯をした少年が立っていたからである。
見た目はまだ10歳程で、どうやってここまで入り込んだのか見当もつかない。
少年はヴラドの去った方向へすたすたと歩きだ出し、男の脇を通り過ぎる。
「全くどこのボンボンだ!ここはガキの入っていい場所じゃあねえぞ!くらぁ!」
男が振り返って怒鳴った時には、少年の姿は煙の如く消えていた。
フォロワさんでRPG詰め所


 *REVOLVER
*REVOLVER