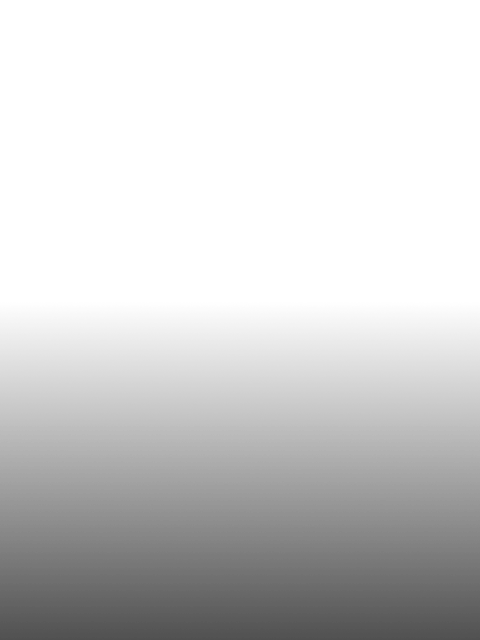ウラド君過去編、闘技場私刑編
――闘技場でヴラドを待っていたのは、割れんばかりの歓声と茹だるほどの熱気、そして通常の試合ではありえない数の「対戦相手たち」だった。土埃の舞う地面には、少なくとも百人近くの敵がすでに各々の得物を抜いて立っており、ヴラドへあらん限りの殺気を投げかけていた。うんざりして上を見上げると、青空が妙に近くに見えた。陽の光に目を細める。
この残虐な舞台は全て、ヴラドの飼い主であり稀代の大商人、ラガルト=ホーキンスが用意したものである。ヴラドの「兄弟たち」を、皆殺しにして。
ラガルトは特等の貴賓席に招待された飢えた好き者の諸国貴族や富豪らの前に立ち、まるまると実った葡萄をひとつ、つまみあげて言った。
「仲間をひとり残らず食べられてひとりぼっちになったかわいそうな灰色オオカミは、これから自分で積み上げる死体の山の上でその血に溺れながら死ぬでしょう。来賓の皆様方に謎かけです。死体の山の死体の数は幾つかな?」
ぽいと口に頬張った葡萄を咀嚼しながら、ラガルトは手を打つ。
運び込まれていた大きな銀の杯に、ラガルトは足元にあった金貨の詰まった袋を投げ入れた。どしゃん、と派手な音を立てて杯が揺れる。
「さてさて皆様方、果たして奴が何人殺れるか、賭けをなさいませんか。ええ、ええ。皆さまが怪訝に思われるお気持ちは重々承知しております、この只ならぬ人数差は馬鹿馬鹿しく思えるでしょうが、それは皆様方があまりやつのことを存じ上げぬがゆえにございます。やつはあまり表舞台へは上がっていないだけで、私の集めた闘犬の中でも最強の手練れなのです!…私がかつて愛した「金色の蛇」を凌ぐほどにね。並の雑魚では到底かないません」
ラガルトはわざとらしいため息をつく。
「ですが私の悪い癖がここにも出てきてね。少々飽きが来てしまったのですよ。悲しいかないつの世でも、人の時代は変わらなくてはならないのです。しかしただ処分するのは勿体無くて。そこでこの刺激的なイベントを思いついたのです。はたから見ればただの私刑でしかありませんが…くく、あの犬はそう簡単には死にませんよ!さあさあ、懐をもっと重くして帰りませんか!ともあれ皆様方、この素晴らしい舞台をともに楽しめることは、私の無上の幸せに御座います!どうか、血沸き肉躍る戦いをお楽しみください!」
貴族らに歓声と笑い声が沸き起こる。杯が金貨であふれるまで、そう時間はかからないだろう。
ラガルトはくるりと振り返り、高く通る声を張り上げた。すかさず彼に付いていた下女がひざまずき何かを小さく呟くと、彼の高く通る声はさらに増幅され客席の隅々にまで響きわたった。
『【闘士ヴラドの首を掲げた者に、莫大な賞金を、自由な身分を、最高の栄誉を】』
これが剣奴たちに布告された試合の勝者への褒美である。
富への欲望、栄誉への熱望。自由への渇望。様々な望みをかけた者たちが、この舞台に押し寄せてきていた。歴戦の剣奴から痩せこけた亡国の農夫までもが。
最高の舞台が用意できたはずだった。しかし、当のヴラドがあまりに冷静に見えるのが気に喰わない。捨て鉢を犯すのは趣味ではなかった。
気に喰わないが、あいつがただ殺されることもないだろう。遥か下にいるウラドを睨め付け、ローブを大げさに翻し背を向け、自身も席に着く。
「まあいい。始めろ」
ウラドは処刑開始の合図をただ待っていた。構えもしない。表情もさして変わらない。
ラガルトの所有する軍団が「金色の蛇」と手下の剣奴、果ては取り巻きのチンピラまで皆殺しにしたのも、ヴラド一人を殺さずに残したのも、全て「飼い主」の指図であることをヴラドは薄々と理解はしていた。だが理由がわからなかった。自分たちが何をした?期待に応えるべく命がけで戦い、血を流し、飼い主たちに富をもたらした。なのになぜ。残り勝てる見込みのない試合に逃げようともせずにいたのは諦めでも意地でもなく、どうすればよいかわからなかったからだ。今まで持ったことのないはずの感情。しかし腹の底にはどす黒いものが確かに湧き上がってきている。これは何なんだ。俺にどうしろというんだ。飼い主は自分を見捨てたのか?ルカ…兄は死んでしまった。自分を慕ってきたあいつらももういない。身内を一人残らず一気に奪われたウラドは衝撃の大きさと自身の感情にまだついてゆけずにいた。自分の感情を識る術を教える大人は、彼らの周りにはいなかった。
その時、視線をぼんやり泳がせていたウラドは確かに見た。遥か向こうの金持ちどもの座る席で、見覚えのある輝きを。
飼い主が振り返った時に翻ったローブのすき間から、陽光を腰に差された「それ」が反射した。それは紛れもなく兄の、ルカの短刀だった。
その瞬間、確信した。認めるしかなかった。飼い主に理由などなかった。これは遊びだ。からかわれているのだ。面白がっているのだ。おもちゃの人形に飽きた子供がその四肢を捥ぐ様に。
渦巻いていたものがウラドの頭の中で音を立てて決壊した。思わず頭を抱える。声にならない呻きが漏れる。
体が震える。初めて味わう真っ黒な「怒り」が、のように身体を広がっていく。
故郷を奪われた頃の記憶がないヴラドだったが、家族を奪われるのはこれで二度目だった。ヴラドの体に長い間とぐろを巻いていた怪物が、深く刻まれじくじくと溜めこまれた憎悪がようやく解き放たれ、殺戮を求めていた。
「かえせ、おれたちを、おれたちのすべてを、かえせ…」
ヴラドは絶叫した。得物も構えずに、開始の合図を無視して敵の只中へと突進した。
―――二十六、二十七、二十八。脚に、腹へ、首を。
応えるかのように、雄叫びとともに突進してくる剣奴たち。躱して、いなして、斬る。止まっている暇は一瞬たりともない。視界に現れるモノを片っ端から殺しまくった。思考は既に消え失せ、今までせき止められていた激情が体中をのたうち回りヴラドの四肢を突き動かした。しかし正気を失いながらも、その動作は恐ろしい程に正確だった。次々に振りおろされる武器の切っ先をくぐりながら、鎧のすき間を瞬間で見定め、そこへ刀身を叩き込み、哀れな獲物を糞袋へと変えてゆく。まだだ。まだ殺す!
兜の中の眼を潰し、喉を潰し、躱し損ねれば首輪で受け止め、両手がふさがれば首の肉に喰らいついて噛み千切る。容赦は一切なかった、自分にできる最短の時間で敵の命を終わらせる。
およそ六十人を斬殺する頃、敵の大半は尻ごみを始めていた。慎重になり始めたのか、周りを取り囲みながらじりじりと間を詰めてくる。それと同時にヴラドは徐々に冷静さを取り戻し始めていた。息も上がってきている。始めに殺した敵から奪った血塗れの剣をその場に捨てて、そばにあった死体を蹴りよけ、転がり出る自分の血に染まることのなかった剣を拾いあげる。浴び続けた夥しい量の返り血で、顔と身体は真っ黒に染まっていた。その時、自分の黒い首輪がゆっくり熱を帯び始めていたことに、ヴラドはまだ気付けないでいた。
闘技場の丸くくりぬかれた空からはぎらつく太陽の光が剣奴たちの背を焦がし、揺らめく彼らの影を繋いで黒い波のようにうねらせている。
フォロワさんでRPG詰め所


 *REVOLVER
*REVOLVER