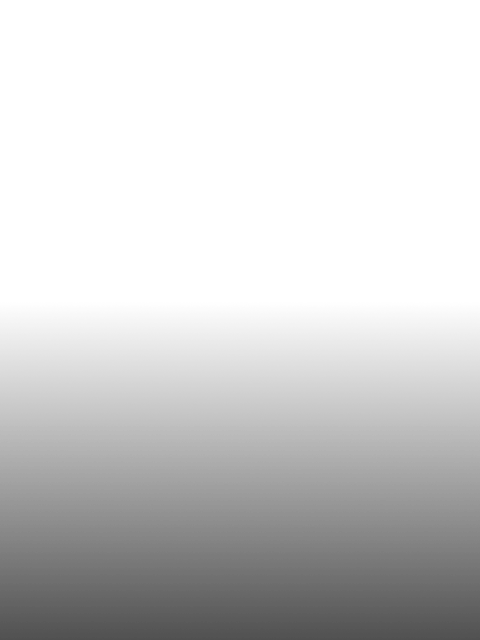科学班にて(すみません、ツバキ博士だいぶ勝手に動かしてしまいました…)
その日は、百年に一度と言われる嵐が島全体を包んでいた。
豪雨と暴風が、木々をなぎ倒し、そこかしこに暮らす生物の生命を脅かす。まだ日中であるにも関わらず、深夜のように闇に包まれた空に時折猛烈な雷光、即座にバリバリと音を鳴らし天地にヒビ。天から落ちたのか、はたまた地上から生えたのかわからない、恐ろしい数の稲妻が走る。
「素晴らしい!!今日をおいて他にこれほど最高の日和はないである!!」
天地を揺るがすかのような騒音に歓喜の声を上げたのは、この島にある科学班の博士・ツバキであった。帝国領の付近に浮かぶ島(とはいえ、どこの領地にも属さない無人島である)に、科学班はある。元々どの種族も暮らしていない緑豊かな無人島であったが、俗世から離れ実験に没頭するためだろうか、博士はここを本拠地として日夜怪しげな実験を行っている。他の国々や、種族達には到底作ることは不可能であろう機器が研究所に所せましと設置されている。博士の科学力や技術は外界と同じ時間が流れているとは思えないほどだ。その力を我が物にしたいと要求する国は後を絶たない。
「雷からのエネルギーは本日予定している強化実験へ有効に利用できるかと思われます。現在エネルギー質量および充填量を計算中…」
涼やかに話す女性の声…恐ろしく透明度のあるその声の主は、試作4号“D”。しなやかに指先を動かし、空中に浮かぶ透過した画面を見つめ何らかの計算をする。腰まであるサラリとした銀の髪、鼻筋の通った整った顔…、海面に緑のインクを少し垂らした雫をそのまま閉じ込めたような瞳は、まばたきすらしない…彼女は博士に作られた人造人間だ。
美しい肢体の色は銀色に光り、雷光の度にキラリと照り返す。彼女がはじき出した数値をみて満足そうに博士は頷いた。
「うむ、何もかも予定通り!吾輩の予想が的中したであるな」
眼鏡を押し上げニカッと、さも嬉しそうにギザギザの歯を見せて笑う博士に、少しばかりため息をついて残念な表情を浮かべてみせる、もう一人の人物…-。
「ええ、賭けは吾輩の負けのようです。さすがはツバキ博士」
ボサボサと伸ばしっぱなしになった朱色の長髪が印象的な彼は、ツバキ博士の助手・マガトキであった。ひょろりとした長身に長く伸びた手足。切れ長の瞳は金色に光り、厚みの薄い唇には普段から微笑をたたえているせいか、先ほどの曇った表情もすぐに消えていた。彼には少し特徴のある箇所がある。耳の部分には蜻蛉の羽のようなものが3対生え、額には角が1対。異形の者特有の風体であったが、以前はそこらにいる人間たちと何ら変わりのない好青年の姿だった。科学班に入り、人体実験を幾度か自身にも施した結果現れた症状だという。
「そうであろう、フフフ、さあ、今日こそは件の実験、成功させてみせるである!!!」
ツバキ博士は興奮ぎみに目を見開き、豪雨で荒れ狂う外からの音さえかき消すほどに大声で叫んだ。
生物実験は毎日のように行っている。被験者の強化、合成、…材料となる生物は比較的たやすく準備できる。奴隷の売買が日常的に行われているのだ。場合によっては国家の兵士強化をと、進んで提供してくれる某国もある。
しかしこの日生物実験する対象は、少しそれらとは違った。
科学班で細胞から作られ、大きく成長した人造の獣。獣とはいえ、知能も高く筋力はケタ違いに強い。獅子のような姿に額からは水牛のごとく巨大な角が生えている。全身は、赤褐色の体毛で覆われ、見るものを圧倒させる巨体であった。名前はカーエデール。博士は敬意をこめてその獣を『卿』と呼んでいた。
「博士」
重低音でボソリとつぶやく。実験を行うため、ベッドに横たえられた獣は目を細め博士を呼ぶ。
「…卿、大丈夫である。これからさらに卿を強く、そして希望通り翼を授ける準備は万端である。吾輩に任せるである」
ゆっくりカーエデールの額を撫でて笑う博士に、獣は嬉しそうに鼻をフフンと鳴らした。そして真似るように博士の髪を撫で、彼の言葉に安心したように瞼を閉じ、深く息をした。
マガトキは様子を見ながらカーエデールの肩付近から麻酔効果のある薬剤を打つ。
「科学班のためにこの身体、捧げる所存。信じていますよ、ツバキ博士」
それだけ言うと、静かに眠りについた。
「脈拍正常、血圧は通常よりやや低めです」
Dが淡々とカーエデールの状況を説明しながら、記録していく。まったく無駄のないその動きはさすが人造人間といったところだろうか。ツバキとマガトキは目を合わせ、術式用の手袋をパチンとはじいた。実験開始の合図だ。
背部に“翼”になるだろう小さい羽根とピンク色の肉塊をねじ込む。縫合しながらDからの情報を聞く。その後、今度は横腹から少し刃を入れ、皮下をめくる。脈動する臓器に新たな生体装置を取り付け、縫合。
何もかも順調に進んでいた。
――最後の仕上げをする、その瞬間までは。
「さあ、総仕上げである。エネルギーの準備は?」
「すべて完了しています。」
「よし、マガトキ。解放装置を」
「エネルギー解放。カーエデールに注入します」
瞬間。
強烈な光が研究所内を包んだ。
否、光だけではなかった。轟音と共に青白い閃光は研究所の装置すべてを起動停止にさせ、カーエデールと助手であるマガトキを貫いてしまった。
「卿!!」
博士は叫んだ。閃光のせいで眩暈がする。耳も先ほどまでの豪雨で騒がしかったのに突然の轟音の後、無音のようになった。自分自身の叫びも、体内の底で響くだけに思えた。
じわりじわりと耳鳴りが起こり、通常の音になるまで時間がかかった。
「卿!!」
博士はもう一度叫ぶ。今度は声が聞こえる。長いまつげをぐむと瞑り、目が慣れるのを促す。必死で目を凝らすと、傍らに倒れるDの姿があった。
Dは、ほかの装置同様、強烈な閃光の後自力で動くことができなくなっていた。衝撃で記憶装置にも支障をきたしたのかもしれない。エラー音を鳴らしながら、博士に訴えている。歯をギリっと食いしばり、彼女の電源を落とす。
「少し待っているである…」
博士は三色に分かれた自髪をガシガシと掻いて、苛立つ様子を見せた。部屋の最奥部でバチ、バチと装置が鳴り、その奥から焦げたようなにおいが漂ってきた。
ソレは、黒鉄色をした咆哮する獅子の彫像。
――いや、彫像ではなかった。
絶句しながらも、心のどこかであまりの美しい形状に歓声をあげたくなる。それほどに、その黒鉄色のソレは、獣そのものの姿をしていた。しがみつくようにする人型も、そこにあった。
「卿…」
博士はそっと手を伸ばした。指先が、一瞬触れる。
途端に、黒鉄色の彫像はボロボロと崩れ、砂山のように足場に積もる。あわててかき集めるけれど、握りしめるとただ手のひらを黒く汚すだけで、何もつかむことは出来なかった。
すべてが灰になった。
それを認識したのか、自嘲するように狂気じみた笑いを浮かべた。すべて失ったのだ。
嵐はまだ止んでいない。騒音の中、徐々に落ち着きを取り戻した博士は、ふと灰の山に何かがあることに気付いた。
(――また崩れてしまう)
一瞬躊躇して、手を引っこめる。すると、もそりと山がうごめいた。
別室の実験動物がまぎれたのだろうか。
さらにもそりもそりとうごめき、灰の山から赤いものが見えた。
「…手?」
驚きながらも急いで灰をどける。そこには全身が緋色のつるりとした肌に、頭に1対の角をもつ、小さな生物が丸まっていた。
その姿は胎児に似ていた。
よく見ると背中に薄い羽根をもち、長い尾のある猫のような生物だ。
「卿?まさかカーエデール卿なのであるか?」
博士がそういうと、丸まっていた生物は起き上がり、ぼんやりとした糸目で見返した。
「…吾輩…、よくおぼえてないけど、ツバキ博士のことはわかるよ」
にこりとして微笑むその顔は獣ともまた別の誰かにも似ていたが、博士にはそれが誰だったのが思い出せない様子だった―――
「…これが、あの日起きたことですよ」
口元に微笑をたたえながら、ゆっくり話し終えると彼はツバキ博士に視線を合わせた。
「…では…、その、君が助手の」
「ご無沙汰しております、博士。嗚呼…やっと再会を果たすことができました」
博士は目をぱちくりさせてもう一度、“助手”と名乗る男の姿を頭からじっくりと見回す。
――やはり覚えがない。たしかにあの日、雷の暴走で閃光を浴びた記憶はあるが…
「いや、待つである。その話だと獣であった卿と助手は消し炭になったのであろう?なぜ…その…、君は」
「今は新月卿と名乗っております」
「あ、ああ、そうであった。なぜ何のケガもなく…生きた姿をしているのである?」
博士の問いに少し落胆した様子を見せる男…新月卿であったが、すぐにまた微笑を浮かべた。スッ…と眼差しを外に向け、静かなる闇夜を見つめる。
「貴方は吾輩に吸収する力を授けてくれた。吾輩は閃光が起きた瞬間、衝撃でカーエデールの身体にしがみつく形となったのです。閃光は吾輩たちを包み、焼き焦がしていった…その時、吾輩の一部がカーエデールと一体化し、今のカーエデール卿が生まれた。彼のものが日々過ごすにつれて、生み出す細胞を吾輩が少しずつ吸収し、吾輩は体内でひそかに再生を目論んでいました。
貴方も知っているでしょう。あの子は月の光で生命力を維持していることを。月が欠けるにつれ、あの子は徐々に眠りにつく時間が増える。そして、今宵のような新月の日…吾輩は新月の日のみ現れることができるようになったのです」
静かに、淡々と話す彼の横顔は夜空をぼんやりと見つめ、少し恍惚とした表情をみせていた。外からは涼やかな風が木々の葉を擦る音が聞こえる。
「そうであるか。…うむ。よくぞ戻ってきたであるな」
「ええ、まだ賭けの配当をいただいていませんから」
新月卿はそういうと、博士ににじり寄った。博士はギクリとして椅子から転げ、そのまま壁際まで追いやられてしまう。
「な、…ま、まて!その賭けは吾輩が勝ったのであろう?!」
息がかかるほどに近距離まで詰め寄られ、視線をあちこちに反らせて逃げ場を探す博士の姿にうっとりとしながら、新月卿は両手を壁に這わせて動きを封じる。
「いえ、残念ながら吾輩が勝たせていただきました」
唇が触れるか触れないかの距離で、さらに続けた。
「貴方はこう、言いました。『今日こそ記憶に残る偉業を吾輩が成すのである!どうだ、賭けてみるか、マガトキ』」
新月卿はそうつぶやくと口元に微笑を浮かべた。博士はただ、目を泳がせることしかできなかった。
フォロワさんでRPG詰め所


 *REVOLVER
*REVOLVER