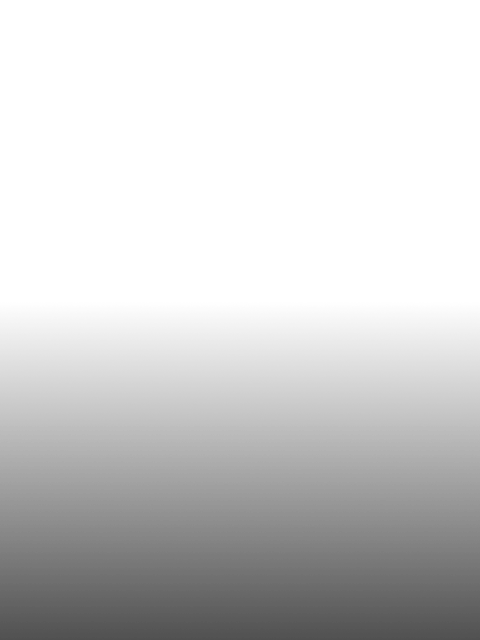ある宿にて
時は夜更け。降り出していた雨はいつの間にか勢いを増して大雨になっており、ざあざあと降り続けている。
…ここはとある国の市街の大通り。時間帯と降りしきる大雨のせいでひと気は全くないが、ふだんは大変な賑わいを見せる活気ある街である。住民の大半を占めるのは、およそ中流下流に位置する民衆。すなわち商人や工員、農夫たちである。その「民草たち」が毎夜ぎゅうぎゅうに集まっては安酒をやけくそにあおる、大きな古酒場があった。
嵐のようないつもの喧騒もようやく終わりをつげ、歌も注文のがなり声ももう聞こえない。外の大雨と今にも轟音とともに稲光を落としてきそうな雷雲の唸り、ジョッキを握ったままに酔い潰れカウンターに突っ伏した貧乏農夫の大いびきと、暖炉のぱちぱちとはぜる音、ひとり店に残った店主とみられる女のせっせとグラスと食器を片付ける音だけが響いている。
その酒場の真上に当たる二階には、八畳ほどで木造りの、二つのいすと小さなテーブル、かび臭いダブルベッドが一つ。あとは箪笥がひとつという古びた部屋があった。
そこに宿を取っていたのは、後ろに結わえた真っ白な長髪と顔の右半分の刺青が目を引く、二十代半ばほどの目つきの悪いが精悍な青年と、まだあどけなさの残る十四、五歳ほどの赤毛の少女。刺青の青年は窓際に置いた椅子に腰掛け、くわえた煙草から紫煙をくゆらせながら、窓の向こうの暗闇をじっと見つめている。窓枠は大粒の雨に打たれ頼りなくがたがたと音を立てて震えていた。少女はすでにベッドで眠りに落ちていた。
青年はしばらく窓のそばで座っていたが、ふと顔をしかめると小さく舌打ちをした。
「ち、撒ききれてねーな…昼前に片付けたハズなんだがな」
気配がする、三人。夜の暗闇と雨音に紛れて這い回る気配を、青年は深いため息とともに煙を吐き出しながら、容易く感じとっていた。
「三匹か。そろそろ来るなこりゃあ。この雨ン中ご苦労なこった…げほっむほっ!おええ!ぐぬぬ、火葬場の煙でもこんなまずかねーぞあの野郎」
青年は苦虫を噛み潰したような顔をして、まだ慣れない煙草を握りつぶしてうしろへ放った。
「あ、途中ですてちゃだめだよ。博士におこられるよお?」
いつの間にか目を覚ましていた少女、いや、少女が寝ていた場所には白い角をはやした緋色の小さな猫のような妖精がいた。しかし猫と違って体毛はなく、大きさは先ほどまでいたはずの少女の頭ほどしかなかった。背中には薄い青色で半透明の羽が生えており、細長い尻尾をゆらゆらと揺らしている。
「ヴラド君のたましいを『ひきとめる』けむりなんだよ。それに、すごくいいにおいじゃない」
青年が妖精の方を振り向いた。全く驚くそぶりも見せない。
「うるせーな。起きたのか、丁度良かった。んなことよりすぐにお客さんが来るぜ。見たところ本職の方々だ。お前にはまだちょっとキツそうだな。終わるまでベッドの下にでも入ってじっとしてろ」
「え、でも昼間は森でどろぼうのおじさんやっつけたよ!」
「はあ、あんな雑魚と一緒にすんな!あいつ火掻き棒しか持ってなかったじゃねえか。まあ今回は見学がてら温存しとけ」
「はぁい。でも床からじゃ何にも見えないよ~、にしてもすごい雨だね!」
妖精はひとつ寝返りを打つとそのままストンと床に落ちて、ころころとベッドの下へ転がって行った。
「うえ!ほこりまみれだよ!クモの死体にねずみのふんもある!げええ~」
2人は追われている。それもずいぶんと長い間。もう三年近くになるだろうか。とうの昔に追われる理由はなくなってしまった筈だったが、青年は忘れられるには如何せん恨みを買いすぎていたし、少女(今は妖精だが)にも追われるべき「途方もない価値」があった。どれほど遠く離れていようとどこからともなく追手たちが現れ、その度に男が追手を手痛く撃退してきた。
つと稲光が輝き、雷鳴が轟く。雷光に照らされたゆらめく影を青年は見逃さない。
賊はどうやら早くも位置に着いたようだ。向かい側の建物の屋根に一人、窓の直線状にいる。おそらくは射手。加えて酒場の入り口に一人。そしてこの酒場の屋根にも一人。
青年は焦るそぶりもなく、足元に立てかけた、鞘に納まった幅広の曲刀のような武器を手に取って立ち上がり、窓の脇の壁にもたれかかった。
「ふう…」
深く息を吸い、ゆっくりと鞘からナイフを外してゆく。二度目の呼吸をし終わる前に、再び雷鳴が轟く。同時に窓ガラスが割れた。射手に放たれた矢弾が窓ガラスを突き破ったのだ。
矢はベッドとカモフラージュの為に丸めた毛布に深々と突き刺さり、さらにその下にいる妖精の頭をかすめた。
「どわあ!?」
続けてこの建物の屋根にいた一人が飛び降りて、割れた窓から器用に身を捻って侵入してきた。が、そこへ間髪入れず身を潜めていた青年が組み付き、三度の膝蹴りを敵の腹にめり込ませる。ひゅっ、という掠れた呻き声とともにうずくまった敵の腕と胸の辺りをつかみ、そのまま割れた窓をさらに破壊しながら外れた窓枠ごと投げ飛ばした。
「っし、あと二人」
土砂降りの雨が部屋になだれ込みはじめ、流れ込んで来た外の音でにわかに部屋の中が騒がしくなる。
豪雨と雷鳴に紛れ、酒場の人間に気付かれることなく侵入してきたのであろう二人目が部屋に躍り込んで来た。先ほどの敵もそうだったが、全身を黒装束で包んでいる。
「とうとう雇われまで使いだしやがったか。ウンザリだな。確かに退屈はしねえけどな?お前らもうちょっと場所と時間を考えろよ」
話しながら青年はベッドの枠につま先をかけている。
「…笑止」
敵は手に持っていた抜き身の長い倭刀を八相に構えた。
「そうかよ」
次の瞬間、青年は一気にベッドをつま先で蹴りあげた。もんどりうって目の前に倒れこんで来たベッドを敵はすばやくかつまっぷたつに叩き割ったが、割れたベッドの影から現れた青年の影まで捉えることは出来なかった。胸とみぞおちに拳を叩きこまれ、あばら骨が折れる音が聞こえる。
「くぉっ…」
かすむ視界にでたらめに刀を振ろうとしたが、後ろに回り込んだ青年に容赦なく蹴倒され、頭を鷲掴みにされて床にしこたま打ちつけられたあと、そのまま一人目と同じように窓から投げ捨てられた。
「今の死んでないよね?まったく、どうやったらあのベッドがけり上がるんだろ…」
いつの間にか角の箪笥の上に避難していた妖精がたずねる。
「ああ、いたんだっけなお前!ケガねえか?悪い悪い。まあ大丈夫だろ、あのくらいで死ぬようには見えねえし。窓の下見てみな、とっくにいねえと思うぜ?」
「もうひとりは?」
「とっくに逃げたろ。気配も消えた。いやあ今度のは大したことなかったなあ」
「傷一つないもんね。吾輩は死にかけたけど」
妖精はふわりと浮いて、窓枠だったであろう場所に着地した。
「つめたっ!…あらほんとだいない」
「だろ?…じゃ、とっととばっくれようぜ。こんなとこでおちおち寝られねえよ、明日には騒ぎになる」
「えー」
翌朝、竜巻が来たような水浸しで悲惨な状態の部屋と、酒場の前に散らばった血糊にまみれた窓枠の残骸が、その街のちょっとしたニュースになったのは言うまでもない。
2人は追われている。それもずいぶんと長い間…
おわり
・・・いつもの恥ずかしい言い訳
(集中力が切れてしまって途中からずいぶんと乱文雑文になってしまいました。雰囲気だけお楽しみください。雰囲気だけ!)
フォロワさんでRPG詰め所


 *REVOLVER
*REVOLVER