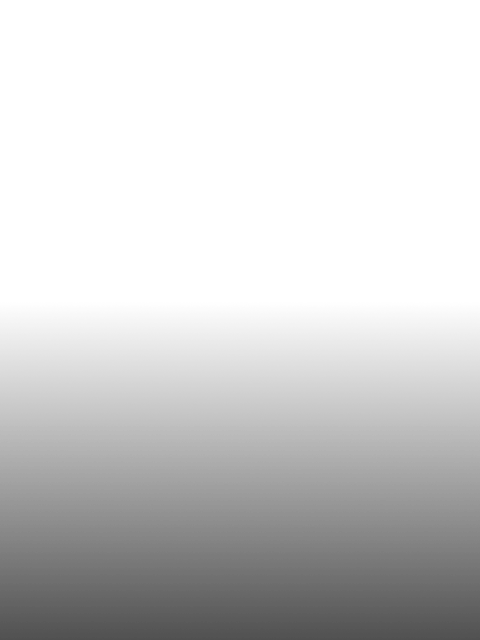初戦
(設定:どこかの帝国領の城から逃げる海賊団。海に面した崖に沿って建てられた背後は断崖絶壁の城。ヴラドは船長と殿をつとめていたが、時間稼ぎのために単独、ジルキオ率いる騎士団を迎え撃つ)
廊下の角を曲がると、全力で逃走する一団のなか、賊らしくない海賊団の中で唯一「悪党」然としていた白髪の青年がたった一人、曲刀のような異国の武器を抜いて立ち止っていた。その青年に対峙した追っ手たる騎士の一隊は相手が一人なのにもかかわらず、何故か思わず立ち止まってしまう。突然ひとり立ち止まっていた青年に意表を突かれたこともそうだが、青年が殺気か気迫か、形容しがたい「うねり」のような空気を発していたからだ。
「は、足止めにたった独りだけとは、無謀以下のもはや大馬鹿だな!見捨てられたか?あわれな下っ端め!」
兵士の一人が気を取り直し、挑発しながら槍を構える。青年は何も答えずにただゆっくりと腰を落とし、武器を逆手に持ち替えた。
「この・・・!」
兵士が動こうとした時、隊を率いていた騎士がそれを制した。
「あれの相手は私がする、手出しは無用。お前たちは行きなさい。あのような者どもは決して逃がしてはならない」
「まさかあのような下手人の挑発に乗るおつもりですか!?」
騎士は何も答えず、ただ視線の先にいる青年を見据えている。
「…わかりました。おい!行くぞ」
兵士は隊列に命令し、青年の脇を走り抜けていった。全員一切青年に手を出さなかったが、青年も兵士らを止めるそぶりを全く見せなかった。青年にとって、向こうが決闘の形式をとったことは僥倖であり、それに従うのが最善の選択でもあった。
ゆっくりと、しかし確実に騎士は青年へのほうへと歩を進め始める。どうやら青年の発する「うねり」はこの騎士には殆ど通用していなかったらしい。むしろ迎え撃つ青年の方が表情が険しくなってきている。騎士は腰に差していた二本の剣のうち一本を抜いた。美しい曲線を持つ柄の上質なレイピアだ。
騎士は精悍で整った、劇役者の二枚目のような流麗な顔立ちをしており、それを引き立てるように長くのばした黒髪はまるで物語の中の人物の様であった。ともすれば王の風格さえ持ち合わせているかのように見える。それに対峙している青年は、ぼさぼさの白髪を半分に刈り上げ、服もろくに着ておらず、全身には刺青。極めつけに黒い首輪まではめている。もはやそのいでたちは王の前に引き出された奴隷に等しかった。
先に動いたのは青年だった。全速力で騎士に突進し、直前で地面を蹴り騎士の顔面に向かって躍りかかる。
騎士はその場でほとんど動かずに、腰と腕の動きだけで淡々と青年の攻撃、二回の蹴りと三回の斬撃をいなした。
そして青年の隙をまるで決められていた動作をこなすかのように生み出し、青年のみぞおちに向かって的確にレイピアの柄をめりこませた。
普通の兵士なら悶絶するであろう一撃だったが、青年も素人ではない。痛みをいったん無視してすぐさまレイピアの切っ先の届く範囲の外へと飛びのいてから、改めてやって来る痛みをやり過ごす。まさか一撃も入らないとは予想もしていなかった。
「ぐう…」
青年は騎士と初めて会いまみえてからその力量の高さをびりびりと感じていたが、今の剣戟でそれを確信に変えていた。
格が、違う。理由はわからないが、手加減さえされているだろう。青年は自分がすべきは時間稼ぎであって勝つことではないのは十分にわかっていたが、出会ったことのない程の大きな力量差と意図のつかめない手加減、加えて涼しげな騎士の冷徹な視線に青年は苛立っていた。
「俺は上から見下ろされるのが嫌いなんだよ」
青年はしゃにむに飛びかかる。が、結果は同じ。
今度は真正面から頬に拳を叩きこまれ、もんどりうって倒れ伏した。
「何度やっても同じですよ?しかし、悪くない動きですね。それに異様なくらい殴られることに慣れている。独特の受け流し方だ」
騎士は視線を落とし白い手袋をはめた手の甲に染みた血を見ながら言う。
「そりゃどうも…げほっごほっ」
青年は切った口の中の血を勢いよく吐き出して答えた。
「殴られたダメージはさほどではないのでは?戦闘の経験で言えばおそらく私よりあなたの方がすこし上なのでしょうね。しかし、あなたには師と呼べるものがいなかったのではないですか」
「…なぜわかる」
「何故って、殆ど貴方の剣には守る動作がありませんよ。噛みつくだけなら犬でも知っていますが、守りと反撃の完成は独学できるものではない。型ですからね。貴方の剣はただ相手より早く、あるいは多く斬りつけようとするのみで、勝利の先にあるものへの欲求がない。勝って、生き残りたいという本来あるべき原理が存在しない。あるのは死への早すぎる道のりだけ。相手の、いやその死は自分にさえ向けられている。命を、試している。かつての奴隷仲間の真似でもしているのですか」
「グダグダとうんちく垂れてんなよカマ野郎。俺が誰の真似をしてるって?」
再び青年は騎士に突進するが、落ちる木の葉を叩こうとするが如く躱され、蚊を叩くが如く脇腹を剣の峰でしたたかに打ち据えられた。
先ほど殴られた二か所のようにごまかす余裕をあたえない、骨の軋むような一撃。
呻き声を上げながら後ずさる青年。ここまでか。青年は覚悟を決めかけていた。かすんで揺らぐ視界。口の中は血の味で一杯だ。もう力量差なんてどうでもいい。あとどれだけ長く立っていられるか…と考え始めた時、青年は「それ」を見た。
廊下に並ぶ大きなステンドグラスの窓枠のひとつに、赤いねずみだろうか、丸っこくてちいさな生き物が見える。見間違いだろうか?いや「それ」は間違いなくこちらを見ている。小さく震えながらおびえた目で二人の男の行く末を見守っている。ずっと後になっても本当に何故だかわからなかったが、青年はその時、自分の視界がすうっと晴れていくような感覚を覚えたという。自分がいま、すべき事。求めるものがわかったという。
「…要するにひとつ確かなことは、あなたの剣には我がまるでない、ということ。そのように空虚な牙では私には届くはずもない。如何せん軽すぎる。さて、うんちくはこれで終わりにしますよ。次は斬ります。残念ですが逃がしもしません」
膝をついている青年につかつかと歩み寄り始めながら、騎士は自分に驚いていた。たかが賊一匹に何故自分は講釈など垂れているのか。脱走奴隷を育ててどうする?地べたを這いずり回る凶暴な子供に自分と通ずるものでも感じたか。意味なんてないはずだろう。なによりもう殺してしまうのだから。
「くくく…なんでもかんでも見透かしてくれやがる」
青年は笑っている。血反吐にまみれた歯をむき出しにして。
「お前、犬に噛みつかれたことあんのかよ?」
騎士が最後まで聞き取る前に、青年はまた愚直に突進し仕掛けてきた。なにかが変わった様子もない。が、問題はそのあとだ。
先ほどと同じように、青年の見え透いた攻撃をいなそうと剣を動かした瞬間、そこにあったのは傷だらけの曲刀ではなく、青年の二の腕であった。短いフェイントを挟み、刀身に直接腕をぶつけて来たのである。これは騎士の予想外であったがもう遅い。肘を高く上げ、V字に曲げた腕の肘から上の部分と手首にみるみる刃が食い込み出血がはじまる。筋肉と骨に挟まれた剣は一瞬だが狼狽えた騎士の動きを阻害した。
青年は刃が食い込んだままの腕を捩って騎士の足を踏みつけて肉薄し、騎士の額に自分の額を押し当てて言った。
「噛みついてやるよ、騎士殿」
青年が思いきり千切れかけた腕を振るい、ついに騎士から剣を引きはがした。腕を犠牲にした代償にこじ開けた隙を逃さず、残った方の腕で騎士の顔に渾身の拳を見舞った。宙を舞った剣は高い音を立てて石の床に突き立つ。騎士が膝をついた瞬間、青年は踵を返して走り出し、ステンドグラスの大きな窓を突き破って遥か下の海に飛び込んだ。
―そのしばらくのち、騎士は何も言わずに立ち上がり、剣を拾い上げて鞘に戻す。
「つっ…ふふ」
口元の血を拭うと、思わず笑みがこぼれた。顔を思いきり殴られたのは一体どれくらい振りだろうか。
「逃してしまったな。これは重大な失態だぞ、騎士殿?」
振り返ると、そこに笑みをたたえながら立っていたのは君主であるマシュー公であった。腕を組み、壁にもたれかかっている。
「…いつから見ておられたのですか殿下。恥ずかしながら後れを取りました。処罰は如何様にもお受けいたします」
「おや本当か。遊んでいたのではないのか?お前ほどの剣士があのような雑魚に手こずるとは思えんが…それに、最後に至ってはお前、わざと拳を受けたろう?」
「滅相もございません。殿下、まだ賊が潜んでいるやもしれません。早く奥へお戻りください」
「わかったわかった。それよりも早く冷やしておけよ?二枚目が台無しになるぞ。ははは」
マシュー公は両手を上げて、笑いながら立ち去った。
「やれやれ」
騎士は溜息をつき、破れた窓を見やる。生きていればいつかまた剣を交えることになるかもしれないと、騎士ジルキオは最後にもう一度うっすらと微笑んだ。
おわり
あとがき
段落?何それ知らん
キャラクター勝手にしゃべらせてすみません。(相変わらずジルキオの勝手なイメージが暴走してます)
剣術やその他うんちくは完全に雰囲気と思い付きで書いておりますゆえ中の人やお詳しい方は鼻で笑っておいてください。おこらんといて
フォロワさんでRPG詰め所


 *REVOLVER
*REVOLVER