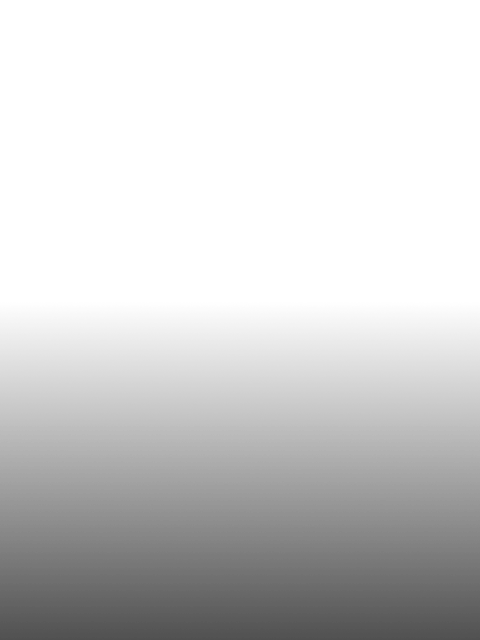初戦、その後
さらさらと海が波打つ音と、口の中の砂の不快な感触が、切れていたヴラドの意識をゆっくりと引き戻してゆく。それにつれ、身体の節々が感覚を取り戻してゆくかのように痛み始める。
「う…」
ヤシの葉から洩れる陽の光がまぶしい。起き上がれるだろうか。その前に、自分がなぜ今こうしているかをぼんやりと思い出してみる。
海賊と城で公爵に喧嘩を売って、逃げる途中であの長い髪の騎士の足止めをして、窓から飛び降りて…あの高さからよく助かったものだと、自分でも思った。その時、ふとあの騎士に言われた言葉が、全く歯が立たなかった剣戟とともによみがえる。
「虚ろな剣だ」
「師と呼べるものがなかったのではないか」
ヴラドは顔をしかめた。腹が立ったのは、それを否定できなかった自分にだ。あの言葉を言われた時、真っ先に思い浮かべたのは兄ルカの顔であったが、思い返せばかつて師と仰いでいた筈の兄は、確かに自分に剣を教えたことは一度もなかった。自分はその殺しざまをひたすらに真似るしかなかった。相手より早く、多く斬りつける方法を。兄もまた誰にも何も教えてもらうことなく生きてきたのだろう。その傑出した才能は、ついに誰にも拾い上げられることはなかった。遺されたのは兄の影を追い続けた自分だけ。
もっと強くならねばならない。兄の真似でなく、「自分の戦い方」とその「使い道」を手に入れなければならない。理由はまだ見つからないが、ヴラドは確信めいた思いを持ち始めていた。あの騎士のようなやつらが他にもいるだろうか。もっと戦いたい。もっと、もっと知りたい。戦いに勝って聞きださねばならない。あの時に獣人から兄に助けられた理由はなんだ?闘技場から出るとき、あの魔術師がこうまでして自分の命を繋ぎとめたのは何故だ?それは自分が強くなりさえすれば、全部この剣が聞きだしてくれる、わからないことは全部。そんな確信。
思いを巡らせていると、ヴラドはあることを思い出した。自分の腕はどうなった?捨て身の一撃を加えるためにくれてやった腕。
目をやると、当たり前だがやはり腕はなかった。そこで妙なことに気が付く。妙に切断面がまっすぐで、何より出血も、痛みさえほとんどなかった。止血すらしていないのに。加えて浜辺に打ち上げられたのならこんな砂浜から離れた木陰にいるだろうか?おもわず起き上がる。すると少し痛みが走った。よく見ると、見覚えのない紋様が傷口の周りに刻まれている。刺青ではないようだった。
辺りを見回すと、すこし離れたあたりに城で見かけた赤い生き物が丸くなってすやすやと寝息をたてているのを見つけた。近くで見るとネズミというよりは猫のような姿形だが、とんぼのような羽と白い角が生えている。
「一体なんなんだあいつは?よっ…と」
とりあえずその場で立ち上がってみる。骨は不満そうに軋むが、折れてはいない、どうやら動き回る分には大丈夫そうだ。
なくなった腕の方の肩をさすりながら、ヴラドは赤い生き物に近づいてみた。しゃがみこんで覗き込む。生き物はよく眠っていた。
頭を鷲掴みにして持ち上げてみるが、起きない。よだれを垂らし、眠ったまま微笑んでいる。じつに幸せそうだった。
ヴラドは少し考えてから、生き物を持ち上げて胴体からかじりついた。
「うぎゃあー!?」
生き物は実に人間らしい悲鳴を上げた。
「イタイ!!なんで!?待って!!食べないで!イタイ!助けたの!吾輩!助けたのに!あイッタイ!痛い!いぎぎぎ…」
噛み切れないし、不味い。それに助けがどうとか言っている。
しばらく咀嚼を試みたが、しぶしぶ解放した。勢いよく宙に舞い上がる奇怪な生き物。
「喋るし飛ぶし食えないネズミ…」
ヴラドのもらした漠然とした感想に、生き物は空中を浮遊し腰に手(前足?)を当て、憮然として反論した。
「失礼な!吾輩はカーエデール卿!きみを助けたの!大変だったんだから!落ちるきみが海に叩きつけられる前に空中に印を展開して受け止めて、水の舟をあみこんで、潮の流れをよそくして、海の上で傷口を塞いで…ここまでやっと運んで、せいこんつきはててたというのに!全く!向こう何年か分の魔力ちょぞうがなくなっちゃったんだからね」
「…ありがとう、ハエ?」
とりあえず礼は言う。命を救われたのだ、
「あ、いやあ、たいしたことないよ…えへへ」
なぜか生き物は頬を赤らめて照れている。話を聞くに、ただの動物ではないらしく、自分を助けるために全力を尽くしたことはヴラドにもわかった。理由はさっぱりわからないが。
「で、ここはどこだか知ってるか?」
「ずいぶん流されたからね、魔力の濃さからして皇国ではないし、吾輩たちの後ろの森のにおいからして多分だけど『お腹』の辺りじゃないかな。多分ここは森を抜けた先の海岸だとおもうよ。あとハエじゃないよ」
「ち、やっぱ全然わかんねえ…あいつ、無事かな」
「船長たちは無事だよ。君はそれよりその腕を治さなくちゃいけないよ。吾輩の印も長くはもたないしね」
「わかるのか」
「わかるよ。みてたもん」
「そうか…で、やばいのか、この腕」
赤い生き物は口に片手をあてて考え込むように話し始めた。
「ふつうのけがだったら止血してれば傷口は癒えるんだけど、きみの全身にある印はどれも欠けちゃいけないものだったんだ。何を封じてるかは知らないけれど、こんなにふくざつでみごとな印は今までに見たことがないよ。吾輩にはむずかしすぎて判断がつかないけれど、腕が無くなったことで印の均衡が崩れてる。吾輩の止血の印も方式の全くちがうのを上書きしたものだし、いずれ『きょぜつはんのう』が起きるとおもう。はやく博士に見てもらわないと痛い!!なんで!?」
赤い生き物は頭をさすっている。
「何言ってるか全然わからん、要はそのハカセってのが何とかしてくれるんだな?」
「うくく…そうだよ。この森を抜けてかなり南にくだらなきゃいけないけどね。本当は吾輩が飛んで案内できればいいんだけど、もうあんまり高くはとべないんだ…森に一人吾輩の知り合いがいるから、もしその人に会えれば森の抜け方がわかるかも知れないよ」
「そうか、じゃあまずそいつに会いに行こう」
「えっ」
「案内しろって。この辺のこたあ全く知らねえんだ、俺より方角くらいはつかめるんだろ?」
「そうだけど…それって吾輩が一緒に行ってもいいってこと?」
赤い生き物はおずおずと尋ねる。ヴラドは赤い生き物に背を向けて、身体の節々を伸ばしながら答えた。
「他に誰がいんだよ」
「…わーい!!やった!やった!!やったあ痛っ!!なんで?」
赤い生き物は頭をさすっている。
「うるせえからだよ。…腹減ったな。」
頭をぼりぼり掻き乍ら、青い海を見つめる。
まずは食料を調達せねばならない。ここはどうやら人の住んでいる場所ではないらしい。「あれ」は食えなかったし、狩りなんてしたことがない。ヴラドが覚えていかなくてはいけないことは、戦いのほかにもまだ山のようにある。
「あー…はぁ」
思わずため息が漏れた。
「どうしたの」
「なんでもねーよ」
当てもなく、彼は浜辺を歩き出した。
自分が見つけるべき答えを迎えに行くために。
おわり
【ほそくといいわけ】
改行とか文節をもっと学校で真面目に習っておくべきだった。
Fsrpg世界地図で言う「竜のへそ」の辺りに流れ着いたヴラドは…的な話です。
これから続き物にできたらなあと思ったり思わなかったり。最後の方ちょっと面倒くさくなって無理やり締めたのは内緒ですねん。あと投稿が自分ばっかりになっていくのがはずかしいしさみしいので誰かなんかかけ。俺の自尊心の為に!
フォロワさんでRPG詰め所


 *REVOLVER
*REVOLVER