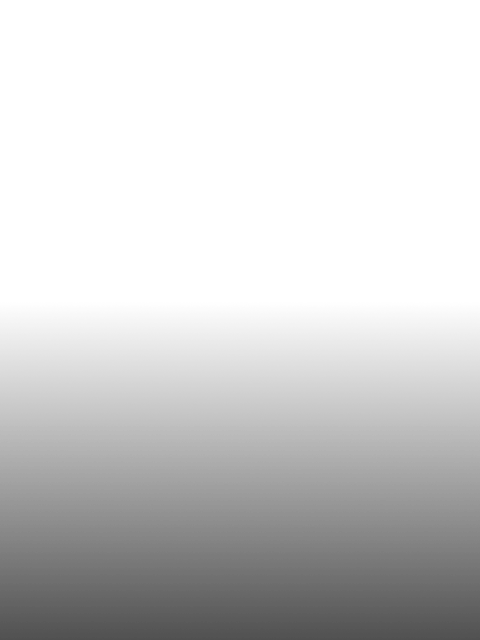いまだ蒙昧という名の夜 (革命期)
自由には二種類あるものだと、“黒犬”と呼ばれた男は信じていた。
混沌と、秩序だ。その両方の中に自由はあった。あるいは、自由の中にその二つがあるのかもしれない。
とにかく男は自由には二つの種類があるのだと考えるに至った。彼が二十にも満たぬ年だった頃にはすでに、そのような鋭く忌々しい諦観に支えられた思想をきっぱりと刻み込んでいた。以来十数年その結論は揺るぐことがなかった。
男は自由を二つに選り分け、そしてそのうちの一方を激しく憎悪した。混沌の上に成り立つ自由を嫌悪し、そして排除しなければならないと決意していた。
それは思うままに殺し、生娘を犯し、貧しい者から盗みを働くことを咎めぬ自由だった。何もかもの悪辣が野放しにされ、法は死に絶え、君主が放逸を極めた時代に、民衆の間で蔓延した病のような自由だった。その悪徳は腹が空けば平気で盗み、口喧嘩の先に決闘を起こし、裏路地に泥にまみれた半死半生の娘を転がした。疫病は流行るままにされ、薬は常に足りず、薪さえ満足に手に入らない。だが、どんな罪さえも咎める者はいない。それも自由の形だといえた。
だが男は肉親を混沌のもたらした自由によって奪われていた。無計画な戦で父を、病で母を亡くし、そして最愛の妹は悪徳の栄えにあやかった貴族に辱められ、少女のうちに命を絶った。
当然の帰結として、まだ少年だった男は混沌を純粋に憎むに至った。そして病理を取り除き、秩序による自由をもたらさなければならないと誓ったのだ。
だがその時、彼自身がまだ吹きすさぶ嵐のような理性なき怒りに囚われていた。煮詰まった鬱屈と義憤の境目を見分ける術を持ってはおらず、またそれを自覚してもいなかった。
「なにを言おうと無駄だ、ジルキオ。今のお前を認めるわけにはいかん」
激しく打ち据えられて全身の感覚が滅茶苦茶になっていた。腕が痛むのか背が痛むのか判別がつかず、頭に直接脚の疲労が接続されているかのようだった。
革命派の暗い地下の隠れ家では、時間の経過も曖昧だった。物騒な炎を燃え立たせる炉のせいで部屋は熱が篭り酷く息苦しい。窒息しそうな視界がぐらぐらと揺れ、ぐずりと膝が萎え、手を突き出す間もなく前のめりに床に崩れ落ちる。地を掻いて立ち上がろうとするジルキオの腹に容赦なく硬いブーツのつま先がねじ込まれ、勢いよく跳ね飛ばされた体は受身も取れずに転がった。
“狼”が自分をなんの感慨もない目で見下ろしているのを感じて、ジルキオは遠のきかけた意識をなんとか捕まえる。
“狼”―この壮年の厳しい男は革命派の中でも選りすぐりの戦闘員を鍛え上げ、特殊な任務に当てるための手駒として育てていた。“狼”は見込みのない者を掬い上げてでも手勢に加えるほど寛容ではなかった。ここで自失して倒れ込んだままでいれば、“狼”は自分を見限るに違いない。そう考え、なけなしの気力をかき集め、床に落ちた訓練剣を拾ってがくがくと震える脚に鞭打ち立ち上がる。汗にまみれてべったりとまとわりつくクシャクシャの黒髪がひどく煩わしかった。
「やめにするか?お前には無理かもしれんな。可哀想に、立つだけで精一杯だな」
「…いいえ…まだ、やれます…!まだ…!」
懇願するように絞り出しながら、なぜそうまでしてしがみつくのだろうと自問した。軋む体の苦しさが意志をだらしなく引き伸ばし、限界に近い疲労のせいで強烈な眠気のような虚脱がまとわりついて来るのを必死に払いのける。
ジルキオ自身は同じように訓練を受けている者たちの内で誰よりも飲み込みが早く上達も群を抜いているという自信があったが、何が気に食わないのか、“狼”は度々彼をひどく叩きのめし、ほかの誰も負ったことのないような怪我と精神的痛手を被るまで追い詰めることがあった。
「やめてもいいんだぞジルキオ。つらいだろう?」
「やめません、続けてください、お願いします」
負けを認めてなるものかとばかりに息せき切って食いつくと、“狼”は奇妙な、侮蔑のような色を微かににじませた。
「…そうまでして復讐したいか」
虚を突かれた。
「復讐のために使う技術などここにはないぞ」
「俺は、復讐をしたいのではありません…二度とあんなことが起きぬようにと…!」
「そのために悪逆な貴族の首を自分の手で刎ねたい、そうではないか?いずれお前の妹を辱めた連中に復讐できるなどと期待していないと言えるか?」
「…それは…」
言いよどんだジルキオを一瞥した“狼”の目はひどく寒々しい色をしていた。彼は背を向け赤々と高温で燃える炉に近づくと、焼き鏝と一緒に火にくべられた剣を引き抜いた。その拍子に黒い鉄の格子に刃が擦れ、ちりちりと火花がこぼれ落ちる。煤で黒光りする刀身は明るく赤熱こそしてはいなかったが、それでも暗がりの中でぼんやりと輝き、陽炎を生むほどにはきつく熱されていた。
「私怨を捨てよ、さもなくば…死ね」
平坦にそう告げると“狼”は一切の前動作なく踏み込み熱を孕んだ剣を叩き込んだ。咄嗟に剣を水平に構えて受け止める。だが疲れきった腕は容赦なく押し込まれる力に徐々に下がり圧倒される。耐え切れず片膝をついたジルキオに覆いかぶさるように“狼”は何のためらいもなく焼けた剣を押し付ける。ついに抵抗も虚しく、“狼”の刃がジルキオの肩に食い込んだ。
激しい動揺が一瞬息を締め上げた。次に耳をつんざくひび割れた悲鳴が迸り、まるで自分の声でないかのように響き渡った。肉を割り裂き血を焼く感触が思考を真っ白にする。剣を取り落とし、死に物狂いで腕を伸ばして“狼”の手を掴み抗う。死の恐怖をこれほどまでに身近に感じたことはなかった。
「がっ、ぁ、やめ…てっ…!ひぐっ…!い、や、しにたく、ない……!」
恐怖に歪んで咽び泣く。年相応の子供じみた命乞いが漏れた。
「耐えられぬなら死んだほうが幸いだ。死を恐れて改革など成せるものか」
無慈悲にそう言い放つ“狼”の手つきには一切の手心もなかった。何よりもその言葉が、彼にとって利己的な臆病者は虫ほどの価値もないのだと物語っていた。
そうと理解した瞬間、怯えた啜り泣きが出し抜けに凶暴な絶叫にかわった。そしてジルキオの表情は突然、ぱっと火が付いたように生存本能と怒りに燃え上がった。理不尽な死に直面したことで彼は奮起し、そして怒り狂った。自分の死を認めるわけにはいかない。そんな憤怒が噴き出したかのように見えた。
「…なにが!わかる!!!!何がわかるって言うんだ!」
ジルキオは残った力を振り絞り、剣が食い込み焼け爛れた傷から鮮血が噴き出すのも構わずに、掴んだ“狼”の腕にむしゃぶりついて血が出るほどに噛み付いた。その反撃は“狼”も予想していなかったのだろう。がむしゃらな突進に足元をすくわれ、二人は取っくみあいながら冷たい石の床に倒れ込んだ。“狼”は素早く平静さを取り戻し、馬乗りになって掴みかかるジルキオを得意の体術で投げ飛ばした。
「笑わせるな!自分が一番不幸だとでも言いたいのか…!」
“狼”は危うげもなく身を起こして鋭く叱責する。ジルキオは派手な音を立てて部屋の隅の机に激突し、椅子やランプを巻き込んで床にしたたかに打ち付けられた。だが堪えたふうもなく、まるで痛みを感じていないかのように機敏に跳ね起きると興奮した猛獣のように荒い息をつきながら低く唸り、ぎらぎらと底光りする青い目で“狼”を睨みつけた。
「そうだ…殺してやりたい!それが悪いか!あいつらも、皇帝も!全員首を刎ねてやる!!」
砕けた声音で吠える青年の癖の強い黒髪が無残に乱れて、殺意をむき出しにした顔を暗く縁る。
そして炉の炎に照らされて、赤紫に燃え上がる瞳に覗く純粋な暴威。
自身の保身すらも眼中にない、ただ相手を打ち倒すことのみを燃すその意志に正対し、“狼”は不意に背筋にかすかな寒気を覚えた。
四肢の血管が長虫となってのたうつような怖気は、“狼”の古い記憶を揺さぶった。
彼に、かつて帝都の墓地で見た大きな黒い犬を思い出させたのだ。
その犬は先帝の葬儀の日にどこからともなく現れて葬列に付き従い、これから訪れることになる現皇帝統治の苦難と荒廃を予見するかのように不気味な遠吠えを上げていた。
若き日の“狼”は犬のあまりに不吉な様子に葬列のそばから追い払おうとしたが、その犬は怖がる様子もなく、まるでにたりと笑うように“狼”に向けてはっきりと牙を見せ、それから喪に服する群衆の中に悠々と紛れて姿を消してしまった。それはもう随分と遠い昔のことであったが、なぜかくっきりと脳裏に焼き付き、忘れることのできない記憶となっていた。
あの日の黒犬が帰ってきたのだ、と“狼”は唐突に畏れに似た思いを眼前の青年に抱いた。
死の匂いを嗅ぎつけ、皇帝の葬列に再びあの嘲笑を捧げるために黒犬が舞い戻ったのだ、という根拠のない確信に襲われ愕然とした。
今は見境なく憤り吼えたてるばかりだが、もし彼に大義の首輪をつけることが出来たなら。そう考えて“狼”は昂ぶりを自覚する。野放しにすればこの青年は野犬のように見境なく周囲の者を噛み殺し、やがて自滅するだろう。
だがもし彼がこの純粋さと熱量、義憤と苛烈さを大義に捧げることを学べば、どれほどの戦果を挙げるだろうか。あるいは狼が率いる群れを継ぐことすらできるかもしれない。
“狼”はおもむろに落ちた剣を拾い上げ、傷を庇いながらも警戒心を隠さず刺々しく睨めつけてくる青年と向かい合う。力尽きれば殺されるとでも思っているかのように後退るジルキオに歩み寄り、手に持った剣の柄を差し出した。
「…わかった。チャンスをやろう。お前の妹の仇をとる機会を」
虚を突かれて言葉を失う青年に、“狼”は表情の薄い顔を近づけて、重々しい声で唸った。
「憎い者たちを皆殺しにしろ。そうして生きて帰って、お前が何を得たのかを示せ。復讐から何を得ることができたのかを」
有無を言わせず差し出した剣を握らせ、それからジルキオの傷つき血に濡れた肩を掴み爪を立てた。短いうめき声を漏らして歯を食い縛る彼にその痛みを刻み付けるように、きつく力を込める。擦り傷だらけの顔を歪めて、ジルキオはくぐもった声で吐き捨てた。
「殺さないのですか、俺を。従わぬ者は必要ないと言ったのは貴方だ」
「処分するかどうかは、お前の答え次第だ、“黒犬”よ」
「……!」
“狼”の言葉にジルキオは思わず顔を上げた。“狼”は自分の部下に決まって名を授ける。人間以外の生き物の名を。この扱いを受ける者は実力を認められた相手だけであることはジルキオもよく知っていた。
「事が済んだ後、お前がどんな答えを持ち帰るか。それがお前の命運を分けるだろう。それまで“黒犬”の名は預かっておく」
「では…!」
「焦るな。まだお前を認めたわけではない。焦らずとも直に機会をくれてやる」
自身の血で汚れた剣を両手で握ったまま立ち尽くす青年に“狼”は無愛想に言い捨てた。
「それまでに、傷を治しておけ」
――――――――――――
(続くよ!たぶんね)
(設定解説:“狼”はもと帝国軍人だったが先帝統治の世に膿み下野を決意。反帝革命派に合流してからは自身の戦闘技術を元手に、有望な若者を来る皇帝派制圧に備えて鍛え上げていた。歳は当時ですでに四十代半ばだったとみられる。彼が育てた戦闘員たちが諜報破壊工作のノウハウを組み立てて継承し、現在の特務隊の前身となる部隊を作った。という勝手な設定。ジルキオが27歳の時に“狼”が病に倒れたことで隊長の任を引き継いだ。)
フォロワさんでRPG詰め所


 *REVOLVER
*REVOLVER