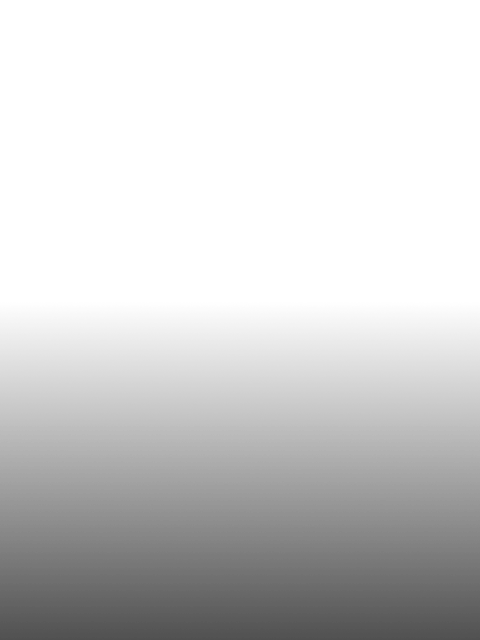闘技場脱出編・中編
強い雨が降っている。先ほどの突き抜けるような青空が嘘のようだ。
翳る空は薄暗く、かつて乱気流の如く闘技場に吹き荒れていた熱気は勢いを強めてきた雨に冷まされ、生ぬるく不快な空気に変えられていた。かつて生気に満ちた剣奴たちの戦っていた地面に散らばっているのは切り裂かれ、潰され、叩きのめされた死体、死体、死体だ。雨と泥と血肉が混じり、もはや戦場の跡の如き様相を呈している。先ほど腹を踏み潰された兵士が胃袋の中の物をまき散らして死んでからというもの、普段の会場にはない重苦しい静けさが一帯を包んでいる。観戦者たちはまさかあれほどの人数が全滅させられるとは予想だにしていなかった。もはや辛うじて生き残った数人がゆらゆらとヴラドを取り囲むだけになっている。
「強い闘士が圧倒的な大人数に槍玉にあげられ敢闘するが見るも無残に殺される様」を期待していた観衆は、いつしか皆野次を飛ばす者も無く固唾を呑んで戦いの行く末を見守っていた。一方、真ん中で片膝をついているヴラド自身にももう生気も最初に放った溢れだすような怒気もない。肩で荒い息をする彼の身体は余す事なくどす黒く血に汚れていた。さっきから何故だか、首輪がひどく熱いような気がする。首輪を中心にして、言いようのない「熱」が体に帯び始めていた。何かがおかしい。が、今気にかけている余裕はない。
「うぅ、おおおっ!」
闘士の一人がついに沈黙を破り、泥を撥ねながらヴラドに向かって突進した。「チビ矛」のサムソン、一攫千金と成り上がりを夢見て外からやってきて試合に出た男。しみったれた傭兵稼業から足を洗おう。少し前に孕ませた酒場の女を買い上げて、その子供と3人で農場でも拓こう。そんな気持ちでここへ来た。立ち寄った街の酒場で募集を知った時はなんとも趣味の悪い試合だと思ったが、手傷を負わせるだけでも分け前は出ると聞き、その分け前だけでも自分の2年分の稼ぎはあると知って色めき立った。そして今彼が感じているのは、その時の選択が今まで渡り歩いた戦場でしくじって死にかけたどんなくそったれな場面よりも最悪にバカなものだということだ。伊達に戦場を生き延びてはいない。時々見かけるんだ、「こういう化け物」を。あの時は近づきさえしなければ生き残ることが出来たが、今回はそうはいかない。哀れなサムソン、お前もここまでか?ああ、死にたくない!
未だ動かない「悪魔」に向かって無我夢中で槍を突き込む。相手はそれを躱そうともせずに、うつむいたまま左の掌をすうっとこちらに向け、そのままどすん、と躊躇なく受け止めた。そのままゆっくりと立ち上がり、こちらへにじり寄る。掌を貫いた槍はその身を血で汚しながらずりずりと掌を貫き通してゆく。サムソンはすでに身動きもできず立ち尽くすのみであった。
「ふぐ…うぐ、ひぐっ」
足元から湯気が立ち上る。涙があふれる。ここで死ぬのか。いやだ、怖い!目の前に迫った悪魔は兜の下からもう片方の手を差し込んで、首を掴んだ。そしてギリギリと締め上げてくる。息が出来ず、泥まみれでもたつく重い足をばたつかせるが、すぐに自分の首の骨の軋む音が聞こえてきて意識が遠のく。苦しみに満ちた少しの間をおいて、ボキリという乾いた音を最後に、彼の生は終わった。
――小柄な死体を地面に捨てて、ヴラドは空を見上げる。顔についた血が少し洗い流された。いつの間にか、敵もあと少しだ。まだ自分も五体満足に生きている。ヴラドは大きく深呼吸をした。やることは変わらない。そろそろ終わらせろ。
おもむろに左手を貫いた槍を右手で掴み、そのそばを膝で叩き折ってから一気に引き抜いた。折れた槍をそれぞれ両手に構え、そして倒れこむように残った敵に向かって突進する。
間もなく、試合の終わりが来た。ヴラドは一人その場に立っている。彼の周りはまさしく血の海が広がっていた。規模としては世紀の大試合になっているはずだが、歓声を上げる者はない。異様すぎる光景だった。みな呆然と眼下に広がる血の池に立つ青年を眺めている。彼は一人で、百人を超そうという相手を皆殺しにしたのだった。
ヴラドは歩き出した。本来退場すべき流血路とは逆の出入り口へ。そう、自分の雇い主のもとへ。まだ彼の相手は残っている。
天幕が張られている貴賓席で、ラガルトはそれを悠然と見下ろしている。
何か考えを巡らせているようだ。
「いや、もしかすると名乗り出る者がいるかもな…おい、用意しろ」
そばで控えていた侍女たちの一人が裏口へと消えていき、もう一人がラガルトの足元でまた「拡声の呪文」をつぶやいた。落ち着き払った、とどろく声。
「御集りの皆様!とんでもない結末になってしまいました!私を含め誰がかような結末を予測しましたでしょうか!いえ私も、このような結末は望んではいなかったし、思ってもみなかった!オオカミは悪魔となった!今ここに!邪悪なる悪鬼が誕生したのです!皆さま!新しい伝説に盛大な拍手と喝采を!」
始めはまばらだった拍手も、徐々に大きくなってくる。その喝采はヴラドをたたえるものではなく、この混乱に収拾がつけられないどよめきと言いしれない興奮に代えられているにすぎなかった。ヴラドはラガルトに一番近い塀の前まで歩み寄り、じっと一点を見つめている。そして、腰を落とし、何かを構えるような素振りをみせた瞬間、何かを投げた。それと同時に、ラガルトは足元にいる侍女をすばやく抱き寄せた。侍女の背中に突き立ったのは血まみれの剣。貴賓席から悲鳴が巻き起こる。ラガルトは顎をくいとあげて、じっと眼下の奴隷を見下ろしていた。
あとがき:
ここでアイデアが腐ってきたので、後編としてまた後で書きます。むずい
フォロワさんでRPG詰め所


 *REVOLVER
*REVOLVER