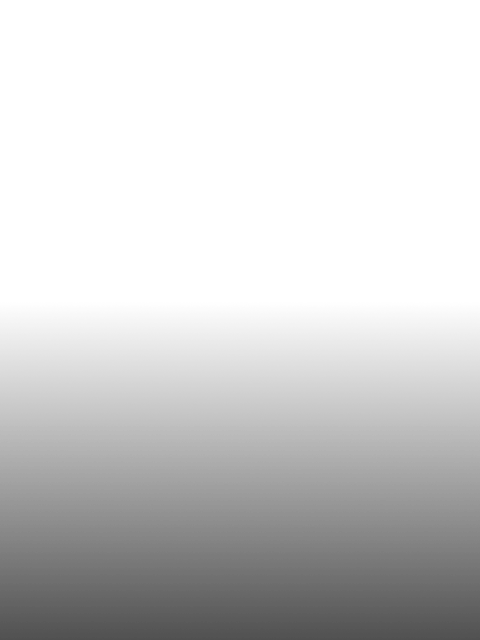利用条件
- チャンネルの購読はのに限られます
- チャンネルの購読はに限られます
- チャンネルの購読はに限られます
- チャンネルの購読はに限られます
- チャンネルの閲覧にはフォロワさんでRPG詰め所へのアカウント登録/ログインが必要です
注意事項
- 購読ライセンスの期限を超えると、チャンネルを閲覧できません。購読ライセンスを新たにご購入ください
- 一度ご購入された購読ライセンスの返金はできません
これまでのご利用、誠にありがとうございました。
ツイッターでは書ききれないのでこっちでw ---------------------------------------------------------------------------------------- 暗い部屋だ。 そう広くはない。 暗くて良くは見えないがわずかに明かりに照らされた部分から品のよい装飾が覗く。 おそらくは宮殿か何かの一室なのだろう。 その中央には玉座・・とは思えないが一段高い段がありそこには何人もの人間がいるようだ。 そしてその段と正対するように一人の小男が床に座らされている。 小男は叫ぶ。 男「おのれ!貴様自分が何をしているのかわかっているのか!」 壇上に座る男を見据え小太りの男が吼える。 顔にあざが出来ているあたりは拷問のあとなのだろう。 みれば薄汚れてはいるが着ている服もずいぶんと質のいい物だ。 どこかの貴族かなにかだったのだろう。 小男の見る先・・・叫んだ相手は・・・ オールバックの髪・・・幾分白いものが多く混じっているようだが。 そして鋭い視線を小男に向けている。 壇上の男は冷ややかな視線で見下ろしながら言った。 「もちろんだ。私は私の行いは熟知している。軽率な行動に走る伯とは違うのだ」 壇上に座る男が見下す小太りの男・・伯というからには貴族だろうが、後ろ手に縛られ 床に座らされている。 それでもなお、伯は吼える。 伯「軽率な行動だと!私の行動が!?許されると思っているのか!貴様の行いが!」 壇上の男は言う。 「ずいぶんと元気がいいな。どうやら審問官の働きが悪かったようだ。この件に ついては後でしかるべき対処を行おう」 伯「はぐらかすな!答えろ!マシュー公!」 マシュー公と呼ばれた壇上の男・・・玉座・・ではない。 だが整えられた椅子はそれなりの地位がある者が座る椅子なのだろう。 表情一つ変えずマシューは言い放つ。 マシュー「さて、伯の質問に答えねばならんな。私の行動が許されるかと言う点だが、 それはギベール伯の判断するところではない」 今にも噛み付かんかの勢いで叫ぶギベール。 ギベール「ならば誰が答える!貴様か!己が世界の頂点だとでも言うつもりか! 神を気取るか!マシュー!」 マシュー「私にそんな権限などない。後の歴史が判断してくれよう」 ギベール「はっ!某弱無人に加え責任まで投げ出すつもりか!外道め!」 以外・・・と言わんばかりに少し眉根を寄せつつマシューは答えた。 マシュー「何を言っている?私は私の行いは熟知しているといったはずだ。功も責も すべて私にある。責が勝ればいずれ裁かれよう。それもまた私の責務なのだ。 短慮に臣民を惑わす伯と同じにしてもらっては困る」 ギベール「奴隷制度に圧政!許される事だと思っているのか!人は平等なのだ! だからこそ私は・・・・」 マシュー「人は平等ではない。生まれつき足の速い者、美しい者、親が貧しい者、 病弱な体を持つ者、生まれも育ちも才能も人間は皆、違っておるのだ。 だが、私は平等に扱っている」 ギベール「どの口がそんな戯言を・・・・!」 マシュー「そうかね?帝国においては奴隷は”存在しない”のだ。彼らは”三等”市民だ。 等しく我らが帝国の民だ。 そして、彼らを奴隷扱いし、一人特権を蝕んでいたもの達。彼らにもしかるべき 責務を与えた。 皆、平等に扱っている」 ギベール「三等市民なぞ建前にすぎん!しかもその行動こそが圧政だろうが!」 マシュー「では伯は皆責務を放棄して無責任に生きろというのかね?伯のように。 権利を得るには義務を履行せねばならない。 伯という地位にありながらに騒乱を起こし、テロリスト共に便宜を図る。 これは無責任・短慮とは言わないのかね?」 ギベール「・・・・っくっ!」 冷ややかな目で断罪の言葉を言い渡すマシュー。 マシュー「あげくに臣民に余計な負担と不安の種をまいた。伯の起こした行動が。だ。 この罪は決して軽くはない」 ギベール「私を殺そうというのか。いいだろう!その行動こそが貴様の独善と独裁の証と 民に知れよう!殺すがいい!」 マシュー「私を極悪人のように扱わないでくれたまえ。殺すわけがないだろう。私が。伯を」 ギベール「・・・・・・・・」 マシュー「さっきから聞いていればよくそんな下品な口が回る。 帝国に下品な男は必要ない。帝国に粗忽な貴族はいない。 高貴なるギベール家の伯爵はかの邪悪なエルフ共の姦計に載せられた配下の 失敗の責を自ら背負い、償いのため身を挺した。違うか?」 ギベールの頬に冷たい汗がつたう。 ギベール「・・・・どうするつもりだ・・・・」 マシュー「城のはずれに小さな廃屋があるのを伯はご存知かな?あそこには世を儚んだ者が 夜な夜な迷い出るらしい。どうだ?ゆっくりとかの者と語らってみては。 迷える魂を慰めてやればいい。なぁに”博愛精神にあふれる”伯の事だ。 きっと気に入られよう」 ギベール「!!!」 冷ややかに傍に傅く配下に宣告するマシュー。 マシュー「嘆きの館に幽閉しろ。ギベールの一族もすべて処罰だ。・・・そうだな。斬首に処せ。 首も放り込んでやればギベールとて寂しくなかろう」 配下「はっ。では・・・」 指示を受け行動に出ようとする配下に声をかけるマシュー。 マシュー「まて。この件についてはしろっこに処理させろ」 このマシューの意外な一言に思わず配下は問い返した。 配下「え?しかし、この程度の事、わざわざシロッコ卿のお手を煩わせる事では・・・」 すでに興味を失ったのか次の受刑者の書類に目を通しながら言うマシュー。 マシュー「かまわん。甘い事をしていればどうなるか。卿にもよい教材となるだろう」 さすがにここまで言われると唖然とするしかない。 何せ自分の腹心まで巻き込もうというのだ。 配下「は、はぁ・・・・・」 納得は行かない・・いや、なにがどうなっているのかと狐につままれたような顔で言う配下。 マシュー「引っ立てろ」 引き立てられていくギベール。 そこに声をかけるもう一人の配下がいた。 「閣下。それではギベール家は取り潰しですか」 マシュー「そうだな。ジルキオ。・・・・・いや、まて」 ジルキオ「は?」 マシュー「確かギベールには妻子がいたな」 手元の資料を確認しつつ言うジルキオ。 ジルキオ「え?あ、はい。確かに調書にはそのようになっております」 マシュー「かの者たちは斬首にするな」 ジルキオ「はぁ?」 これにはジルキオも目を白黒させざるを得ない。一体急に何の冗談だ?マシューが急にこんな 仏心を出すわけがない。 マシュー「無論裁かないわけではない。帝国を永久追放だ」 一体これは・・・考えをめぐらすジルキオ。 ジルキオ「!・・・なるほど!嘆きの館で妻子だけが首がなかったら・・・奴めにはこれほどの痛手は ないでしょう!さすが陛下!しかしそうなりますとジルキオ家は取り潰しとなりますな。 ジルキオ家の資産もついでに国庫に没収というわけですね」 マシューの差配に感嘆の念を隠せない。 マシュー「いや。取りつぶしにはしない」 さすがにこの発言だ。配下だけでなくジルキオも目を白黒させる。 ジルキオ「か、閣下?一体何をお考えで・・・・?」 マシュー「この間つれてきた少年がいたろう?」 ジルキオ「ええ、まぁ。しかしそれとこれがどのような・・・・?」 さすがにこの問答に少し辟易したのか、ジルキオを見て答えるマシュー。 マシュー「あの少年を頭首に据えろ。まぁあの年でさすがに辺境伯もなかろうが。後見人を付けさせればいい」 ジルキオ「あの者をですか?正気ですか?閣下?」 マシュー「歳の割に出来た少年だ。育てれば有用な人材となる」 ジルキオ「しかし・・・あの少年は奴隷・・いえ、三等市民ですよ?たまたま陛下が町に出られた際、偶然話された だけではありませんか」 マシュー「なんだ?ジルキオの方では不満か?ならば私が後見人になろうか」 この仰天発言に思わず否定にかかるジルキオ ジルキオ「い、いえ!こちらの手の者で手配いたします!しかし!何度も申しますがあの少年は・・・!」 さすがに据えかねたのだろう。マシューのジルキオを見る目が鋭くなる マシュー「だからなんだというのだ?才がある者を登用する。才に身分なぞ関係あるまい。それだけの事だ。何か不満があるのか?」 この剣呑な雰囲気にさすがのジルキオも折れざるを得なかった ジルキオ「わ、わかりました・・・こちらで手配いたします・・・」 マシュー「すまんな。君には面倒をかけるがよろしく頼む」 ジルキオ「御意・・・・」 マシュー「さて、書類を見てみたが、14番目からは明日の審議で良かろう。それまではジルキオ。貴卿に任せるとする。かまわんか?」 ジルキオ「はい」 マシュー「申し訳ないが今日は先に上がらせてもらおう」 そういうとマシューは席を立った ---------------------------------------------------------------------------------------- 私室・・・なのだろうか。 それなりの大きさの部屋だ。 おそらく一般市民であれば家1軒分はゆうにある。 整えられた部屋で敷かれたじゅうたんや柱の装飾がそれなりの地位にある物が住まう場所である事を物語る。 部屋には品のよい品が並ぶが決して華美ではない。 むしろこの部屋の質感、規模に際して言えば相当に質素に写る。 「・・・・ふぅ・・・・」 疲労困憊とばかりにため息をつくマシュー。 近くのソファーに座り込んだ。 そんなマシューに声をかけるものがあった。 「お疲れ様でした。公爵様。今お食事を運ばせます」 みれば若い女性だが出で立ちからして侍従(メイド)なのだろうか。 マシュー「いや、いい。査問の後、ビヤ樽(ドワーフ)共と話をするハメになってな。おかげで腹いっぱいだ」 そんなマシューに声をかけるメイドがまだいた。 いや、メイドというには随分とたくまし過ぎるが・・・ 「ククク・・・・夜の食事は健康の要!食を抜こうとは何たる不届きご主人よ!だが心配するなご主人! この俺がいる限りいつも主人の健康に全力奉仕!それがこの俺メイドガ・・・」 マシュー「お前は呼んでいない。コガラシ」 そういうとポケットから小さな笛のようなものを出して吹くマシュー。 音は聞こえない。犬笛のようなものであろうか・・・ コガラシ「ヌファァーーッ!」 ズドン! まるで猛獣が倒れるような音がする。 思わず目頭を押さえながら言うマシュー マシュー「連れて行け。君達も今日はもう下がっていい」 メイド「は・・・はい・・・・・・」 マシューは思う (いいかげんこの男も面倒になってきたな。さっさとジルキオに引き渡すべきかもしれんな・・・・) 人気のなくなった部屋でソファーに座っていたマシューはふと立ち上がる カラン・・・ 乾いた音がして何かが運ばれてくる。 グラスだ。 おや?それにしては・・・ マシューが運んできたのは質のいい・・とはとても言えない酒だ。おそらく貴族が呑むような酒ではない。 そしてグラスが2つ・・・ マシュー「久しぶりだな・・・この酒を開けるのも」 トクトクトク・・・ グラスに酒を注ぐ。 トクトク・・・ そしてなぜかもう一つのグラスにも。 マシュー「そういえばこの酒を飲んでふらふらになってはよく君に怒られていたな・・・・」 ゆっくりと口を付けるように少し酒を口に運ぶマシュー。 もう一つのグラスに目をやりながら言うマシュー。 マシュー「ふふ・・・あの頃は私が衛兵上がりの頃だったかな。よく君は言っていたな・・・ ”そんなに呑むから膝に矢を受けて衛兵なんかになる羽目になったんです!”って・・・・」 珍しいのだろうか・・あのマシューが微笑んでいる・・・ いや・・・どこか寂しげな・・・何かを懐かしむような、寂しがるようなそんな笑みを・・・ マシュー「よく仕えてくれたよなぁ・・・あの後色々あったな。結局私が国の中枢入り込むようになって・・・ それでも君は影から支えてくれた。周りにいう事はさすがに出来なかったがね・・・・」 「覚えているよ。あの女を連れてきたときの君の表情は・・・いや、今更だがな・・・ 申し訳ないと思っている。 所詮政(まつりごと)のためだけの女でもそんなの目の当たりにしちゃいい気はしないよなぁ・・・」 「でもさすがに君だ。すぐに悟ってくれたね。感謝しているよ。あの女か?さぁな・・・もう今となっては 何の用もないんでね。どんな女かも忘れたよ。もっとも書面では戦(いくさ)を避けて別宅に避難中 となっているが。 まぁ城の地下のダンジョンの土の中も避難中には変わるまい・・・・」 ふっ・・・そんな笑みがマシューに浮かぶ。 「どうしてだろうな。なぜか急に君の事を思い出してね。ある査問の最中に自分でも変だとは思うが思わず 仏心を出してしまった」 そしてきまりが悪そうに笑いながらつぶやくマシュー 「まぁ、君の逆鱗に触れたか、天罰なんだろうね。おかげでそのあと散々ビヤ樽共に付き合わされるハメに なってしまった。だが、それだけの価値はあったぞ」 グラスを両手で持って祈るように言うマシュー。 「もう少しだ。もう少しで敵が討てる。君の命を奪った憎きクソ虫共。あのエルフ共をこの世から駆逐できそうだ」 「だがもう少しだけまっちゃくれないか・・・君の敵は必ず討つ。たとえ私が滅ぶ事になってもね」 「もっともコレだけの事をしてるんだ、天国の君には会えそうにないが・・はは・・・私の行くのは地獄だろうからね」 「だが約束する・・・いや、約束を果たしてみせる。私自身に誓った約束だが、君の敵は必ず討とう。必ず・・・・」 帝国の夜は深けて行く・・・
長くなったので前後分けます。後編はまとまり次第投げに来ます。 「だから、何度も言わせんなよ、その気はないって言ってるだろ」 もう何度目だ、こうやって花街で袖を引かれるのは。それも一夜の誘いではない。こんな痩せっぽっちな子供が女を買うような金を持っているはずもない。店に並べというのだ。小奇麗に飾られた艶やかで淫らな女と同じぐらい高値のつく、色物の花にしようという心づもりで、こうして身寄りのない子供に声をかけているのだ。まだ無理やり攫ってしまわないだけ、随分良心的だと言えた。為政者は政治に関心を失い、この国はひどく傾いていた。そんな中、取締もろくに行き届かない花街で人道的な取引をもちかけてくるなど、店の歴史に自信があるか、懐に余裕がある商売上手といったところか。だがしかし、女を物のように売り買いする人間に対する少年の不信は大きかった。男を買おうという者の気もしれない。今日もこうして計算高い手を突っぱねて、目尻のきつい大きな蒼い目で女衒を睨む。その勝気で初心な表情は整った顔立ちを歳よりもやや幼く見せ、今から店に仕込んでも何年かは使い物になりそうだと思わせてしまうことを少年は知る由もない。だが美しい花は枯れるのも早いということを考えないほど、少年は愚かではなかった。ここでいくらか稼ぎが良くなっても、二十代も半ばの歳になれば売り物にならなくなる。そうすれば体を売るしか稼ぎ方を知らない者の末路など決まっている。惨めな凋落と破滅だ。そんな死に方をするなら、綺麗なまま野垂れ死んでやると、少年は不器用な高潔さを胸に、まだ引き止めようとする女衒を無理やり振り切る。揶揄の言葉と嘲笑を背に受けながらうつむき加減で唇を噛んで大股で裏通りを飛び出したところ、前を見ていなかったことも手伝って、脇道から出てきた男と派手にぶつかってしまった。たたらを踏んで、叩きつけそうになった悪態をすんでのところで飲み込んで見上げた人間はまだ歳若く、随分背の高い男であった。 「すみません」 下手に絡まれたくないという思いもあり早口に謝って脇をすり抜けようとすると、その青年が肩を軽く掴んで引き止めてくる。 「ねえ君さっき…」 「なんの用だよ…!」 また声をかけられる。一日で二度という事実は少年の事を荒立たせたくないという気持ちを吹き飛ばす。肩に置かれた手を乱暴に叩き落として振り返り、なにか罵ってやらなくては気が済まないと振り仰いだ青年の目を見て、少年は小さく息を飲んだ。 突然声を荒らげた子供に少し呆れ気味の驚きの表情を浮かべて面白がるように唇を緩ませたその青年の瞳の色は、否応なく血の色を連想させるほどの純粋な真紅。体の色素を持たない白子に赤い目が希に現れるというのは聞き知ってはいたが、本物の紅い瞳を目にするのは初めてであった。少年の凝視を感じ取ったのか、男は悪戯っぽく瞬くと長身をかがめた。 「この目が珍しいかい?」 軽薄で人懐っこそうな笑みが唇に張り付いていたが、細められた目に浮かぶのは妙に空々しい熱のない表情、あるいは空虚さ。その寒々しさに少年はたじろいだ。 「みんな大抵、初めはそういう反応をするね」 そう言ってどこか自虐的な調子でまるで人ごとのように言い捨てる投げやりさに気圧されたことが悔しく、少年は背筋を伸ばして男を真っ向から見上げた。そうしてみるとだらしなく気崩れてはいるものの身につけている物は仕立ての良さそうな上着や手触りの良さそうなシャツなど、明らかに貴族か、あるいはそれに準ずる裕福な上流市民出身であることを示していた。客引きでも女衒でもないなら、この町の客だ。肩にかかるほど伸ばされた明るく線の細い金髪と、目鼻立ち一つ一つは穏やかで柔和な作りだが少しばかり粗野な表情も相まって、まるで結婚詐欺師のようだなと少年は内心ひとりごちる。 「で、何の用だよ。俺は売りはやってない」 「買いに来たってのはわかるんだねぇ」 「あんたみたいなのがこの街ですることって言ったらそれぐらいだろ、お貴族さん」 「喧嘩っ早いかと思ったら、存外に人を見る目もあるようだね」 えらいえらい、と馴れ馴れしく頭を撫でる手を少年に忌々しげに叩き落されて、青年は苦笑いを零した。 「だけど不正解。君みたいに小さい子に手を出すほど外道じゃあないよ。さっきの勧誘みたいなの、よくされるのかい」 どうやら見られていたらしい。不躾な質問に少年はぶすくれる。どうせ細くて白くて男らしくないとでも思われているのだろう。 「時々。でも全部断ってる」 つっけんどんに答えにも、青年の熱を映さない態度は変わらない。 「君みたいなのは高値がつくから、売る気がないならこんなところ、出て行った方がいいだろうね。何処の店もああいう紳士的なやり方とは限らないから」 「今のこの国じゃどこに行ったってろくな仕事なんてないよ。特にこんな痩せたガキができることなんか何もない。こうやって人が沢山いるところのほうがまだマシだ」 言い募るうちに妙に腹立たしい気持ちになってくる。腹が空けば気が立つが、それ以上に成長期だというのに栄養が足りないせいか背が伸び悩んでいる自分と、目の前の男の惚れ惚れするほど恵まれた体格を比べて、いったいこの男と自分の境遇を分けたのはなんだったのかという実のない疑問に苛立ちが湧き起こる。 「悪いけど、あんたの同情じゃ腹は膨れないんだよ。あんたはこうやって名前も知らないガキに同情おしつけてりゃ満足かもしれないけどな、まだ金のほうがありがたいよ」 特に急ぐ用もないせいもあって、強く話を遮ってこの場を立ち去る理由が見つからなかったせいか、言うつもりのないことまで口をつく。せめて仕事があれば良かったが、それさえも心もとないというのに、この遊び呆けていることを許された身分の青年と同じようにここに立ち止まって時間を無為にしている。青年はそんな複雑な心境を知ってか知らずか、おもむろに上着のポケットに手を突っ込むと、一枚の硬貨を引っ張り出して、二人のそばに積まれた木箱の上に静かに置いた。その色に少年は思わず目を奪われる。 金貨だった。 少年がそれなりに安定した幸せな家庭で暮らしていた頃でさえ、そうそうお目にかかれるものでなはい、最も重い金貨だった。 「じゃあ名前を聞いても?」 金のことには触れず、青年はそう聞いた。道を尋ねるような気軽さだった。それに少年は無理矢理視線を金貨から引き剥がし、剣呑な目で睨めつけた。 「断る。教える義理がない。それにこんなもんいらない」 「そっか」 それだけ呟いたが、青年は金貨を引っ込めることはぜず、相変わらず冷めた目で飢えた野良犬のような少年を見下ろしていた。青年が何かを思いついたように口を開きかけたとき、表通りから女の声が掛かる。 「ねえ、ジィーベン、何をしてるの?」 その婀娜っぽいふしだらな声に少年は盛大に顔を顰めた。あからさまな表情に思わずといったふうに青年は苦笑して、女の声にすぐに戻ると返してから、身をかがめて少年に抑えた声で囁く。 「貴族街外れの3番地、若いのを探してる偏屈がいる。身売りは無しだけど、多分他のどんな仕事よりもずっと厳しい。だけど君みたいな子が、相応しいかもしれないね」 青年はそれだけ一方的に伝えると、ふたたび少年のくしゃくしゃの黒髪を乱雑に撫でるとぽんと軽く叩いて、払いのけられるよりも早く身を引くと、ひらりと手を振って待たせている女のもとへと去っていく。 残されたのは煤けて色あせた木箱の上に、不似合いな金貨。鋳造からそう年の経っていないであろう、縁も刻まれた皇帝の横顔もくっきりとした黄金。それ一枚で、少年は食いつなげる、誰のものでもなくなって、今はただ石ころのように転がる贅沢。あの青年にとってはおそらく人肌で、少年にとっては暖炉で、この寒々しい夜を凌ぐことのできる金色の気まぐれ。 だがそれを手に取るのは、少年にとっては敗北に思われた。何に負けるわけでもない、ただ道端の石を拾うような事でも、決定的な敗北であるように感じられた。それから目をそらし、立ち去ろうとするが、足がひどく重かった。歯を食いしばり、脳裏に焼き付いた空虚な紅い瞳の残像を追い払い、少し裏路地を進む。振り返ると、まだそこにある。いずれ誰かが見つけて、信じてもいない神に幸運を感謝して、なんの葛藤もなく持ち去るのだろうか。そう考えると、こうして未練を感じる自分を棚に上げて腹立たしさを覚えた。ふと少年の胸に、預かっておくだけだ、という考えがよぎる。それも所詮言い訳に過ぎなかったが、次に会った時に落し物だと言って返せばいい。いや、叩きつければいい。同情なんて糞くらえだと、そう言って笑ってやろう。 くだらない意地だと自嘲する自分を感じながらも、それは随分名案に思われて、少年は足早に取って返すと金貨を素早くつかみ、誰にも見られないようシャツのポケットに押し込んだ。 ずっしりと重い感触が胸に伝わったが、その場を立ち去る足取りは幾分勇み足であった。 貴族街外れの3番地。少年は金貨一枚よりもずっと価値のある者を青年によって与えられたことを、まだ知らなかった。 《前編完》
しん…とした闇夜。全てが黒で染まる。 今宵は新月…カーエデール卿が唯一、普段とは異なる姿になれる日。 小さき獣となってこの世界を飛び回る、それもまた一興ではあるがやはり、たまには人の姿に興じるのもよい。やはり博士は吾輩の心をよくわかっている。 寝床から起き上がり、被験者用ベッドにおいてある白衣を羽織る。と、足元に大きな塊がみえた。 「んん…」 もぞりと動くそれは、どうやら人のようだった。 ここに人間がくることは実に珍しい。いや、皆無だ。自力でこの場に入ることは不可能なのだ。 「さては…連れて来たのか」 ぽつりと呟きながら、顎をしゃくり、ハア、と溜息を洩らす。元は自分とはいえ、あの子はあまり深く物事を考えていないように思える。とはいえ、以前は小動物の死体を運んでくることもあったが、それに比べればまだ研究のしがいもありそうだ。 (せめて手術台で眠ってくれればいいのだが…) 明りをともすと、足元で青年が丸まって眠りについている。みたところ、今は健康状態も良さそうだ。だが、ここに連れて来たということは何らかの問題があるのだろう。 持っているろうそくの明かりを顔のあたりにやると、ズキリと頭が痛んだ。 「この子は…」 吾輩が小さき獣の姿で外にいると、詳細には伝わらないが吾輩にとって重要になることだけは中にいる人格にも伝わる。彼の顔は何度も伝達されてきた。 ―――ヴラド。 それだけしか知らない。だが、それで十分だった。 獣が連れてきた唯一の生きた人間。よほど大切に想っているのだろう。 静かに寝息を立てる彼のマントをゆっくりとめくる。どうやら、片腕が無くなっているようだ。どのように止血したのか初見では解りかねるが最近のモノでもないらしい。 他にも切り傷は頬や肌の出ている箇所に数点見受けられるが、それほど問題もなさそうだった。 「腕か…」 布できつく縛られた箇所をナイフで切る。その瞬間、バッと翻され、開いている片方の手で掴みかかられた。そのまま床に押し付け、乗りかかる。一瞬の出来事だった。 「…誰だ、てめぇ…」 力強く握られ、ナイフを落としてしまう。カランと響く音を聞きながら、さらに床に背中を押しつけられる。 「少し力をゆるめてもらえないか。吾輩はただ、触診をしていただけだ」 「ショクシン…?てめぇ、あのハエの仲間か?」 鋭い眼光で睨みつけ、いまにも喰いかかってきそうな勢いに吾輩は少しだけ眉間に皺を寄せた。 「蠅とはまた…。わざわざ君を連れてきたあの子も悲しむのではないかね?」 「別に、大した問題でもねえよ。…ナイフなんざ出して、何のつもりだ」 「腕。布を取ろうとしたが、硬すぎてね」 少しばかり力が緩み、のしかかる重みが軽くなった。 「ああ。…治せんのか?」 覗きこむようにこちらを見る目は、先ほどの勢いはなくなっていた。獣は多分、この目に惹かれたのだろう。片方の目はウェーブがかった前髪で伺うことは出来なかった。 「さて、さすがにそのままではわからない。…済まないが一旦降りてくれないか?君がこのままのほうが良ければ無理はいわない」 「!…わぁったよ。」 飛び起きるように吾輩の上から起き上がり、「こちらへ」と促すと意外にも素直に手術台へ座った。 右腕に乱暴にまかれた布をナイフで切り、ゆっくりと解く。最近ではないとはいえ、まだ痛みは強くあるようで傷口に布が触れると顔をゆがませるのが見えた。 「まだ、痛むのだね…仕方あるまい。どうやらこれは…あの子が一時的に切り口を?」 「…おう、印でなんとかしてるっつー話は聞いた。で、…なんとかなんのか?」 痛みに耐えながら発する声は、あまりにも辛そうで。早く処置をせねばと思いながらも切り口がまだ断面の見える状態に心臓が脈打った。 (これは…いい実験台になりそうだ…博士に見せてあげたい) 吾輩の心の奥で浮かぶ言葉を抑え、傷口に触れる。 「あぐっ…ッツ…!!!!!」 「少し痛むかもしれないが…、一度縫合の為に印を切る」 その言葉にびくりとしたヴラドは一瞬制止しようとしたが、思いとどまったようだった。 「わかった」 「いい子だ。腕はまだこの場にはない。だが、このまま放置するわけにもいかないだろう。吾輩としては…今のうちに全て済ましてしまいたいところだが…、一時的に縫合しておこうと思う。印だけではどうしても腐食まではおさえられないからな」 苦痛にゆがみながら、頷く彼の表情に脳内が沸きあがるように興奮していた。 (いけないよ、カーエデール卿。彼の回復を祈っているのだろう。今はまだその時ではない) 言い聞かせるように頭の中で呟く。冷静を取り戻し、目の前の“患者”に目を落とした。 『新月の間に出来ることは限られる。処置は完了したが彼の腕を取り戻すのは、まだ不可能だ。』 吾輩は、それだけ紙片に書き残し、傍らで眠るヴラドの顔を見つめた。 このまま普通の義手をはめるにはもったいない。なるほど、あの子が目を付けたのもよくわかる。 目を細め、満足げに科学班に連絡事項をしたため、カーエデール卿はゆっくりと彼の額を撫でた。 「また次の新月で会おう。その日まで…」 ボソリと呟き、ヴラドの額に唇を落とした。
【名前】本名はヴラディスラウス・ドラクリヤ(本人は知らない)。略してヴラド。 【性別】男 【年齢】20代前半 【種族】人間 【所属・役職】海賊 【性格等設定】 ほぼ白に近い銀色の髪をもち、その半分は刈り上げてある。腰には古いが手入れの行き届いたククリナイフを二本提げている。全身に彫られた刺青と黒い首輪が特徴的。 帝国に滅ぼされた辺境の国の遺児で、独自の文化を築き上げていた故郷は、黒魔術や死霊術、食人など一般的に忌み嫌われる事を是とする神を信仰していた。本人はそれを知る由もない。 物心ついた時にはすでに故郷は帝国に焼き払われ、彼は出自不明の安い売り物だった。闘技場の余興で子供が殺されるだけの見世物同然の試合に駆り出されてしまうが、命からがら勝利し、才能を見込んだ奴隷商のもとで剣闘士として死線を潜り抜けてゆく。 名をあげ始めた18歳の頃、突然現れた眼帯をした青年に大金で強引に買い上げられ、その日のうちに魔術で縛り上げられたすえ全身に謎の黒い刺青を彫られてしまう。そして数日後の傷の癒えはじめた朝、その青年はいくばくかの路銀を残し彼の前から姿をくらましてしまう。 それ以後は鉄砲玉や殺し屋を転々としながら食いつなぐ日々が続くが、盗みに入ったとある海賊船の船長に見つかってしまう。しかしそこでなぜか海賊の一味として勧誘され、さらにその船長が自分に刺青を彫った青年まで知っているという言葉を聞き、勧誘を受け入れる。最初こそ残忍な盗賊が来たと船員たちは嫌悪の視線を送っていたが、彼の持つ卓越した戦闘能力と気取らない、威張らない飄々とした態度に知らず知らず船員たちの人望が集まり、結果的に船長の右腕として信頼され始めている。好奇心も強く、最近は船長に普通の人間の暮らしや作法を教わりはじめている。 気分屋で、たまに口を開けばボヤくか茶化す彼だがその生い立ちは凄絶である。少年時代は同じような境遇の奴隷仲間達との友情や息もつかせぬ戦いの日々が彼を壊さずにいたが、やはりどこか感情が欠落している部分があり、善悪に頓着がなく無辜の他人の命を奪うことにもためらいがない。