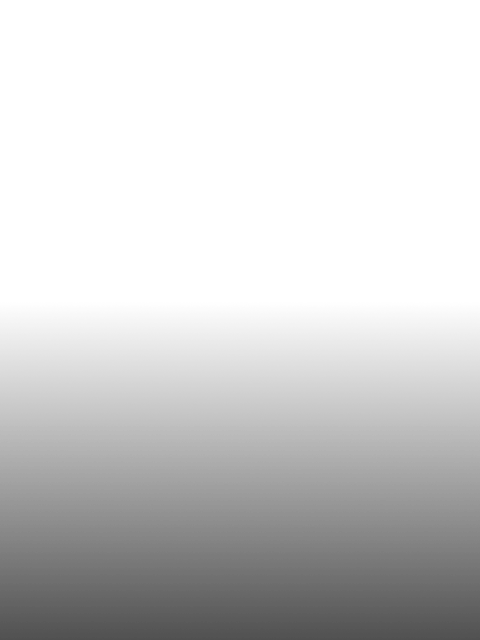利用条件
- チャンネルの購読はのに限られます
- チャンネルの購読はに限られます
- チャンネルの購読はに限られます
- チャンネルの購読はに限られます
- チャンネルの閲覧にはフォロワさんでRPG詰め所へのアカウント登録/ログインが必要です
注意事項
- 購読ライセンスの期限を超えると、チャンネルを閲覧できません。購読ライセンスを新たにご購入ください
- 一度ご購入された購読ライセンスの返金はできません
これまでのご利用、誠にありがとうございました。
くらいくらい黒の空に浮かぶひとつの光。日毎に丸くなってはしぼむ不思議なひかり。小さなけものはその光が大好きでした。暗闇でしかしっかりと見られない、そんな不思議なひかり…そのひかりを浴びるだけで心が満たされるのでした。 「卿、あれは月と言うのである」 ぼんやりと眺めていると後ろから聞こえる声。小さなけもののカーエデール卿を作ったツバキ博士の声でした。博士の声はいつも優しく自信に満ちているように思えます。彼はそんな博士が大好きでした。 「つき、か。いいねー、月。吾輩だいすきだよ」 「ウム。卿のエネルギーは月光を源にしてあるのである。よーく浴びておくである」 ニカッとご自慢のギザギザ歯を光らせて笑う博士。カーエデール卿も思わず笑ってしまいます。 博士や博士の助手であるDのいる科学班は、この世界にある大きな陸からすこしばかり離れた島にあります。周りの様相はどこの地域とも違う色をしているけれど、空から降り注ぐ白銀の光はどこにいても変わりません。 「月の力には諸説あって、古くから満月になると変身する生き物がいると言われているのである。吾輩、その説は大いにあり得ると思うである。なんとか使えれば或いは…」 ツバキ博士はたまに話しかけているのか、独り言なのかわからないトーンで呟きます。そんなときは決まっていいアイデアが浮かんでいるときです。卿はわくわくしながら、ふと博士の呟きにあった『変身』という言葉に思い当たる節がありました。 (あのとき、吾輩、へんしんしてたのかな?) 二人の見知った人たちが戦う。そんな瞬間を吾輩はただ窓の陰から見つめるしかなかった。 いろんな人たちが戦って怪我をして、息耐えていった。種族違いでケンカしていることは、前に黒い豊かな髪をもつ騎士さんから聞いていたけれど、あの日は違ったんだ。 (なんでおなじヒト同士なのに戦うの?) 吾輩にはきっともっと計り知れない何かがあったのかもしれない。 あの日も月がすごく丸くてきれいな日だった。海に映る光を見ながら月光浴をしていると、海の近くに佇む城にかけ上る、たくさんの兵士さんたちが見えた。松明を掲げ、駒に乗る兵士さんの中に見覚えのある緩やかに波打つ黒髪の騎士がいる。 (ジルキオさんだ。…すごく怖い顔してる) ブルッと震えながらも、一体何をそんなに急いでいるのか吾輩は気になって、その城の回廊奥で輝くステンドグラスまで飛んでいくことにしたんだ。 月光を照り返してキラキラ光るあのお城のステンドグラスは、吾輩のお気に入り。 (ステンドグラス、見に来たってわけじゃ…なさそうだよね) お城に近づくにつれて、鼻をつく鉄のような臭いが充満していた。 ーーーこれは、ヒトの、血の臭いだ。 やっぱり引き返そう。咄嗟にそう思い直したその時、ステンドグラスの前に人影が見えたんだ。なんとか中が見える場所に潜り込むと、そこには右側は白銀に流れる髪、その反対はすっぱりと剃りこんだ特徴のある髪型に上半身には入れ墨を持った人物の後ろ姿が見えた。 (あれってせんちょうの横にいた、ヴラドくん…だよね?) (ヴラドくん、ジルキオさんと戦うの?) (なんで?) 頭のなかで疑問符がグルグルしてしまう。お話をするだけじゃないことはすぐ雰囲気でわかった。あまりにも殺気と興奮と熱気が満ちていたからだ。 回廊からかけ上がる多くの足音が近づいてくる。 ヴラドくんを見つけて何やら話す声がして、兵士たちがざっと詰め寄るのが見える。…と、その時ジルキオさんの一声で彼の脇を抜けていくようだった。 (なんだ、戦わないんだね) 吾輩がほっとしたのもつかの間、兵士たちがいなくなってから、今度はヴラドくんとジルキオさんが対峙したんだ。そして… 吾輩はただ怯えながら、二人の戦いをみつめて、怯えながらもどこかで剣と剣のぶつかる音や飛び回る姿に興奮して見いる。 (どっちも…無事でいて) 幾度か交わす剣の音、空を切る音。そして。 互いに何かを話し、もう一度、鋭い一太刀。 吾輩は二人の殺気に気圧されて思わず目を抑えた。…恐る恐るもう一度、二人に視線を合わせると、ジルキオさんがしゃがんでるのが見えて、声を出しそうになった瞬間、今度はヴラドくんがこちらに駆け寄ってくるのがわかったんだ。 「ヴラドくん!」 吾輩が叫んだと同時にステンドグラスを割って城を飛び出す彼を、ただ救うことしか浮かばなかった。片腕があったはずの断面から多量の血が舞い、眼下の海に落ちていく。吾輩も必死で 落下速度に合わせて彼にしがみつく。 (このままじゃ海面にぶつかる!!) 必死に勢いを止めようと精一杯の力でヴラドくんを持ち上げようとするけれど、吾輩の非力さに涙がこぼれた。 (いやだ!いやだ、吾輩、ヴラドくんを助けたいよ!) 不意に羽が大きくなった気がした。いや、羽だけじゃない。さっきまで小さかった手足が、小さなケモノではないヒトの手足になっていたんだ。 これなら、きっと、飛べる! 海面スレスレを滑空して、すぅっと飛行する。抱えられた彼の爪先が水切りのように海面を跳ねる。もっと高く飛べればと思ったけれど、それは無理そうで、ギリギリを飛ぶのでやっとだ。両腕でヴラドくんを抱えながら、いつもよりは力が出たとはいえ、じわじわと支えている腕の痺れに、ヴラドくんとは違うか弱さを感じていた。 (なんとか…もうちょっと離れた陸地にいかなきゃ。) このまま飛びつづけられる気はしなかった。けれどここで海に落ちたら、腕のなかで気を失ったままの彼と肉食魚のエサになってしまうだろうことは必至だった。 未だに断面から流れる血も心配でならない。とにかく半泣きで飛び続けたんだ。 「…あ、あれ…陸だ!…陸だよ、ヴラドくん!」 「…」 一瞬、目がゆっくり開き、苦しげだった口元にいつもの不敵な笑みを浮かべて、また目を閉じた。 (よかった、まだ生きてる) ほっとした瞬間、突然力が抜け、ザバッと海に落下してしまう。低空飛行で浅瀬まで着ていたからよかったものの、二人ともいっぱい海水と砂を噛んでしまった。 ぐったりと浅瀬に寝転んで、波の泡立ちに濯がれる。吾輩の身体はもういつものケモノの姿に戻っていた。ふぅ、とため息をついて彼の右腕があった場所を見つめる。 (まだ、やることがいっぱいだ) 「博士、吾輩ってもしかしてへんしん、出来るのかな」 「…ん?卿はもう新月になると…」 博士は言いかけたところでみるみるばつの悪そうな顔を浮かべました。そして唇を真一文字にして言葉を飲み込みました。 「シンゲツ?って何?」 「ゴホゴホ!いや、何でもないである。そうであるな!卿なら変身できる可能性は大いにあるである!」 科学者の魂に火がついたのか、黄金色の瞳をキラキラさせて博士は話します。卿はぼんやりと思い出しながら、クスクス笑いました。 「えへへ、あのね。吾輩、実はもう変身したことがあるんだよ!今一緒に旅してるヒトを助けたときにね、今日みたいな真ん丸の月が出てて…それで多分変身できたんだ」 カーエデール卿の言葉にツバキ博士は目をぱちくりしました。 「なんと?!そ、それは本当であるか?!うむ、うむ、ちょっと待つである。」 博士はバタバタと資料を漁り、Dにも指示を出しながら目当てのものを見つけたようで嬉しそうに卿のもとへ駆けてきました。 「これである」 「これは、なあに?」 渡されたのは銀に光る丸い珠でした。 「これは、いま空に光っている月の石を圧縮して固め、研磨した珠である。月光浴をする時にはこれにも光を浴びせてやるといいのである。まだ効果はないやもしれないが、いつか肌身離さずもっていればいつでも変身できるようになるである」 話を聞きながら、卿はその珠をこねくりまわしては嬉しそうに抱きしめました。 「ありがとう、博士!これで吾輩もっとヴラドくんの役に立てるようになるかな!」 キラキラと嬉しそうに話す卿の頭をなでて、うなずきながら、うむと微笑みかける博士。 「ヴラドくんというと、ああ。卿が吾輩に腕を治してって言ってた子の名前であるな。ここへは生身のヒトが来れる道がないから如何にと考えていたのであるが、卿がこれで長く変身出来るようになれば、無事に連れてこられるかもしれないであるな。その時は吾輩も腕をふるうである!」 博士の言葉にまた嬉しくなって、えへへと笑う小さなケモノ。 ふと、博士はあることに気づきました。 「卿、先ほど『今日みたいな真ん丸の月』といっていたであるな?…ふむ。もしかしたら今日も変身できるかもしれないである。」 「え!…で、でも吾輩あのとき無我夢中だったからどうやってなったのかわかんないよ?」 博士の言葉に驚きが隠せない卿でしたが、どこかワクワクした様子で言葉じりが浮わついたようになっています。今日は満月の夜。海の上には綺麗な真円の月が浮かんでいました。 「一度変身出来たのなら、きっと出来るである。屋上で月光浴をしてみるである」 博士もどんな風に変身するのか、好奇心と探究心で一杯のようでした。 一人と一匹は急いで屋上に飛び出し、いつもより近くで月を浴びることにしました。 「きれいだねえ、博士」 満月をぼんやり見つめながら、いくらか時間がたった時。それは始まりました。月光につつまれて卿の身体は光を放ち、光のなかで羽が大きくなり、手足が延び、体や頭にも変化が見られました。 「これは…」 ごくりと、唾を飲み込み目の前で起きる奇跡にただ目をぱちくりするしかできない博士は、触れるのをぐっと我慢して変化の形態を見つめました。 月光を照り返す白い肌とふわりとした赤い髪と大きな角。薄朱色のひらりとしたドレスに包まれた少女がそこにいたのです。 「博士、吾輩変身…」 手のひらと甲を交互にみつめ、顔を撫でて自分自身の変化に驚く卿と、思わず口をあんぐりさせ、そしてすぐに嬉しそうに歓声をあげる博士。自分が作った生物の変化に研究者冥利につきたのか、本当に大喜びしています。 「大成功である!なんと…そうであったか。卿、ヒト型だとメスなのであるな」 「えっ。あ、あ、ほんとだね。」 へへ、と互いに笑いながらまた月を見上げて嬉しそうに月光を浴びるのでした。 ーーーーーーーーーーーー あとがきと言う名の言い訳 すんません、無駄に長くなりました。ヴラドくんの「初戦」らへんのとこの話と、卿が変身することの話をかこうと思ったらなーんかこう…まとまってんのかなあという感じに; ジルキオさんとも会ったことがあるていで進めてみました。あっちこっちいくからね、卿は! ヴラドくんと会話させるシーンいれるつもりがほぼ博士とのフリートークになってしまって。。いつもすんません。 科学班には普通にヒトが入ったりできないようになってて、他国との話も多分卿か別の通信手段で連絡してやりとりしてるのでヴラドくんを連れて腕直すのは卿がいつでも変化できるようになってから或いはエルフのアーティファクトかなんかで移動するかみたいな感じじゃないですかね。(ただ、エルフサイドからは危険地域だから閉鎖してる出入口とか…)とにかく普通に来ても実験体たちに襲われて腕治すだけで済まないはずです。 ちなみに卿はヒト型だとメス→ケモノ型だと雌雄同体です。ここ、テストに出るよ!(出ない)


その日は、百年に一度と言われる嵐が島全体を包んでいた。 豪雨と暴風が、木々をなぎ倒し、そこかしこに暮らす生物の生命を脅かす。まだ日中であるにも関わらず、深夜のように闇に包まれた空に時折猛烈な雷光、即座にバリバリと音を鳴らし天地にヒビ。天から落ちたのか、はたまた地上から生えたのかわからない、恐ろしい数の稲妻が走る。 「素晴らしい!!今日をおいて他にこれほど最高の日和はないである!!」 天地を揺るがすかのような騒音に歓喜の声を上げたのは、この島にある科学班の博士・ツバキであった。帝国領の付近に浮かぶ島(とはいえ、どこの領地にも属さない無人島である)に、科学班はある。元々どの種族も暮らしていない緑豊かな無人島であったが、俗世から離れ実験に没頭するためだろうか、博士はここを本拠地として日夜怪しげな実験を行っている。他の国々や、種族達には到底作ることは不可能であろう機器が研究所に所せましと設置されている。博士の科学力や技術は外界と同じ時間が流れているとは思えないほどだ。その力を我が物にしたいと要求する国は後を絶たない。 「雷からのエネルギーは本日予定している強化実験へ有効に利用できるかと思われます。現在エネルギー質量および充填量を計算中…」 涼やかに話す女性の声…恐ろしく透明度のあるその声の主は、試作4号“D”。しなやかに指先を動かし、空中に浮かぶ透過した画面を見つめ何らかの計算をする。腰まであるサラリとした銀の髪、鼻筋の通った整った顔…、海面に緑のインクを少し垂らした雫をそのまま閉じ込めたような瞳は、まばたきすらしない…彼女は博士に作られた人造人間だ。 美しい肢体の色は銀色に光り、雷光の度にキラリと照り返す。彼女がはじき出した数値をみて満足そうに博士は頷いた。 「うむ、何もかも予定通り!吾輩の予想が的中したであるな」 眼鏡を押し上げニカッと、さも嬉しそうにギザギザの歯を見せて笑う博士に、少しばかりため息をついて残念な表情を浮かべてみせる、もう一人の人物…-。 「ええ、賭けは吾輩の負けのようです。さすがはツバキ博士」 ボサボサと伸ばしっぱなしになった朱色の長髪が印象的な彼は、ツバキ博士の助手・マガトキであった。ひょろりとした長身に長く伸びた手足。切れ長の瞳は金色に光り、厚みの薄い唇には普段から微笑をたたえているせいか、先ほどの曇った表情もすぐに消えていた。彼には少し特徴のある箇所がある。耳の部分には蜻蛉の羽のようなものが3対生え、額には角が1対。異形の者特有の風体であったが、以前はそこらにいる人間たちと何ら変わりのない好青年の姿だった。科学班に入り、人体実験を幾度か自身にも施した結果現れた症状だという。 「そうであろう、フフフ、さあ、今日こそは件の実験、成功させてみせるである!!!」 ツバキ博士は興奮ぎみに目を見開き、豪雨で荒れ狂う外からの音さえかき消すほどに大声で叫んだ。 生物実験は毎日のように行っている。被験者の強化、合成、…材料となる生物は比較的たやすく準備できる。奴隷の売買が日常的に行われているのだ。場合によっては国家の兵士強化をと、進んで提供してくれる某国もある。 しかしこの日生物実験する対象は、少しそれらとは違った。 科学班で細胞から作られ、大きく成長した人造の獣。獣とはいえ、知能も高く筋力はケタ違いに強い。獅子のような姿に額からは水牛のごとく巨大な角が生えている。全身は、赤褐色の体毛で覆われ、見るものを圧倒させる巨体であった。名前はカーエデール。博士は敬意をこめてその獣を『卿』と呼んでいた。 「博士」 重低音でボソリとつぶやく。実験を行うため、ベッドに横たえられた獣は目を細め博士を呼ぶ。 「…卿、大丈夫である。これからさらに卿を強く、そして希望通り翼を授ける準備は万端である。吾輩に任せるである」 ゆっくりカーエデールの額を撫でて笑う博士に、獣は嬉しそうに鼻をフフンと鳴らした。そして真似るように博士の髪を撫で、彼の言葉に安心したように瞼を閉じ、深く息をした。 マガトキは様子を見ながらカーエデールの肩付近から麻酔効果のある薬剤を打つ。 「科学班のためにこの身体、捧げる所存。信じていますよ、ツバキ博士」 それだけ言うと、静かに眠りについた。 「脈拍正常、血圧は通常よりやや低めです」 Dが淡々とカーエデールの状況を説明しながら、記録していく。まったく無駄のないその動きはさすが人造人間といったところだろうか。ツバキとマガトキは目を合わせ、術式用の手袋をパチンとはじいた。実験開始の合図だ。 背部に“翼”になるだろう小さい羽根とピンク色の肉塊をねじ込む。縫合しながらDからの情報を聞く。その後、今度は横腹から少し刃を入れ、皮下をめくる。脈動する臓器に新たな生体装置を取り付け、縫合。 何もかも順調に進んでいた。 ――最後の仕上げをする、その瞬間までは。 「さあ、総仕上げである。エネルギーの準備は?」 「すべて完了しています。」 「よし、マガトキ。解放装置を」 「エネルギー解放。カーエデールに注入します」 瞬間。 強烈な光が研究所内を包んだ。 否、光だけではなかった。轟音と共に青白い閃光は研究所の装置すべてを起動停止にさせ、カーエデールと助手であるマガトキを貫いてしまった。 「卿!!」 博士は叫んだ。閃光のせいで眩暈がする。耳も先ほどまでの豪雨で騒がしかったのに突然の轟音の後、無音のようになった。自分自身の叫びも、体内の底で響くだけに思えた。 じわりじわりと耳鳴りが起こり、通常の音になるまで時間がかかった。 「卿!!」 博士はもう一度叫ぶ。今度は声が聞こえる。長いまつげをぐむと瞑り、目が慣れるのを促す。必死で目を凝らすと、傍らに倒れるDの姿があった。 Dは、ほかの装置同様、強烈な閃光の後自力で動くことができなくなっていた。衝撃で記憶装置にも支障をきたしたのかもしれない。エラー音を鳴らしながら、博士に訴えている。歯をギリっと食いしばり、彼女の電源を落とす。 「少し待っているである…」 博士は三色に分かれた自髪をガシガシと掻いて、苛立つ様子を見せた。部屋の最奥部でバチ、バチと装置が鳴り、その奥から焦げたようなにおいが漂ってきた。 ソレは、黒鉄色をした咆哮する獅子の彫像。 ――いや、彫像ではなかった。 絶句しながらも、心のどこかであまりの美しい形状に歓声をあげたくなる。それほどに、その黒鉄色のソレは、獣そのものの姿をしていた。しがみつくようにする人型も、そこにあった。 「卿…」 博士はそっと手を伸ばした。指先が、一瞬触れる。 途端に、黒鉄色の彫像はボロボロと崩れ、砂山のように足場に積もる。あわててかき集めるけれど、握りしめるとただ手のひらを黒く汚すだけで、何もつかむことは出来なかった。 すべてが灰になった。 それを認識したのか、自嘲するように狂気じみた笑いを浮かべた。すべて失ったのだ。 嵐はまだ止んでいない。騒音の中、徐々に落ち着きを取り戻した博士は、ふと灰の山に何かがあることに気付いた。 (――また崩れてしまう) 一瞬躊躇して、手を引っこめる。すると、もそりと山がうごめいた。 別室の実験動物がまぎれたのだろうか。 さらにもそりもそりとうごめき、灰の山から赤いものが見えた。 「…手?」 驚きながらも急いで灰をどける。そこには全身が緋色のつるりとした肌に、頭に1対の角をもつ、小さな生物が丸まっていた。 その姿は胎児に似ていた。 よく見ると背中に薄い羽根をもち、長い尾のある猫のような生物だ。 「卿?まさかカーエデール卿なのであるか?」 博士がそういうと、丸まっていた生物は起き上がり、ぼんやりとした糸目で見返した。 「…吾輩…、よくおぼえてないけど、ツバキ博士のことはわかるよ」 にこりとして微笑むその顔は獣ともまた別の誰かにも似ていたが、博士にはそれが誰だったのが思い出せない様子だった――― 「…これが、あの日起きたことですよ」 口元に微笑をたたえながら、ゆっくり話し終えると彼はツバキ博士に視線を合わせた。 「…では…、その、君が助手の」 「ご無沙汰しております、博士。嗚呼…やっと再会を果たすことができました」 博士は目をぱちくりさせてもう一度、“助手”と名乗る男の姿を頭からじっくりと見回す。 ――やはり覚えがない。たしかにあの日、雷の暴走で閃光を浴びた記憶はあるが… 「いや、待つである。その話だと獣であった卿と助手は消し炭になったのであろう?なぜ…その…、君は」 「今は新月卿と名乗っております」 「あ、ああ、そうであった。なぜ何のケガもなく…生きた姿をしているのである?」 博士の問いに少し落胆した様子を見せる男…新月卿であったが、すぐにまた微笑を浮かべた。スッ…と眼差しを外に向け、静かなる闇夜を見つめる。 「貴方は吾輩に吸収する力を授けてくれた。吾輩は閃光が起きた瞬間、衝撃でカーエデールの身体にしがみつく形となったのです。閃光は吾輩たちを包み、焼き焦がしていった…その時、吾輩の一部がカーエデールと一体化し、今のカーエデール卿が生まれた。彼のものが日々過ごすにつれて、生み出す細胞を吾輩が少しずつ吸収し、吾輩は体内でひそかに再生を目論んでいました。 貴方も知っているでしょう。あの子は月の光で生命力を維持していることを。月が欠けるにつれ、あの子は徐々に眠りにつく時間が増える。そして、今宵のような新月の日…吾輩は新月の日のみ現れることができるようになったのです」 静かに、淡々と話す彼の横顔は夜空をぼんやりと見つめ、少し恍惚とした表情をみせていた。外からは涼やかな風が木々の葉を擦る音が聞こえる。 「そうであるか。…うむ。よくぞ戻ってきたであるな」 「ええ、まだ賭けの配当をいただいていませんから」 新月卿はそういうと、博士ににじり寄った。博士はギクリとして椅子から転げ、そのまま壁際まで追いやられてしまう。 「な、…ま、まて!その賭けは吾輩が勝ったのであろう?!」 息がかかるほどに近距離まで詰め寄られ、視線をあちこちに反らせて逃げ場を探す博士の姿にうっとりとしながら、新月卿は両手を壁に這わせて動きを封じる。 「いえ、残念ながら吾輩が勝たせていただきました」 唇が触れるか触れないかの距離で、さらに続けた。 「貴方はこう、言いました。『今日こそ記憶に残る偉業を吾輩が成すのである!どうだ、賭けてみるか、マガトキ』」 新月卿はそうつぶやくと口元に微笑を浮かべた。博士はただ、目を泳がせることしかできなかった。
そこはまるで牢獄のような、最底辺に位置する剣奴の部屋。ひどく高い位置に設けられた格子窓からは日の光が差し込んでいて、宙に舞う砂埃を照らしている。その先の日の当たる場所に、二人の少年はいる。ヴラドは粗末な藁の寝床の脇に座って、かつて「金色の蛇」と呼ばれ、栄光のすべてを手にしていた闘士の亡骸を見下ろしている。ヴラドはゆっくりと彼の身体の下へ手を差し込み、そっと抱きかかえた。 ――「いまをもって、俺とおまえは兄弟だ。なあ、こんなくだらねえことでお前は死ぬな。ひとりでも生き延びろ。安心しろよ、俺が死んでこの体が腐り果ててクソ以下の存在になっても、地獄の底からお前を見ててやる。お前を愛してる。絶対に忘れるなよ。俺を、忘れないでいてくれ」 これがルカの最期の言葉である。 生まれて十数年、食事と人殺し以外に使ったことのなかった生傷だらけの両腕に、初めて抱く人間。それは枯れ枝のように痩せこつれ、たった今自分の兄となった人間の亡骸。強く抱きしめると、ぽきりとどこかの骨が折れる音がした。しばらくの間をおいて、ヴラドは彼をゆっくりと床におろした。闘技場へ向かおう。次の試合がいつも通りの熱気と狂気をもって始められるだろう。今回ばかりは処刑という方が正しいかもしれない。 「もういいのかよ?ありゃ、死んじまったか」 ドアの前で見張りをさせられていた太ったごろつきが話しかけてきた。 部屋を覗き込んで大きな溜息をつく。 「しっかし金色の蛇ともあろう闘士がこんなみじめな最期だとはなァ…ラガルト様もむごいお方よ。しかしヴラド、お前もこれからどうすんだ。試合に出たところで無駄死にするだけだぞ。なあ、おれの知り合いの連れにジャックって逃がし屋がいる。今からでも遅くはねえ!そいつに頼んで…」 ウラドは何も答えず、ごろつきの肩を二度叩いてその場を立ち去り、闘技場へと向かった。 「行っちまいやがった。…ルカ坊よぉ、お前の弟も直ぐにそっちへ行っちまうかもしれんぜ」 「…かれは試合に出るのですね」 「ああ…ん?…うわぁ!」 太った男は大仰に驚いて尻餅をついた。いつの間にか背後に眼帯をした少年が立っていたからである。 見た目はまだ10歳程で、どうやってここまで入り込んだのか見当もつかない。 少年はヴラドの去った方向へすたすたと歩きだ出し、男の脇を通り過ぎる。 「全くどこのボンボンだ!ここはガキの入っていい場所じゃあねえぞ!くらぁ!」 男が振り返って怒鳴った時には、少年の姿は煙の如く消えていた。
(特務隊の戦闘スタイルとかお仕事とかの雰囲気小説です。例の後編はまた今度…) 「馬鹿なことを…」 ジルキオは嘆息する。槍を向け自分を取り囲む私兵達と勝ち誇った表情で兵をけしかける男を、片目を眇めて眺める。敵意なきことを示すために剣を預けたため全くの丸腰で、これ以上ないほどの危機的状況だというのにまるで他人事のような態度ですらあった。 「犬を始末して、その先はどうするおつもりです?仮に私を殺せてもて、露見するのに一日とかからないでしょう。その先のことはお考えになっていますか、パーヴァス卿…」 言葉に嘘は一つもない。既にパーヴァス卿は翻意ありと中央から目をつけられているのだ。革命に不満を持つ前体制派の一派である彼のきな臭い動向を危険視して内密に逮捕命令が下されたが、反乱を実行に移す前ということもあり表向きは調査同行依頼のためと称して接触した。しかし話し合いもそこそこにこの有様である。政敵の重要人物ながらこの軽はずみな行動には呆れて憐憫の念すら湧く。馬脚を現すにしても考え無しにも程があった。 「命乞いと交渉はもっとうまくやるべきだったな黒犬…!残飯漁りが似合いの貧民が身の丈に合わぬことをするからだ」 優位を確信してるがゆえの同情めいた傲慢さが言葉の端々に臭う。先帝の庇護に甘んじてプライドだけ肥え太らせた男の肥大しきった慢心に、ジルキオの涼しい面差しに不快の色が過ぎる。 「命乞い…それをするべきは貴方でしょうに」 先代の特務隊隊長が死亡し跡を継いだばかりの、齢もまだ30に遠いジルキオは先代の威を借る若輩者と軽視される向きが強く、こうして舐められることもままあった。組織の頭が変わっても、公爵の猟犬たる特務隊の鼻も牙も鈍らないということを知らない者はあまりに多い。 「これは警告です卿よ。与えられた機会は有効にお使いなさい。もう一度だけ、お願い申し上げます。我々特務隊に『ご協力』を。貴方にしか語れぬことがございますので」 無数の切っ先を向けられてなお全く動じず、辛抱強い静かな口ぶりで説得を繰り返す。戦わずに済むならそれに越したことはない。だがそんな姿勢を虚勢ととったか弱腰と見たか、パーヴァス・ハクスリー爵は嬲り殺しを夢想するかの如き表情で、蛇が舌を鳴らすような嘲笑を歯列から漏らしてはっきりと首を振った。 「貴様らに語る言葉など持ち合わせてはおらんわ、盗人公爵の犬め!」 「…そうですか、残念です」 その一言が結ばれるよりも早く、ほとんど無防備にすら見えたジルキオの手が目にも止まらぬ速さで突きつけられた槍の柄を捕らえて兵の一人を引き倒し、倒れ込んできたその兵の腹に石突きを叩き込む。返す手でもう一人の腕を掴んで捻り上げて足を払い、瞬く間に膝をつかせると腰に下げられた片手剣を奪って手早く喉をなで斬りにした。 二人が地に伏せるまでの間になんとか動揺から立ち返って次の一手を警戒する他の兵たちから距離を取り、油断のない目で間合いを計る。包囲したまま攻めあぐねている兵が六名、さらに広間に詰めているものもめいめい得物を取りじりじりと距離を詰めてくる。今は二十人ばかりだがすぐに増援が駆けつけるだろう。 突然の反攻に泡を食ってパーヴァスが広間の勝手口側からまろぶように逃げ出していくのと同時に、控えさせていた部下二人が交渉決裂を察知して正面扉から突入してくる。 「ボス、無事ですか!?」 「手間取りすぎだエヴァレット、剣を!クローディア!パーヴァス卿を捕えろ、生かしてだ!」 「了解です」 簡潔に一声返事を残して、栗色の髪をひとつに結った細身の女がパーヴァスを追ってゆく。鳥のように身軽で猫のように音もなく駆け抜ける彼女は、その魔術の才でジルキオの命令と期待を裏切ったことはなかった。今度も間違いなくそうなるだろう。 同時に部屋に飛び込んできたもう一人の青年が右手に血に濡れた剣を引っさげ、左手にひと振りの優雅な長剣を抱えて駆け寄ってくる。彼は新手の登場に矛先を変えた兵たち数人を無造作に薙ぎ払いながら人使いの荒い隊長に抗議した。 「これでも急いだんですよー、全力で!」 ジルキオはどことなく間延びした部下の青年の言葉を無視して、粗悪な片手剣を投げ捨てると自身の手に馴染んだ鋭いレイピアを受け取る。 「下はどうなっている」 「とりあえず押さえました、軍から借りた連中と一緒に封鎖にあたっています」 「申し分ない、あとは彼らの相手をするだけだ」 広間には特務隊隊長の実力を目の当たりしても戦意を失わない兵が踏みとどまり、それどころか騒ぎを聞きつけて駆けつけてくる者でその数は増えてゆく。 形勢は相変わらず人数で劣る特務隊が不利に思われたが、ジルキオは切っ先を下げるようにレイピアを構え、兵たちの次の動きを余裕の佇まいで待った。エヴァレットは使い込まれた剣をやや高く構え、隊長の一手と敵の顔色を伺っていた。その表情には場違いな愉快そうな色が微かに滲む。焦れるような睨み合いの拮抗はすぐに崩れた。 一人の兵が間合いの優位を確信して果敢に繰り出した槍をジルキオは半身を捻って躱し、左手の甲で柄を押しのけて相手の懐に躍り込む。その大きな一歩の踏み込みで一瞬のうちに不利な間合いを踏み越え、勢いのままにレイピアを相手の胸へと突き入れた。よく手入れされた刃は容易く肉を貫き、鈍い感触を腕へと伝える。びくんと痙攣して崩れ落ちた肉体を蹴り飛ばして剣を引き抜き、さらに手近なもう一人も片付けた。 全体の連携が取れておらず、重大な局面で冷静さを失っている兵たちの動きを見て、実戦経験なしと判断する。近年大きな戦もなく、革命派の一方的な粛清と貴族私有の騎士団解体が断行され、兵力の国軍一極集中体制へと再編成されたことで、中央の新体制派と地方へ飛ばされた旧体制派との間の力関係は急速に天秤を傾けつつあった。その影響が如実に現れた嘆かわしいほどの練度。もう何人か始末して脅せば戦意を挫けるだろうと読む。 無謀にも突っかかってくる者の斬撃は真っ向から受け止めず、細身の刀身で羽で触れるように軽く受け流す。相手の隙を誘い、無駄な手数は一切挟まず、確実に急所を貫き、それでもまだ立ち上がろうと足掻く者の背を念入りに軍靴で踏みにじる。できるだけ残虐に見せ、揺さ振りをかけて動揺を生み、一気に心を折る。このような無慈悲な行いを容易くやってのけるためにしばしば死の前兆と忌み嫌われる黒犬になぞらえられる冷酷な男は、しかし、ほとんど美しいといっても良いほどの剣筋を誇っていた。 今また左足を引いて上体を逸らし攻撃を避ける、その危ういバランスを保つために上がる左手の指先から、狂い無くレイピアを振るう右手、次の一歩へ淀みなく繋がる足さばきに至るまで、まるで一曲の音楽のように心地よい緊張感に満ち自然な連なりを描く。修練と実戦の中で何度も繰り返し磨き上げた楽章に相手を引き込み、自分の独壇場で流れるように殺戮する。たった二人に対して束になってかかっても傷一つ負わせられないどころか仲間が次々と倒れていく事実に、さすがに数で勝る兵たちにも動揺の色が見え始める。 「隊長、そろそろじゃないですかね」 「ああ、頃合か」 ざっくばらんだが柔軟で機敏な剣筋で補佐していたエヴァレットも形勢が傾いたのを感じたのかジルキオに声をかける。適切な読みに頷き返してやりながら一旦切っ先を下ろしてぴんと背筋を伸ばすと、きっぱりとした蒼い目で生き残っている兵たちを眺め渡した。 「これが最後通告です、投降しなさい。今ここで武器を捨て我々に帰順したものの命は保証しましょう」 「死にたくないでしょ、うちの隊長、殺るときは殺るよ」 エヴァレットも剣を担いで相槌を打つ。 何かを成すのに、誰よりも早く行動するのは難しいことだが、誰かが言い出さねばならない。しかし誰も剣を捨てようとはしない。兵同士はお互いの顔色を伺い、互いの圧力に動けずにいた。 とその時、ほかよりも立派な制服の男が一団から躍り出ると、剣を腹の辺りで構え、死に物狂いで突進してきた。 「公爵の犬に売る魂などありはしないぞ!!」 凶暴な感情に男の表情は歪み、ぎらぎらとした目と無感情な蒼い瞳の視線が交錯する。だが勝負は一瞬だった。ジルキオは猪突猛進な一撃をあくまで冷静に、闘牛士のようにひらりと躱して手首を返し柄頭で顎を強打した。頭を突き抜けた強烈な衝撃に膝から崩れ落ちた男の肩に間髪入れずにレイピアを突きたて、叩きつけるように床に押し倒す。呆然と大の字に転がり口から血を流す男の投げ出された腕を踏みつけ傲然と立ちふさがると、ジルキオは燃えるような氷の目で男の愕然とした顔を見下ろした。 「…貴方が兵隊長殿ですね?貴方の可愛い部下たちにひとこと、命を大事にするよう伝えて頂けませんか?」 肩から豊かな黒髪が流れ落ち、ジルキオの冷たい表情をぞっとするような色に翳らせる。慇懃な言葉を紡ぐ薄く控えめな口元だけ妙に女じみた形をしていたが、それは優しさを連想させることはなく、むしろ底冷えした端正な面差しを一層恐ろしげに見せていた。 床に伸びた兵隊長は悔しげに唇を噛んでジルキオを睨みつけたが、肩に突き立てられた剣をぐいと押し込まれてうめき声をあげ、憎々しげな表情を隠そうともせず、砕かれた顎を難儀して動かしてやっとのことで投降を命じた。 「みな、武器を捨てて、犬野郎にしたがえ」 兵たちは顔を見合わせたが、苦々しい顔で次々に武器を足元に投げ捨て、その場に膝をついて投降の意思を示した。 それを見届けるとジルキオは兵隊長の肩から無造作に剣を引き抜いて足をのける。思わず見とれてしまうような優しげな作り笑いが彼の鋭い目尻に張り付いた。 「勇敢なご判断とご協力に感謝致しますよ、兵隊長殿」 完全な敗北を悟って抵抗を一切やめた兵隊長と投降した兵たちをエヴァレットに任せ、ジルキオはパーヴァス卿追跡に放ったクローディアを追いかける。広間を出て廊下を抜け、足早に階下へと向かうと、クローディアが階段を下りきったすぐ近くで凛とした背を見せて佇んでいた。その足元に目をやれば芋虫のように転がされたパーヴァス卿の姿もあった。単純だが有用な捕縛魔術で拘束されていることをひと目で見てとって、大股で近づく。 「クローディア、ご苦労。随分静かだが、塞いだのか?」 「ええ、女性の前で口を開かせるには少々躾がなっていませんでしたので」 ジルキオにも劣らぬ冷淡な声に煩わしげな忌々しさを漂わせて彼女は柳眉を顰めた。捕縛して拘束する間、口汚い女性蔑視論にでも付き合わされたのだろう。気の毒なことだ、と転がされたパーヴァス卿に視線をやる。クローディアは気に食わない相手に優しくするほど淑やかな性質ではなかった。 「まったく、困りますね、パーヴァス卿、貴方のご立派なご両親の品位まで疑われるような振る舞いは」 クローディアに合図して沈黙の魔術を解かせると、パーヴァス卿は顔を真っ赤にして押し込められていた罵倒を撒き散らした。 「その父を殺したのは貴様だろう犬め!あの成り上がりのエセ公爵の靴を舐めて尻尾を振ったんだろう!いいや、振ったのは尻尾だけじゃなさそうだなメス犬が!その上女に権力を与えるなど惰弱で恥知らずな!何処の馬の骨ともしれない貴様のような乞食がのさばるようでは帝国は御終いだ!」 四肢を折り曲げて縛り上げられた体をよじって一息にまくし立てるパーヴァス卿を、ジルキオは顔色一つ変えずに見下ろす。そばで小さく「下衆が」と吐き捨てて戒めの魔術をきつく締め上げるクローディアを手で制して片膝をつき、拘束の痛みに呻き声をあげながらもまだ何か飛び切りの侮蔑を必死に考えているのであろうパーヴァス卿の憤怒の形相を覗き込んだ。 「そうですね、貴方の知っている帝国はもう御終いです。ここから先は、私たちの帝国となる。貴方の言葉など、もう我々に届きはしないのですよ、パーヴァス卿」 革命勃発より5年。先帝の遠戚に連なる、前時代の有力貴族の復権の要とも言える男がついに執政派の猟犬に追い詰められた瞬間であった。
12歳のヴラドが闘技場で獅子の獣人に殺されかけているのを救った少年。(別項参照)気まぐれで雇い主の富豪に頼んで盛り上げ名目で自らの乱入を許可させ、さらには自軍に引き入れた。 長く腰まで伸ばした美しい金髪と青い瞳、浅黒い肌が特徴的。剣士としての実力も抜きん出ており、腰に差した二本の短刀で曲芸のように攻撃をいなしながら素早く相手に組みつき首を裂く。見目の美しさをおぞましく際立てるその残忍な戦いぶりに闘技場の人気は確固たるものだった。 奴隷には少ない常に明るく飄々とした性格で、常に彼のまわりには他の奴隷が集まってくるが、一切それを拒むそぶりを見せることはなかった。しかしひとたび試合になれば相手には一切の容赦がなく、眉一つ動かす事なく首をはね剣を突き立てる。その実力と人望の厚さには雇い主も一目置いており、スターとして実子並の待遇を受けてもいた。 ヴラドのことを自分の弟の様に可愛がり、彼に生き残る術を教え、ヴラドにとって友以上に師であり兄のような存在でもあった。ヴラドが才能を開花させ肩を並べるまでになると、2人は闘技場の花形として名を上げ、数年の間彼らは闘士としての名誉を欲しいままにしたという。 しかしその幸せも突然に終わる。 ヴラドが17になったころに彼の存在に飽きて疎ましく思った雇い主が、彼を慕っていた取り巻きの闘士を全員殺害し、彼自身にも毒を射たのである。重い病に伏し、死に向かう直前にヴラドと兄弟としての血の契りを交わして、彼はその20年の短い生涯を閉じた。毒に犯され痩せ細ったその亡骸はまるで枯れ草の様だったという。 (設定としてはジェイド船長が彼の生き写しというもので、ヴラドがジェイド船長にこだわる理由の一つです。ヴラド君、思春期においては割とまともな青春送ってます。その辺もおいおい創作できたらなと思います…)
むかしむかし あるところに いっぴきの 小さなけものが いました。 ネコくらいの大きさで空の色がすけるトンボのうすい羽と、頭には2本のつの、体は真っ赤で、空をとぶとてもふしぎな生き物でした。 そのけものは自分のことを「カーエデール卿」と呼んでいました。卿は言葉をしゃべり 世界中をとびまわって、いろいろな人たちと話をしました。 この世界には、人間、エルフ、鳥人、獣人、ドラゴン、吸血鬼、かいぞうされた生物…いろいろな生き物がいました。卿はいつも不思議に思うことがありました。 「どうして皆いっしょに生きてるのに、仲良くしないんだろう?」 ふしぎなけものである卿にとってはそれが自分以上にふしぎでなりませんでした。 ラース帝国にいくと、きっちりした制服に身をつつむ人間たちがいました。きれいな衣装に卿はうっとりしました。帝国をふよふよと飛んでいると、お城の高いところにある窓際に、ひとりさみしそうな人間がいました。 「こんにちは」 卿が声をかけると、驚いた様子で目を真ん丸に開きました。そしてゆっくりとその人間は卿の姿を頭のてっぺんからしっぽの先まで見つめ、 「…あ、あなたは?」 と話しました。少年の姿をしていましたが、声は少しばかり高く、卿もふしぎそうにその人間を見つめました。 「吾輩はカーエデール卿。貴殿は?」 「…この帝国の皇帝だ」 目線をはずし、そうつぶやいた彼は皇帝というにはあまりにも幼いように思えました。そして、あまり幸せそうに見えませんでした。 「皇帝?ならなぜそんなに寂しそうな顔をしているの?…この国は吾輩が見た中でも一番栄えてるというのに」 卿の言葉に彼はフフッと笑い、また目に憂いを浮かべた様子で卿に向かいました。 「…さあ、どうしてだろうね。卿に…話しても何も変わりはしないだろう」 カーエデール卿はむかむかしましたが、それよりも彼の寂しい顔が心配になりました。この素敵な帝国でも一番偉い人がこんなに寂しそうにする理由、なにかあるのだろうか。 卿は心の中にもやもやがあふれていきました。同じ人間が暮らすこの帝国の中でも、皆が仲良く暮らしているわけではない。そう見えたのです。 (同じ姿でいるのに、この人間の心はひとりなのかな。) 卿は皇帝の寂しさを少しだけ感じて、頭を下げ、そっと窓際から飛び立ちました。 姿かたちだけの問題じゃないんだと思いながら、もっとふしぎな姿の卿は心のどこかで吾輩の本当の居場所はどこだろうと、またもやもやと考え込んでしまいます。 夜になり、月明かりが世界中を照らし始めます。キラキラと静かに海面に照り返す月光が、カーエデール卿は好きでした。ぼんやりと海辺でその様子を見ていると、ズズズ…と大きな影が卿に覆いかぶさってきました。なんだろうと横を向くと、すぐ隣にそれは大きな船が岸に上陸していたのです。その船は立派ではありましたが、よく見ると船底はいたんで、すこしおんぼろな船でした。 卿はふわっと飛び上がり、船上にだれかいないか様子を見に行きました。すると、大の字に倒れている男が二人。甲板にいるのが見えました。 あわてて卿は近寄って声をかけます。 「だいじょうぶ?ねえ、…だいじょうぶ??」 卿の声を聞いて、小さく唸る青年。月光に照らされた髪は金色の少しのびた短髪で、肌は褐色に焼けている…身なりから若い船長のようでした。もう一人は首輪をして、髪の毛が半分だけ白くて半分は黒い変わった髪型の青年のようです。卿はどうしたらいいかあわてていると、枯れた声が聞こえました。 「み、…みず…」 「ミミズ?」 その言葉に脱力しながらも、のどの渇きを訴える彼の姿にやっと気づいた卿は、近くにあった農家から水を拝借して彼の前にビンを差し出します。船長はビンをとり、一口毒見をしてすぐに隣で倒れているもう一人の青年の口に、ビンをあてました。 「ほら、水、もってきてくれたぞ」 一口、一口とゆっくりと水が流れ、のどが動くのが見えて卿も船長もホッとして顔を見合わせました。そして少なくなったビンの残りを船長が飲み、水面に光る月光のようにキラキラと目を輝かせ、すぐにニッコリと笑いました。 「ありがとう、赤いの!なかなか島に到着できなくってな…やっぱ海は甘くねえや」 「よかったね。…あの、あの人はだいじょうぶ?」 赤いのと呼ばれ、卿はきょとんとしたが、彼はあまり卿を見て驚く様子はないようでした。あたたかな笑顔に心がほっこりとしました。 「大丈夫だ、問題ない。あいつはそんなヤワな男じゃないぜ。…まあ水がなくなったときはさすがに焦ったんだけどな」 「海に水があるのに?」 卿がそういうと、船長はハハハと笑い出します。 「あんなの飲んだらのどが焼ける!ま、ちょっと準備不足だったみたいだ」 準備不足という言葉に卿は疑問に思いました。普通の漁師さんならきっと航海の想定はしているんじゃないのか、それに水が尽きるほど長く船を出すことは少ないんじゃないだろうか。卿はそう思ったのです。 「船長さん…は、漁師さんじゃないの?」 「?ああ、わかるか。…俺たちは、そうだな…―――」 「おい、…そんなよくわかんねーいきもんに言う必要ねえだろ」 後ろから突然声がして、卿はびくりとしました。さっき倒れていた青年が起き上がってきたのでした。 「お、ヴラド。もう大丈夫か」 「ったく…んだよ、だからあのルートやめとけっつったんじゃねーか」 少し怖そうな人間でしたが、船長が嬉しそうに話しているのでそこまで悪い人間でもないのだろうと卿は思いました。 「あーそうだっけ。まあこうして助かったんだし!そうそう、この赤いのが俺たちに水、持ってきてくれたんだぞ。よくわかんねーいきもんとは失礼じゃないか」 「アンタもその羽虫、赤いのっつってんだろ。それは失礼とはいわねーの?」 「はむし…」 卿は(やっぱりこの人怖い)と思いました。 「ごめん、恩人さん。ほんとに助かったよ。俺はジェイド。君は?」 すっと手を出して握手を求めているようでした。船長の手に卿はちいさな手を伸ばし、握手をすると、にっこりと笑っていいました。 「吾輩はカーエデール卿だよ」
【名前】ハーディア・ロート(Hardia・Rot) 【性別】女 【年齢】人間換算30代中盤 【種族】エルフ 【所属・役職】王室専属家庭教師 【性格等設定】 真面目かつそれなりに冗談もこなす穏やかな気性の持ち主。 堅物に見られることも少なくないが、マイペースな王族兄妹達の振る舞いもそれなりに楽しんでいる。 特に姫君の脱走報告は楽しみの一つで、彼女の見つけてくる不思議なものの話が一番好き。 【備考】 濃い緑の瞳。赤毛を高い位置で結ってまとめている。 教育係として任命されるまでは外交官としての任についていた。 嗜みとしてある程度ならば剣を扱う事もできるものの、本職には遠く及ばない。 もっぱら頭脳担当で、王族兄妹達に自身の知り及ばぬ事を質問されてもすぐに答えられるよう、 分厚い辞書を常に携えている。ごくごくたまに武器にもする。 いい加減適齢期もいいところだが、今は自分の幸せより姫君の幸せが優先。 手のかかる、もとい手のつけられない弟がいる。 【ステータス】 ★HP:150 ★MP:250 *攻撃力:10 *魔力:50 *防御力:20 攻撃方法:魔法
【名前】 マシュー 【性別】 男 【年齢】 三十台後半~40代前半 【種族】 人間 【所属・役職】 公爵位。帝国執政。征夷大将軍という感じかも。 【性格等設定】 冷酷。武より知を好む。この辺は過去とも関係あるようだ。 敵には一切の情け容赦しないが、臣下は家族同様に扱う。 【ステータス】 ★HP: 150 ★MP: 350 *攻撃力: 10 *魔力: 60 *防御力: 30 ただし膝だけは強固な積層立体魔法陣に守られているので、消し炭にされても膝だけは残る 攻撃方法:主に魔法。といっても派手な破壊魔法は使わない。 スネア(転ばす)、スリープクラウド(眠り)、スタン(麻痺)等の状態異常系のヤな魔法系と 地の利を生かして戦う方。 昔は冒険者で傭兵をしていたり、膝に矢を受けて衛兵になった経験もあり、人並みより少しマシ 程度には剣を扱えるが、剣豪と言うわけではない。 趣味:部下いぢり。 他にも秘密があるようで、千の無・・おっとこれ以上は秘密だ。