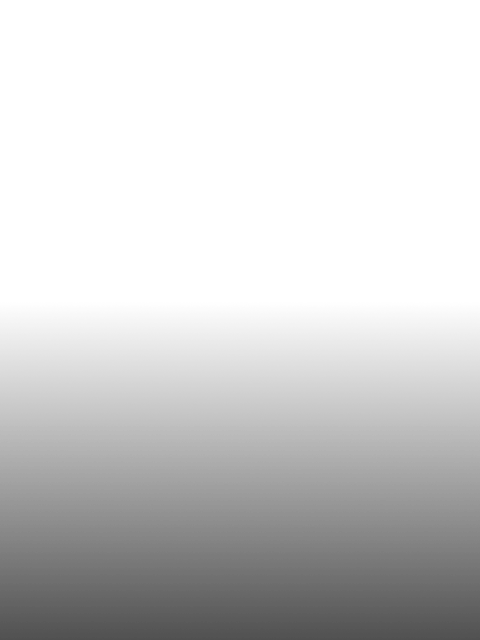利用条件
- チャンネルの購読はのに限られます
- チャンネルの購読はに限られます
- チャンネルの購読はに限られます
- チャンネルの購読はに限られます
- チャンネルの閲覧にはフォロワさんでRPG詰め所へのアカウント登録/ログインが必要です
注意事項
- 購読ライセンスの期限を超えると、チャンネルを閲覧できません。購読ライセンスを新たにご購入ください
- 一度ご購入された購読ライセンスの返金はできません
これまでのご利用、誠にありがとうございました。
さらさらと海が波打つ音と、口の中の砂の不快な感触が、切れていたヴラドの意識をゆっくりと引き戻してゆく。それにつれ、身体の節々が感覚を取り戻してゆくかのように痛み始める。 「う…」 ヤシの葉から洩れる陽の光がまぶしい。起き上がれるだろうか。その前に、自分がなぜ今こうしているかをぼんやりと思い出してみる。 海賊と城で公爵に喧嘩を売って、逃げる途中であの長い髪の騎士の足止めをして、窓から飛び降りて…あの高さからよく助かったものだと、自分でも思った。その時、ふとあの騎士に言われた言葉が、全く歯が立たなかった剣戟とともによみがえる。 「虚ろな剣だ」 「師と呼べるものがなかったのではないか」 ヴラドは顔をしかめた。腹が立ったのは、それを否定できなかった自分にだ。あの言葉を言われた時、真っ先に思い浮かべたのは兄ルカの顔であったが、思い返せばかつて師と仰いでいた筈の兄は、確かに自分に剣を教えたことは一度もなかった。自分はその殺しざまをひたすらに真似るしかなかった。相手より早く、多く斬りつける方法を。兄もまた誰にも何も教えてもらうことなく生きてきたのだろう。その傑出した才能は、ついに誰にも拾い上げられることはなかった。遺されたのは兄の影を追い続けた自分だけ。 もっと強くならねばならない。兄の真似でなく、「自分の戦い方」とその「使い道」を手に入れなければならない。理由はまだ見つからないが、ヴラドは確信めいた思いを持ち始めていた。あの騎士のようなやつらが他にもいるだろうか。もっと戦いたい。もっと、もっと知りたい。戦いに勝って聞きださねばならない。あの時に獣人から兄に助けられた理由はなんだ?闘技場から出るとき、あの魔術師がこうまでして自分の命を繋ぎとめたのは何故だ?それは自分が強くなりさえすれば、全部この剣が聞きだしてくれる、わからないことは全部。そんな確信。 思いを巡らせていると、ヴラドはあることを思い出した。自分の腕はどうなった?捨て身の一撃を加えるためにくれてやった腕。 目をやると、当たり前だがやはり腕はなかった。そこで妙なことに気が付く。妙に切断面がまっすぐで、何より出血も、痛みさえほとんどなかった。止血すらしていないのに。加えて浜辺に打ち上げられたのならこんな砂浜から離れた木陰にいるだろうか?おもわず起き上がる。すると少し痛みが走った。よく見ると、見覚えのない紋様が傷口の周りに刻まれている。刺青ではないようだった。 辺りを見回すと、すこし離れたあたりに城で見かけた赤い生き物が丸くなってすやすやと寝息をたてているのを見つけた。近くで見るとネズミというよりは猫のような姿形だが、とんぼのような羽と白い角が生えている。 「一体なんなんだあいつは?よっ…と」 とりあえずその場で立ち上がってみる。骨は不満そうに軋むが、折れてはいない、どうやら動き回る分には大丈夫そうだ。 なくなった腕の方の肩をさすりながら、ヴラドは赤い生き物に近づいてみた。しゃがみこんで覗き込む。生き物はよく眠っていた。 頭を鷲掴みにして持ち上げてみるが、起きない。よだれを垂らし、眠ったまま微笑んでいる。じつに幸せそうだった。 ヴラドは少し考えてから、生き物を持ち上げて胴体からかじりついた。 「うぎゃあー!?」 生き物は実に人間らしい悲鳴を上げた。 「イタイ!!なんで!?待って!!食べないで!イタイ!助けたの!吾輩!助けたのに!あイッタイ!痛い!いぎぎぎ…」 噛み切れないし、不味い。それに助けがどうとか言っている。 しばらく咀嚼を試みたが、しぶしぶ解放した。勢いよく宙に舞い上がる奇怪な生き物。 「喋るし飛ぶし食えないネズミ…」 ヴラドのもらした漠然とした感想に、生き物は空中を浮遊し腰に手(前足?)を当て、憮然として反論した。 「失礼な!吾輩はカーエデール卿!きみを助けたの!大変だったんだから!落ちるきみが海に叩きつけられる前に空中に印を展開して受け止めて、水の舟をあみこんで、潮の流れをよそくして、海の上で傷口を塞いで…ここまでやっと運んで、せいこんつきはててたというのに!全く!向こう何年か分の魔力ちょぞうがなくなっちゃったんだからね」 「…ありがとう、ハエ?」 とりあえず礼は言う。命を救われたのだ、 「あ、いやあ、たいしたことないよ…えへへ」 なぜか生き物は頬を赤らめて照れている。話を聞くに、ただの動物ではないらしく、自分を助けるために全力を尽くしたことはヴラドにもわかった。理由はさっぱりわからないが。 「で、ここはどこだか知ってるか?」 「ずいぶん流されたからね、魔力の濃さからして皇国ではないし、吾輩たちの後ろの森のにおいからして多分だけど『お腹』の辺りじゃないかな。多分ここは森を抜けた先の海岸だとおもうよ。あとハエじゃないよ」 「ち、やっぱ全然わかんねえ…あいつ、無事かな」 「船長たちは無事だよ。君はそれよりその腕を治さなくちゃいけないよ。吾輩の印も長くはもたないしね」 「わかるのか」 「わかるよ。みてたもん」 「そうか…で、やばいのか、この腕」 赤い生き物は口に片手をあてて考え込むように話し始めた。 「ふつうのけがだったら止血してれば傷口は癒えるんだけど、きみの全身にある印はどれも欠けちゃいけないものだったんだ。何を封じてるかは知らないけれど、こんなにふくざつでみごとな印は今までに見たことがないよ。吾輩にはむずかしすぎて判断がつかないけれど、腕が無くなったことで印の均衡が崩れてる。吾輩の止血の印も方式の全くちがうのを上書きしたものだし、いずれ『きょぜつはんのう』が起きるとおもう。はやく博士に見てもらわないと痛い!!なんで!?」 赤い生き物は頭をさすっている。 「何言ってるか全然わからん、要はそのハカセってのが何とかしてくれるんだな?」 「うくく…そうだよ。この森を抜けてかなり南にくだらなきゃいけないけどね。本当は吾輩が飛んで案内できればいいんだけど、もうあんまり高くはとべないんだ…森に一人吾輩の知り合いがいるから、もしその人に会えれば森の抜け方がわかるかも知れないよ」 「そうか、じゃあまずそいつに会いに行こう」 「えっ」 「案内しろって。この辺のこたあ全く知らねえんだ、俺より方角くらいはつかめるんだろ?」 「そうだけど…それって吾輩が一緒に行ってもいいってこと?」 赤い生き物はおずおずと尋ねる。ヴラドは赤い生き物に背を向けて、身体の節々を伸ばしながら答えた。 「他に誰がいんだよ」 「…わーい!!やった!やった!!やったあ痛っ!!なんで?」 赤い生き物は頭をさすっている。 「うるせえからだよ。…腹減ったな。」 頭をぼりぼり掻き乍ら、青い海を見つめる。 まずは食料を調達せねばならない。ここはどうやら人の住んでいる場所ではないらしい。「あれ」は食えなかったし、狩りなんてしたことがない。ヴラドが覚えていかなくてはいけないことは、戦いのほかにもまだ山のようにある。 「あー…はぁ」 思わずため息が漏れた。 「どうしたの」 「なんでもねーよ」 当てもなく、彼は浜辺を歩き出した。 自分が見つけるべき答えを迎えに行くために。 おわり 【ほそくといいわけ】 改行とか文節をもっと学校で真面目に習っておくべきだった。 Fsrpg世界地図で言う「竜のへそ」の辺りに流れ着いたヴラドは…的な話です。 これから続き物にできたらなあと思ったり思わなかったり。最後の方ちょっと面倒くさくなって無理やり締めたのは内緒ですねん。あと投稿が自分ばっかりになっていくのがはずかしいしさみしいので誰かなんかかけ。俺の自尊心の為に!

(設定:どこかの帝国領の城から逃げる海賊団。海に面した崖に沿って建てられた背後は断崖絶壁の城。ヴラドは船長と殿をつとめていたが、時間稼ぎのために単独、ジルキオ率いる騎士団を迎え撃つ) 廊下の角を曲がると、全力で逃走する一団のなか、賊らしくない海賊団の中で唯一「悪党」然としていた白髪の青年がたった一人、曲刀のような異国の武器を抜いて立ち止っていた。その青年に対峙した追っ手たる騎士の一隊は相手が一人なのにもかかわらず、何故か思わず立ち止まってしまう。突然ひとり立ち止まっていた青年に意表を突かれたこともそうだが、青年が殺気か気迫か、形容しがたい「うねり」のような空気を発していたからだ。 「は、足止めにたった独りだけとは、無謀以下のもはや大馬鹿だな!見捨てられたか?あわれな下っ端め!」 兵士の一人が気を取り直し、挑発しながら槍を構える。青年は何も答えずにただゆっくりと腰を落とし、武器を逆手に持ち替えた。 「この・・・!」 兵士が動こうとした時、隊を率いていた騎士がそれを制した。 「あれの相手は私がする、手出しは無用。お前たちは行きなさい。あのような者どもは決して逃がしてはならない」 「まさかあのような下手人の挑発に乗るおつもりですか!?」 騎士は何も答えず、ただ視線の先にいる青年を見据えている。 「…わかりました。おい!行くぞ」 兵士は隊列に命令し、青年の脇を走り抜けていった。全員一切青年に手を出さなかったが、青年も兵士らを止めるそぶりを全く見せなかった。青年にとって、向こうが決闘の形式をとったことは僥倖であり、それに従うのが最善の選択でもあった。 ゆっくりと、しかし確実に騎士は青年へのほうへと歩を進め始める。どうやら青年の発する「うねり」はこの騎士には殆ど通用していなかったらしい。むしろ迎え撃つ青年の方が表情が険しくなってきている。騎士は腰に差していた二本の剣のうち一本を抜いた。美しい曲線を持つ柄の上質なレイピアだ。 騎士は精悍で整った、劇役者の二枚目のような流麗な顔立ちをしており、それを引き立てるように長くのばした黒髪はまるで物語の中の人物の様であった。ともすれば王の風格さえ持ち合わせているかのように見える。それに対峙している青年は、ぼさぼさの白髪を半分に刈り上げ、服もろくに着ておらず、全身には刺青。極めつけに黒い首輪まではめている。もはやそのいでたちは王の前に引き出された奴隷に等しかった。 先に動いたのは青年だった。全速力で騎士に突進し、直前で地面を蹴り騎士の顔面に向かって躍りかかる。 騎士はその場でほとんど動かずに、腰と腕の動きだけで淡々と青年の攻撃、二回の蹴りと三回の斬撃をいなした。 そして青年の隙をまるで決められていた動作をこなすかのように生み出し、青年のみぞおちに向かって的確にレイピアの柄をめりこませた。 普通の兵士なら悶絶するであろう一撃だったが、青年も素人ではない。痛みをいったん無視してすぐさまレイピアの切っ先の届く範囲の外へと飛びのいてから、改めてやって来る痛みをやり過ごす。まさか一撃も入らないとは予想もしていなかった。 「ぐう…」 青年は騎士と初めて会いまみえてからその力量の高さをびりびりと感じていたが、今の剣戟でそれを確信に変えていた。 格が、違う。理由はわからないが、手加減さえされているだろう。青年は自分がすべきは時間稼ぎであって勝つことではないのは十分にわかっていたが、出会ったことのない程の大きな力量差と意図のつかめない手加減、加えて涼しげな騎士の冷徹な視線に青年は苛立っていた。 「俺は上から見下ろされるのが嫌いなんだよ」 青年はしゃにむに飛びかかる。が、結果は同じ。 今度は真正面から頬に拳を叩きこまれ、もんどりうって倒れ伏した。 「何度やっても同じですよ?しかし、悪くない動きですね。それに異様なくらい殴られることに慣れている。独特の受け流し方だ」 騎士は視線を落とし白い手袋をはめた手の甲に染みた血を見ながら言う。 「そりゃどうも…げほっごほっ」 青年は切った口の中の血を勢いよく吐き出して答えた。 「殴られたダメージはさほどではないのでは?戦闘の経験で言えばおそらく私よりあなたの方がすこし上なのでしょうね。しかし、あなたには師と呼べるものがいなかったのではないですか」 「…なぜわかる」 「何故って、殆ど貴方の剣には守る動作がありませんよ。噛みつくだけなら犬でも知っていますが、守りと反撃の完成は独学できるものではない。型ですからね。貴方の剣はただ相手より早く、あるいは多く斬りつけようとするのみで、勝利の先にあるものへの欲求がない。勝って、生き残りたいという本来あるべき原理が存在しない。あるのは死への早すぎる道のりだけ。相手の、いやその死は自分にさえ向けられている。命を、試している。かつての奴隷仲間の真似でもしているのですか」 「グダグダとうんちく垂れてんなよカマ野郎。俺が誰の真似をしてるって?」 再び青年は騎士に突進するが、落ちる木の葉を叩こうとするが如く躱され、蚊を叩くが如く脇腹を剣の峰でしたたかに打ち据えられた。 先ほど殴られた二か所のようにごまかす余裕をあたえない、骨の軋むような一撃。 呻き声を上げながら後ずさる青年。ここまでか。青年は覚悟を決めかけていた。かすんで揺らぐ視界。口の中は血の味で一杯だ。もう力量差なんてどうでもいい。あとどれだけ長く立っていられるか…と考え始めた時、青年は「それ」を見た。 廊下に並ぶ大きなステンドグラスの窓枠のひとつに、赤いねずみだろうか、丸っこくてちいさな生き物が見える。見間違いだろうか?いや「それ」は間違いなくこちらを見ている。小さく震えながらおびえた目で二人の男の行く末を見守っている。ずっと後になっても本当に何故だかわからなかったが、青年はその時、自分の視界がすうっと晴れていくような感覚を覚えたという。自分がいま、すべき事。求めるものがわかったという。 「…要するにひとつ確かなことは、あなたの剣には我がまるでない、ということ。そのように空虚な牙では私には届くはずもない。如何せん軽すぎる。さて、うんちくはこれで終わりにしますよ。次は斬ります。残念ですが逃がしもしません」 膝をついている青年につかつかと歩み寄り始めながら、騎士は自分に驚いていた。たかが賊一匹に何故自分は講釈など垂れているのか。脱走奴隷を育ててどうする?地べたを這いずり回る凶暴な子供に自分と通ずるものでも感じたか。意味なんてないはずだろう。なによりもう殺してしまうのだから。 「くくく…なんでもかんでも見透かしてくれやがる」 青年は笑っている。血反吐にまみれた歯をむき出しにして。 「お前、犬に噛みつかれたことあんのかよ?」 騎士が最後まで聞き取る前に、青年はまた愚直に突進し仕掛けてきた。なにかが変わった様子もない。が、問題はそのあとだ。 先ほどと同じように、青年の見え透いた攻撃をいなそうと剣を動かした瞬間、そこにあったのは傷だらけの曲刀ではなく、青年の二の腕であった。短いフェイントを挟み、刀身に直接腕をぶつけて来たのである。これは騎士の予想外であったがもう遅い。肘を高く上げ、V字に曲げた腕の肘から上の部分と手首にみるみる刃が食い込み出血がはじまる。筋肉と骨に挟まれた剣は一瞬だが狼狽えた騎士の動きを阻害した。 青年は刃が食い込んだままの腕を捩って騎士の足を踏みつけて肉薄し、騎士の額に自分の額を押し当てて言った。 「噛みついてやるよ、騎士殿」 青年が思いきり千切れかけた腕を振るい、ついに騎士から剣を引きはがした。腕を犠牲にした代償にこじ開けた隙を逃さず、残った方の腕で騎士の顔に渾身の拳を見舞った。宙を舞った剣は高い音を立てて石の床に突き立つ。騎士が膝をついた瞬間、青年は踵を返して走り出し、ステンドグラスの大きな窓を突き破って遥か下の海に飛び込んだ。 ―そのしばらくのち、騎士は何も言わずに立ち上がり、剣を拾い上げて鞘に戻す。 「つっ…ふふ」 口元の血を拭うと、思わず笑みがこぼれた。顔を思いきり殴られたのは一体どれくらい振りだろうか。 「逃してしまったな。これは重大な失態だぞ、騎士殿?」 振り返ると、そこに笑みをたたえながら立っていたのは君主であるマシュー公であった。腕を組み、壁にもたれかかっている。 「…いつから見ておられたのですか殿下。恥ずかしながら後れを取りました。処罰は如何様にもお受けいたします」 「おや本当か。遊んでいたのではないのか?お前ほどの剣士があのような雑魚に手こずるとは思えんが…それに、最後に至ってはお前、わざと拳を受けたろう?」 「滅相もございません。殿下、まだ賊が潜んでいるやもしれません。早く奥へお戻りください」 「わかったわかった。それよりも早く冷やしておけよ?二枚目が台無しになるぞ。ははは」 マシュー公は両手を上げて、笑いながら立ち去った。 「やれやれ」 騎士は溜息をつき、破れた窓を見やる。生きていればいつかまた剣を交えることになるかもしれないと、騎士ジルキオは最後にもう一度うっすらと微笑んだ。 おわり あとがき 段落?何それ知らん キャラクター勝手にしゃべらせてすみません。(相変わらずジルキオの勝手なイメージが暴走してます) 剣術やその他うんちくは完全に雰囲気と思い付きで書いておりますゆえ中の人やお詳しい方は鼻で笑っておいてください。おこらんといて
時は夜更け。降り出していた雨はいつの間にか勢いを増して大雨になっており、ざあざあと降り続けている。 …ここはとある国の市街の大通り。時間帯と降りしきる大雨のせいでひと気は全くないが、ふだんは大変な賑わいを見せる活気ある街である。住民の大半を占めるのは、およそ中流下流に位置する民衆。すなわち商人や工員、農夫たちである。その「民草たち」が毎夜ぎゅうぎゅうに集まっては安酒をやけくそにあおる、大きな古酒場があった。 嵐のようないつもの喧騒もようやく終わりをつげ、歌も注文のがなり声ももう聞こえない。外の大雨と今にも轟音とともに稲光を落としてきそうな雷雲の唸り、ジョッキを握ったままに酔い潰れカウンターに突っ伏した貧乏農夫の大いびきと、暖炉のぱちぱちとはぜる音、ひとり店に残った店主とみられる女のせっせとグラスと食器を片付ける音だけが響いている。 その酒場の真上に当たる二階には、八畳ほどで木造りの、二つのいすと小さなテーブル、かび臭いダブルベッドが一つ。あとは箪笥がひとつという古びた部屋があった。 そこに宿を取っていたのは、後ろに結わえた真っ白な長髪と顔の右半分の刺青が目を引く、二十代半ばほどの目つきの悪いが精悍な青年と、まだあどけなさの残る十四、五歳ほどの赤毛の少女。刺青の青年は窓際に置いた椅子に腰掛け、くわえた煙草から紫煙をくゆらせながら、窓の向こうの暗闇をじっと見つめている。窓枠は大粒の雨に打たれ頼りなくがたがたと音を立てて震えていた。少女はすでにベッドで眠りに落ちていた。 青年はしばらく窓のそばで座っていたが、ふと顔をしかめると小さく舌打ちをした。 「ち、撒ききれてねーな…昼前に片付けたハズなんだがな」 気配がする、三人。夜の暗闇と雨音に紛れて這い回る気配を、青年は深いため息とともに煙を吐き出しながら、容易く感じとっていた。 「三匹か。そろそろ来るなこりゃあ。この雨ン中ご苦労なこった…げほっむほっ!おええ!ぐぬぬ、火葬場の煙でもこんなまずかねーぞあの野郎」 青年は苦虫を噛み潰したような顔をして、まだ慣れない煙草を握りつぶしてうしろへ放った。 「あ、途中ですてちゃだめだよ。博士におこられるよお?」 いつの間にか目を覚ましていた少女、いや、少女が寝ていた場所には白い角をはやした緋色の小さな猫のような妖精がいた。しかし猫と違って体毛はなく、大きさは先ほどまでいたはずの少女の頭ほどしかなかった。背中には薄い青色で半透明の羽が生えており、細長い尻尾をゆらゆらと揺らしている。 「ヴラド君のたましいを『ひきとめる』けむりなんだよ。それに、すごくいいにおいじゃない」 青年が妖精の方を振り向いた。全く驚くそぶりも見せない。 「うるせーな。起きたのか、丁度良かった。んなことよりすぐにお客さんが来るぜ。見たところ本職の方々だ。お前にはまだちょっとキツそうだな。終わるまでベッドの下にでも入ってじっとしてろ」 「え、でも昼間は森でどろぼうのおじさんやっつけたよ!」 「はあ、あんな雑魚と一緒にすんな!あいつ火掻き棒しか持ってなかったじゃねえか。まあ今回は見学がてら温存しとけ」 「はぁい。でも床からじゃ何にも見えないよ~、にしてもすごい雨だね!」 妖精はひとつ寝返りを打つとそのままストンと床に落ちて、ころころとベッドの下へ転がって行った。 「うえ!ほこりまみれだよ!クモの死体にねずみのふんもある!げええ~」 2人は追われている。それもずいぶんと長い間。もう三年近くになるだろうか。とうの昔に追われる理由はなくなってしまった筈だったが、青年は忘れられるには如何せん恨みを買いすぎていたし、少女(今は妖精だが)にも追われるべき「途方もない価値」があった。どれほど遠く離れていようとどこからともなく追手たちが現れ、その度に男が追手を手痛く撃退してきた。 つと稲光が輝き、雷鳴が轟く。雷光に照らされたゆらめく影を青年は見逃さない。 賊はどうやら早くも位置に着いたようだ。向かい側の建物の屋根に一人、窓の直線状にいる。おそらくは射手。加えて酒場の入り口に一人。そしてこの酒場の屋根にも一人。 青年は焦るそぶりもなく、足元に立てかけた、鞘に納まった幅広の曲刀のような武器を手に取って立ち上がり、窓の脇の壁にもたれかかった。 「ふう…」 深く息を吸い、ゆっくりと鞘からナイフを外してゆく。二度目の呼吸をし終わる前に、再び雷鳴が轟く。同時に窓ガラスが割れた。射手に放たれた矢弾が窓ガラスを突き破ったのだ。 矢はベッドとカモフラージュの為に丸めた毛布に深々と突き刺さり、さらにその下にいる妖精の頭をかすめた。 「どわあ!?」 続けてこの建物の屋根にいた一人が飛び降りて、割れた窓から器用に身を捻って侵入してきた。が、そこへ間髪入れず身を潜めていた青年が組み付き、三度の膝蹴りを敵の腹にめり込ませる。ひゅっ、という掠れた呻き声とともにうずくまった敵の腕と胸の辺りをつかみ、そのまま割れた窓をさらに破壊しながら外れた窓枠ごと投げ飛ばした。 「っし、あと二人」 土砂降りの雨が部屋になだれ込みはじめ、流れ込んで来た外の音でにわかに部屋の中が騒がしくなる。 豪雨と雷鳴に紛れ、酒場の人間に気付かれることなく侵入してきたのであろう二人目が部屋に躍り込んで来た。先ほどの敵もそうだったが、全身を黒装束で包んでいる。 「とうとう雇われまで使いだしやがったか。ウンザリだな。確かに退屈はしねえけどな?お前らもうちょっと場所と時間を考えろよ」 話しながら青年はベッドの枠につま先をかけている。 「…笑止」 敵は手に持っていた抜き身の長い倭刀を八相に構えた。 「そうかよ」 次の瞬間、青年は一気にベッドをつま先で蹴りあげた。もんどりうって目の前に倒れこんで来たベッドを敵はすばやくかつまっぷたつに叩き割ったが、割れたベッドの影から現れた青年の影まで捉えることは出来なかった。胸とみぞおちに拳を叩きこまれ、あばら骨が折れる音が聞こえる。 「くぉっ…」 かすむ視界にでたらめに刀を振ろうとしたが、後ろに回り込んだ青年に容赦なく蹴倒され、頭を鷲掴みにされて床にしこたま打ちつけられたあと、そのまま一人目と同じように窓から投げ捨てられた。 「今の死んでないよね?まったく、どうやったらあのベッドがけり上がるんだろ…」 いつの間にか角の箪笥の上に避難していた妖精がたずねる。 「ああ、いたんだっけなお前!ケガねえか?悪い悪い。まあ大丈夫だろ、あのくらいで死ぬようには見えねえし。窓の下見てみな、とっくにいねえと思うぜ?」 「もうひとりは?」 「とっくに逃げたろ。気配も消えた。いやあ今度のは大したことなかったなあ」 「傷一つないもんね。吾輩は死にかけたけど」 妖精はふわりと浮いて、窓枠だったであろう場所に着地した。 「つめたっ!…あらほんとだいない」 「だろ?…じゃ、とっととばっくれようぜ。こんなとこでおちおち寝られねえよ、明日には騒ぎになる」 「えー」 翌朝、竜巻が来たような水浸しで悲惨な状態の部屋と、酒場の前に散らばった血糊にまみれた窓枠の残骸が、その街のちょっとしたニュースになったのは言うまでもない。 2人は追われている。それもずいぶんと長い間… おわり ・・・いつもの恥ずかしい言い訳 (集中力が切れてしまって途中からずいぶんと乱文雑文になってしまいました。雰囲気だけお楽しみください。雰囲気だけ!)
その日は、百年に一度と言われる嵐が島全体を包んでいた。 豪雨と暴風が、木々をなぎ倒し、そこかしこに暮らす生物の生命を脅かす。まだ日中であるにも関わらず、深夜のように闇に包まれた空に時折猛烈な雷光、即座にバリバリと音を鳴らし天地にヒビ。天から落ちたのか、はたまた地上から生えたのかわからない、恐ろしい数の稲妻が走る。 「素晴らしい!!今日をおいて他にこれほど最高の日和はないである!!」 天地を揺るがすかのような騒音に歓喜の声を上げたのは、この島にある科学班の博士・ツバキであった。帝国領の付近に浮かぶ島(とはいえ、どこの領地にも属さない無人島である)に、科学班はある。元々どの種族も暮らしていない緑豊かな無人島であったが、俗世から離れ実験に没頭するためだろうか、博士はここを本拠地として日夜怪しげな実験を行っている。他の国々や、種族達には到底作ることは不可能であろう機器が研究所に所せましと設置されている。博士の科学力や技術は外界と同じ時間が流れているとは思えないほどだ。その力を我が物にしたいと要求する国は後を絶たない。 「雷からのエネルギーは本日予定している強化実験へ有効に利用できるかと思われます。現在エネルギー質量および充填量を計算中…」 涼やかに話す女性の声…恐ろしく透明度のあるその声の主は、試作4号“D”。しなやかに指先を動かし、空中に浮かぶ透過した画面を見つめ何らかの計算をする。腰まであるサラリとした銀の髪、鼻筋の通った整った顔…、海面に緑のインクを少し垂らした雫をそのまま閉じ込めたような瞳は、まばたきすらしない…彼女は博士に作られた人造人間だ。 美しい肢体の色は銀色に光り、雷光の度にキラリと照り返す。彼女がはじき出した数値をみて満足そうに博士は頷いた。 「うむ、何もかも予定通り!吾輩の予想が的中したであるな」 眼鏡を押し上げニカッと、さも嬉しそうにギザギザの歯を見せて笑う博士に、少しばかりため息をついて残念な表情を浮かべてみせる、もう一人の人物…-。 「ええ、賭けは吾輩の負けのようです。さすがはツバキ博士」 ボサボサと伸ばしっぱなしになった朱色の長髪が印象的な彼は、ツバキ博士の助手・マガトキであった。ひょろりとした長身に長く伸びた手足。切れ長の瞳は金色に光り、厚みの薄い唇には普段から微笑をたたえているせいか、先ほどの曇った表情もすぐに消えていた。彼には少し特徴のある箇所がある。耳の部分には蜻蛉の羽のようなものが3対生え、額には角が1対。異形の者特有の風体であったが、以前はそこらにいる人間たちと何ら変わりのない好青年の姿だった。科学班に入り、人体実験を幾度か自身にも施した結果現れた症状だという。 「そうであろう、フフフ、さあ、今日こそは件の実験、成功させてみせるである!!!」 ツバキ博士は興奮ぎみに目を見開き、豪雨で荒れ狂う外からの音さえかき消すほどに大声で叫んだ。 生物実験は毎日のように行っている。被験者の強化、合成、…材料となる生物は比較的たやすく準備できる。奴隷の売買が日常的に行われているのだ。場合によっては国家の兵士強化をと、進んで提供してくれる某国もある。 しかしこの日生物実験する対象は、少しそれらとは違った。 科学班で細胞から作られ、大きく成長した人造の獣。獣とはいえ、知能も高く筋力はケタ違いに強い。獅子のような姿に額からは水牛のごとく巨大な角が生えている。全身は、赤褐色の体毛で覆われ、見るものを圧倒させる巨体であった。名前はカーエデール。博士は敬意をこめてその獣を『卿』と呼んでいた。 「博士」 重低音でボソリとつぶやく。実験を行うため、ベッドに横たえられた獣は目を細め博士を呼ぶ。 「…卿、大丈夫である。これからさらに卿を強く、そして希望通り翼を授ける準備は万端である。吾輩に任せるである」 ゆっくりカーエデールの額を撫でて笑う博士に、獣は嬉しそうに鼻をフフンと鳴らした。そして真似るように博士の髪を撫で、彼の言葉に安心したように瞼を閉じ、深く息をした。 マガトキは様子を見ながらカーエデールの肩付近から麻酔効果のある薬剤を打つ。 「科学班のためにこの身体、捧げる所存。信じていますよ、ツバキ博士」 それだけ言うと、静かに眠りについた。 「脈拍正常、血圧は通常よりやや低めです」 Dが淡々とカーエデールの状況を説明しながら、記録していく。まったく無駄のないその動きはさすが人造人間といったところだろうか。ツバキとマガトキは目を合わせ、術式用の手袋をパチンとはじいた。実験開始の合図だ。 背部に“翼”になるだろう小さい羽根とピンク色の肉塊をねじ込む。縫合しながらDからの情報を聞く。その後、今度は横腹から少し刃を入れ、皮下をめくる。脈動する臓器に新たな生体装置を取り付け、縫合。 何もかも順調に進んでいた。 ――最後の仕上げをする、その瞬間までは。 「さあ、総仕上げである。エネルギーの準備は?」 「すべて完了しています。」 「よし、マガトキ。解放装置を」 「エネルギー解放。カーエデールに注入します」 瞬間。 強烈な光が研究所内を包んだ。 否、光だけではなかった。轟音と共に青白い閃光は研究所の装置すべてを起動停止にさせ、カーエデールと助手であるマガトキを貫いてしまった。 「卿!!」 博士は叫んだ。閃光のせいで眩暈がする。耳も先ほどまでの豪雨で騒がしかったのに突然の轟音の後、無音のようになった。自分自身の叫びも、体内の底で響くだけに思えた。 じわりじわりと耳鳴りが起こり、通常の音になるまで時間がかかった。 「卿!!」 博士はもう一度叫ぶ。今度は声が聞こえる。長いまつげをぐむと瞑り、目が慣れるのを促す。必死で目を凝らすと、傍らに倒れるDの姿があった。 Dは、ほかの装置同様、強烈な閃光の後自力で動くことができなくなっていた。衝撃で記憶装置にも支障をきたしたのかもしれない。エラー音を鳴らしながら、博士に訴えている。歯をギリっと食いしばり、彼女の電源を落とす。 「少し待っているである…」 博士は三色に分かれた自髪をガシガシと掻いて、苛立つ様子を見せた。部屋の最奥部でバチ、バチと装置が鳴り、その奥から焦げたようなにおいが漂ってきた。 ソレは、黒鉄色をした咆哮する獅子の彫像。 ――いや、彫像ではなかった。 絶句しながらも、心のどこかであまりの美しい形状に歓声をあげたくなる。それほどに、その黒鉄色のソレは、獣そのものの姿をしていた。しがみつくようにする人型も、そこにあった。 「卿…」 博士はそっと手を伸ばした。指先が、一瞬触れる。 途端に、黒鉄色の彫像はボロボロと崩れ、砂山のように足場に積もる。あわててかき集めるけれど、握りしめるとただ手のひらを黒く汚すだけで、何もつかむことは出来なかった。 すべてが灰になった。 それを認識したのか、自嘲するように狂気じみた笑いを浮かべた。すべて失ったのだ。 嵐はまだ止んでいない。騒音の中、徐々に落ち着きを取り戻した博士は、ふと灰の山に何かがあることに気付いた。 (――また崩れてしまう) 一瞬躊躇して、手を引っこめる。すると、もそりと山がうごめいた。 別室の実験動物がまぎれたのだろうか。 さらにもそりもそりとうごめき、灰の山から赤いものが見えた。 「…手?」 驚きながらも急いで灰をどける。そこには全身が緋色のつるりとした肌に、頭に1対の角をもつ、小さな生物が丸まっていた。 その姿は胎児に似ていた。 よく見ると背中に薄い羽根をもち、長い尾のある猫のような生物だ。 「卿?まさかカーエデール卿なのであるか?」 博士がそういうと、丸まっていた生物は起き上がり、ぼんやりとした糸目で見返した。 「…吾輩…、よくおぼえてないけど、ツバキ博士のことはわかるよ」 にこりとして微笑むその顔は獣ともまた別の誰かにも似ていたが、博士にはそれが誰だったのが思い出せない様子だった――― 「…これが、あの日起きたことですよ」 口元に微笑をたたえながら、ゆっくり話し終えると彼はツバキ博士に視線を合わせた。 「…では…、その、君が助手の」 「ご無沙汰しております、博士。嗚呼…やっと再会を果たすことができました」 博士は目をぱちくりさせてもう一度、“助手”と名乗る男の姿を頭からじっくりと見回す。 ――やはり覚えがない。たしかにあの日、雷の暴走で閃光を浴びた記憶はあるが… 「いや、待つである。その話だと獣であった卿と助手は消し炭になったのであろう?なぜ…その…、君は」 「今は新月卿と名乗っております」 「あ、ああ、そうであった。なぜ何のケガもなく…生きた姿をしているのである?」 博士の問いに少し落胆した様子を見せる男…新月卿であったが、すぐにまた微笑を浮かべた。スッ…と眼差しを外に向け、静かなる闇夜を見つめる。 「貴方は吾輩に吸収する力を授けてくれた。吾輩は閃光が起きた瞬間、衝撃でカーエデールの身体にしがみつく形となったのです。閃光は吾輩たちを包み、焼き焦がしていった…その時、吾輩の一部がカーエデールと一体化し、今のカーエデール卿が生まれた。彼のものが日々過ごすにつれて、生み出す細胞を吾輩が少しずつ吸収し、吾輩は体内でひそかに再生を目論んでいました。 貴方も知っているでしょう。あの子は月の光で生命力を維持していることを。月が欠けるにつれ、あの子は徐々に眠りにつく時間が増える。そして、今宵のような新月の日…吾輩は新月の日のみ現れることができるようになったのです」 静かに、淡々と話す彼の横顔は夜空をぼんやりと見つめ、少し恍惚とした表情をみせていた。外からは涼やかな風が木々の葉を擦る音が聞こえる。 「そうであるか。…うむ。よくぞ戻ってきたであるな」 「ええ、まだ賭けの配当をいただいていませんから」 新月卿はそういうと、博士ににじり寄った。博士はギクリとして椅子から転げ、そのまま壁際まで追いやられてしまう。 「な、…ま、まて!その賭けは吾輩が勝ったのであろう?!」 息がかかるほどに近距離まで詰め寄られ、視線をあちこちに反らせて逃げ場を探す博士の姿にうっとりとしながら、新月卿は両手を壁に這わせて動きを封じる。 「いえ、残念ながら吾輩が勝たせていただきました」 唇が触れるか触れないかの距離で、さらに続けた。 「貴方はこう、言いました。『今日こそ記憶に残る偉業を吾輩が成すのである!どうだ、賭けてみるか、マガトキ』」 新月卿はそうつぶやくと口元に微笑を浮かべた。博士はただ、目を泳がせることしかできなかった。
追憶1 ~おまじない~ 「あらまあ。そんな顔して帰って来るなんて、また学院でからかわれたのね。」 俯き加減の少年は太陽の翳りを背中に感じつつ、とぼとぼと覚束ない足取りで家路へと歩を進めていた。 ハンドメイドの素朴な装飾の施された木の門扉に手を掛けた時、声を掛けられ足を止める。 ささやかながらも可憐な花で彩られた中庭からだった。 「あなたは男の子なんだからもっとしっかりなさい、そんなんじゃ将来好きな子ができた時に笑われちゃうわよ。」 その声音には、呆れながらも幼い我が子に向けられた慈愛に満ちた温かみがこもっている。 少年は眉尻を下げた頼りなげな表情のまま、ゆっくりと顔を上げて母を見つめる。 少年の名はオルキャットと言った。 淡い水色がかった銀髪に、光を受けると琥珀がかった輝きを放つ不思議な茶色い瞳をしていた。 今はその子供特有の大きな瞳はうっすら潤んでいる。 彼の母はエルフらしくほっそりとした長身の女性だった。長く豊かな髪を頭の後ろでゆったりとした三つ編みでひとまとめにしていた。 彼女はそんな我が子の様子に苦笑しつつ、膝を折り、ぼんやりと立ち尽くした息子と目線を合わせる。 額に手を伸ばし、髪を優しく梳いてやる。 少年は黙ったまま、されるがままになっていた。 彼女には少年の浮かない表情の理由について、察しがついているようだった。 「また、クラスメイトの子に”人間”が突然街に現れて子供を攫う、なんて脅かされたんでしょう?」 それまで沈黙を守っていた少年が「その」言葉を聞いた途端、はっと強張った表情で見つめ返す。 「そんな作り話を信じてどうするの? あなたがあまりに怖がるものだから、みんな面白がってしまうのだわ」 諭すように続ける母の言葉を遮り、少年は悲痛な叫びを上げた。 「そんなことない!だって現に父さんは王様の命令で”境界”の外へ見張りに行っているじゃないかっ!! 僕知ってるんだから!」 「オルキャット・・」 「母さん誤魔化さないで!父さんは今じゃ島にいる時間より外にいる時間の方が長いじゃないっ みんなそう言ってる。そう言ってるんだよ!」 「オルキャットやめてちょうだい・・」 言いようもなく募る不安を激情と共に吐き出した少年は、最後の母の苦しげな声で俄かに我に返る。 彼は少年たちの中でも取り立てて何かに優れた素質を未だ見せてはいなかったが、 9歳という幼い年齢の割には他者を思いやる心を生来持ち合わせている方だった。 「あ・・ごめんなさい、母さん・・ ・・僕ひどいこと言っちゃった・・」 痛みに耐えるような表情と共に、瞼を閉じてしまった母の肩はかすかに震えていた。 少年は思い出す。 夕暮れ時、まだ床に届かない脚をぶらぶらさせながらテーブルについて、 母が夕餉の準備をしている様子を眺めていた時のことを。 母の背中は、父が居ない時いつも淋しそうだったのだ。 2人分の食器に特製のシチューをよそい、テーブルの方へ振り返ったときには いつもの柔らかい笑顔がそこには常にあったのだけれども。 少年は頼りにしている母の肩が、思っていたよりもずっと華奢で 自分の前では気丈に振舞っているのだとおぼろげ乍ら気づいてしまった。 胸が痛かった。 母の肩に触れてぎゅっと指に力を籠める。 「ごめん、母さん 父さんはきっともうすぐ帰って来るところなんだよね」 母は息子を抱き寄せると、額をこつんと合わせた。 「そうね。お父さんは帰って来るわよ。私も早く会いたいわ。 オルキャットもそうでしょう?」 「うん 父さんに会いたい。」 母は目を細めて柔らかく微笑んだ。 「じゃあ、早く帰ってくるおまじないしようか」 「うん!」 少年の幼い顔にようやく子供らしい笑みが浮かんだ。 「お母さんがおまじないをかけてあげる。 いいって言うまで動かずにじっとしてるのよ?オルキャット。」 「はーい!」 「ふふっ」 少年は母のかけてくれる”魔法”の力を受け止めようとするかのように そっと瞼を閉じた。 母は素直な息子の様子に破顔しつつ、息子の前髪の一房を白いほっそりした指で器用に編み込んでいく。 「おしまいよ。もう目を開けてもいいわ」 少年はそれを聞くと、一度パチクリと瞬きをしてから大きな目を開いた。 自身の前髪に施された細い三つ編みに手を触れる。 中庭にある小さな泉まで小走りで駆け寄り、水面を覗き込む。 様子を眺めていた母は、振り返った少年のはにかんだ笑顔につられて笑みを深める。 「母さん!これすごくかっこいい!!」 「お父さんが帰って来るまで毎日編み込んであげる」 「わーい!やったぁ!!ありがとう! 父さんにも早く見せてあげたいなぁ!かっこいいって言ってくれるよね!」 「ふふ。 さあ、もう日も暮れてしまうから中に入りましょう? オルキャットの好きなウサギ肉のシチューができているわ。 今日は学院でどんなことを習ったのかお母さんに聞かせてちょうだい」 「うん!あのね・・」 親子は夕日を背に、手を繋いで木の扉を開いて小さな我が家へと入って行った。 これが在りし日の母との思い出だと、後年のオルキャットは妻に語った。 三つ編みを編むとき、自分は目を閉じているふりをして、母の白い指が優しく髪に触れるのを見ていたのだとも。 妻は「いくつになってもあなたは変わらないわね」と言いながら、 口振りとは裏腹に優しいしぐさで夫の三つ編みに触れた。 その表情は窓からそそぐ朝の光のまばゆさで判然とはしなかったが、 柔らかいものだとオルキャットには分かった。 ~あとがき~ 三つ編みの由来 →母が怖がりだった幼いオルキャットに「お父さんが早く自分たちのところに戻って来られるおまじない」と言って 編んでくれたのが始まり。 母はオルキャ10歳の時に流行り病で亡くなる(入手が難しい薬草さえ手に入れば特効薬が作れるはずだったが、父は 王命を帯びて遠隔地へ任務に赴いていたため、伝書鳩による伝言を受け、戻ろうとするも間に合わず) 以後は、母を偲んで毎朝自ら編み込んでいる。
――闘技場でヴラドを待っていたのは、割れんばかりの歓声と茹だるほどの熱気、そして通常の試合ではありえない数の「対戦相手たち」だった。土埃の舞う地面には、少なくとも百人近くの敵がすでに各々の得物を抜いて立っており、ヴラドへあらん限りの殺気を投げかけていた。うんざりして上を見上げると、青空が妙に近くに見えた。陽の光に目を細める。 この残虐な舞台は全て、ヴラドの飼い主であり稀代の大商人、ラガルト=ホーキンスが用意したものである。ヴラドの「兄弟たち」を、皆殺しにして。 ラガルトは特等の貴賓席に招待された飢えた好き者の諸国貴族や富豪らの前に立ち、まるまると実った葡萄をひとつ、つまみあげて言った。 「仲間をひとり残らず食べられてひとりぼっちになったかわいそうな灰色オオカミは、これから自分で積み上げる死体の山の上でその血に溺れながら死ぬでしょう。来賓の皆様方に謎かけです。死体の山の死体の数は幾つかな?」 ぽいと口に頬張った葡萄を咀嚼しながら、ラガルトは手を打つ。 運び込まれていた大きな銀の杯に、ラガルトは足元にあった金貨の詰まった袋を投げ入れた。どしゃん、と派手な音を立てて杯が揺れる。 「さてさて皆様方、果たして奴が何人殺れるか、賭けをなさいませんか。ええ、ええ。皆さまが怪訝に思われるお気持ちは重々承知しております、この只ならぬ人数差は馬鹿馬鹿しく思えるでしょうが、それは皆様方があまりやつのことを存じ上げぬがゆえにございます。やつはあまり表舞台へは上がっていないだけで、私の集めた闘犬の中でも最強の手練れなのです!…私がかつて愛した「金色の蛇」を凌ぐほどにね。並の雑魚では到底かないません」 ラガルトはわざとらしいため息をつく。 「ですが私の悪い癖がここにも出てきてね。少々飽きが来てしまったのですよ。悲しいかないつの世でも、人の時代は変わらなくてはならないのです。しかしただ処分するのは勿体無くて。そこでこの刺激的なイベントを思いついたのです。はたから見ればただの私刑でしかありませんが…くく、あの犬はそう簡単には死にませんよ!さあさあ、懐をもっと重くして帰りませんか!ともあれ皆様方、この素晴らしい舞台をともに楽しめることは、私の無上の幸せに御座います!どうか、血沸き肉躍る戦いをお楽しみください!」 貴族らに歓声と笑い声が沸き起こる。杯が金貨であふれるまで、そう時間はかからないだろう。 ラガルトはくるりと振り返り、高く通る声を張り上げた。すかさず彼に付いていた下女がひざまずき何かを小さく呟くと、彼の高く通る声はさらに増幅され客席の隅々にまで響きわたった。 『【闘士ヴラドの首を掲げた者に、莫大な賞金を、自由な身分を、最高の栄誉を】』 これが剣奴たちに布告された試合の勝者への褒美である。 富への欲望、栄誉への熱望。自由への渇望。様々な望みをかけた者たちが、この舞台に押し寄せてきていた。歴戦の剣奴から痩せこけた亡国の農夫までもが。 最高の舞台が用意できたはずだった。しかし、当のヴラドがあまりに冷静に見えるのが気に喰わない。捨て鉢を犯すのは趣味ではなかった。 気に喰わないが、あいつがただ殺されることもないだろう。遥か下にいるウラドを睨め付け、ローブを大げさに翻し背を向け、自身も席に着く。 「まあいい。始めろ」 ウラドは処刑開始の合図をただ待っていた。構えもしない。表情もさして変わらない。 ラガルトの所有する軍団が「金色の蛇」と手下の剣奴、果ては取り巻きのチンピラまで皆殺しにしたのも、ヴラド一人を殺さずに残したのも、全て「飼い主」の指図であることをヴラドは薄々と理解はしていた。だが理由がわからなかった。自分たちが何をした?期待に応えるべく命がけで戦い、血を流し、飼い主たちに富をもたらした。なのになぜ。残り勝てる見込みのない試合に逃げようともせずにいたのは諦めでも意地でもなく、どうすればよいかわからなかったからだ。今まで持ったことのないはずの感情。しかし腹の底にはどす黒いものが確かに湧き上がってきている。これは何なんだ。俺にどうしろというんだ。飼い主は自分を見捨てたのか?ルカ…兄は死んでしまった。自分を慕ってきたあいつらももういない。身内を一人残らず一気に奪われたウラドは衝撃の大きさと自身の感情にまだついてゆけずにいた。自分の感情を識る術を教える大人は、彼らの周りにはいなかった。 その時、視線をぼんやり泳がせていたウラドは確かに見た。遥か向こうの金持ちどもの座る席で、見覚えのある輝きを。 飼い主が振り返った時に翻ったローブのすき間から、陽光を腰に差された「それ」が反射した。それは紛れもなく兄の、ルカの短刀だった。 その瞬間、確信した。認めるしかなかった。飼い主に理由などなかった。これは遊びだ。からかわれているのだ。面白がっているのだ。おもちゃの人形に飽きた子供がその四肢を捥ぐ様に。 渦巻いていたものがウラドの頭の中で音を立てて決壊した。思わず頭を抱える。声にならない呻きが漏れる。 体が震える。初めて味わう真っ黒な「怒り」が、のように身体を広がっていく。 故郷を奪われた頃の記憶がないヴラドだったが、家族を奪われるのはこれで二度目だった。ヴラドの体に長い間とぐろを巻いていた怪物が、深く刻まれじくじくと溜めこまれた憎悪がようやく解き放たれ、殺戮を求めていた。 「かえせ、おれたちを、おれたちのすべてを、かえせ…」 ヴラドは絶叫した。得物も構えずに、開始の合図を無視して敵の只中へと突進した。 ―――二十六、二十七、二十八。脚に、腹へ、首を。 応えるかのように、雄叫びとともに突進してくる剣奴たち。躱して、いなして、斬る。止まっている暇は一瞬たりともない。視界に現れるモノを片っ端から殺しまくった。思考は既に消え失せ、今までせき止められていた激情が体中をのたうち回りヴラドの四肢を突き動かした。しかし正気を失いながらも、その動作は恐ろしい程に正確だった。次々に振りおろされる武器の切っ先をくぐりながら、鎧のすき間を瞬間で見定め、そこへ刀身を叩き込み、哀れな獲物を糞袋へと変えてゆく。まだだ。まだ殺す! 兜の中の眼を潰し、喉を潰し、躱し損ねれば首輪で受け止め、両手がふさがれば首の肉に喰らいついて噛み千切る。容赦は一切なかった、自分にできる最短の時間で敵の命を終わらせる。 およそ六十人を斬殺する頃、敵の大半は尻ごみを始めていた。慎重になり始めたのか、周りを取り囲みながらじりじりと間を詰めてくる。それと同時にヴラドは徐々に冷静さを取り戻し始めていた。息も上がってきている。始めに殺した敵から奪った血塗れの剣をその場に捨てて、そばにあった死体を蹴りよけ、転がり出る自分の血に染まることのなかった剣を拾いあげる。浴び続けた夥しい量の返り血で、顔と身体は真っ黒に染まっていた。その時、自分の黒い首輪がゆっくり熱を帯び始めていたことに、ヴラドはまだ気付けないでいた。 闘技場の丸くくりぬかれた空からはぎらつく太陽の光が剣奴たちの背を焦がし、揺らめく彼らの影を繋いで黒い波のようにうねらせている。
そこはまるで牢獄のような、最底辺に位置する剣奴の部屋。ひどく高い位置に設けられた格子窓からは日の光が差し込んでいて、宙に舞う砂埃を照らしている。その先の日の当たる場所に、二人の少年はいる。ヴラドは粗末な藁の寝床の脇に座って、かつて「金色の蛇」と呼ばれ、栄光のすべてを手にしていた闘士の亡骸を見下ろしている。ヴラドはゆっくりと彼の身体の下へ手を差し込み、そっと抱きかかえた。 ――「いまをもって、俺とおまえは兄弟だ。なあ、こんなくだらねえことでお前は死ぬな。ひとりでも生き延びろ。安心しろよ、俺が死んでこの体が腐り果ててクソ以下の存在になっても、地獄の底からお前を見ててやる。お前を愛してる。絶対に忘れるなよ。俺を、忘れないでいてくれ」 これがルカの最期の言葉である。 生まれて十数年、食事と人殺し以外に使ったことのなかった生傷だらけの両腕に、初めて抱く人間。それは枯れ枝のように痩せこつれ、たった今自分の兄となった人間の亡骸。強く抱きしめると、ぽきりとどこかの骨が折れる音がした。しばらくの間をおいて、ヴラドは彼をゆっくりと床におろした。闘技場へ向かおう。次の試合がいつも通りの熱気と狂気をもって始められるだろう。今回ばかりは処刑という方が正しいかもしれない。 「もういいのかよ?ありゃ、死んじまったか」 ドアの前で見張りをさせられていた太ったごろつきが話しかけてきた。 部屋を覗き込んで大きな溜息をつく。 「しっかし金色の蛇ともあろう闘士がこんなみじめな最期だとはなァ…ラガルト様もむごいお方よ。しかしヴラド、お前もこれからどうすんだ。試合に出たところで無駄死にするだけだぞ。なあ、おれの知り合いの連れにジャックって逃がし屋がいる。今からでも遅くはねえ!そいつに頼んで…」 ウラドは何も答えず、ごろつきの肩を二度叩いてその場を立ち去り、闘技場へと向かった。 「行っちまいやがった。…ルカ坊よぉ、お前の弟も直ぐにそっちへ行っちまうかもしれんぜ」 「…かれは試合に出るのですね」 「ああ…ん?…うわぁ!」 太った男は大仰に驚いて尻餅をついた。いつの間にか背後に眼帯をした少年が立っていたからである。 見た目はまだ10歳程で、どうやってここまで入り込んだのか見当もつかない。 少年はヴラドの去った方向へすたすたと歩きだ出し、男の脇を通り過ぎる。 「全くどこのボンボンだ!ここはガキの入っていい場所じゃあねえぞ!くらぁ!」 男が振り返って怒鳴った時には、少年の姿は煙の如く消えていた。
帝国広報 マシュー「ふむ・・・もういいだろう。ジルキオ。解放軍に使者を送れ。平和的に話し合おう。 和解の道を共に模索するのだ」 マシュー「しろっこ、エルフ領にも使者を送れ。講和会議を開きたいと通達するのだ」 帝国暦○○年 四月一日 帝国執政 マシュー Q:この話は信じられる?
まぁ9割方の理由は先に書いたお話の通り、シ・ゲルをはじめとしたエルフへの恨みだと思う。 でも元々エルフって魔法に長けた種族のはず。 であれば、神を召還したりするアーティファクト(秘宝)もあったりするんじゃないか?と。 だからこそ、シ・ゲルが召還とか企めたわけだし。 (もっとも、召還しようとした神自身に酷い目にあわされたわけだが・・呼ぼうとしたのがアレじゃぁなぁw) で、召還ができるって事は逆に封じる事もできるわけで、そういう秘宝とかあるんだろうね。 それもあるからシ・ゲルは神を使役できると思ったんだろう。 で、恐らくその封じるアーティファクトがコアみたいにあって、島のあちこちにパワーの源や制御装置のような アーティファクトのある遺跡があるんだろうね。 六芳星みたいに6つとか。 元々、魔術的には五芳星が有名だけど、五芳星は”神の使いの力”(つまり天使とか)といわれてる。これはひっくり返すと悪魔召還とか堕天につながるから。 で六芳星はひっくり返しても同じなので”神自身の力”といわれてる。だから6つあるんじゃないか。と。 で、コア的なのがエルフ島にあって邪神を封じてたのなら・・・・ そりゃあの神様の一部(のデガラシ)であるマシューとすれば、放っとくわけにはいかない。己(とか本体とか)が封じられてるんだから。 それが残りの1割じゃないかな? つーことで、エルフ島を狙ってるんだと思う。