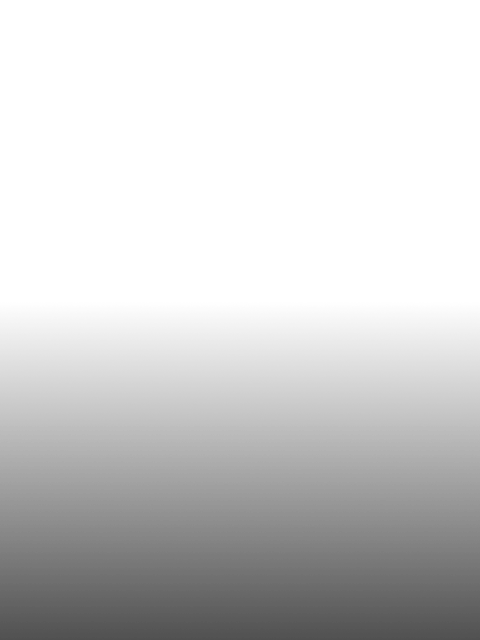利用条件
- チャンネルの購読はのに限られます
- チャンネルの購読はに限られます
- チャンネルの購読はに限られます
- チャンネルの購読はに限られます
- チャンネルの閲覧にはフォロワさんでRPG詰め所へのアカウント登録/ログインが必要です
注意事項
- 購読ライセンスの期限を超えると、チャンネルを閲覧できません。購読ライセンスを新たにご購入ください
- 一度ご購入された購読ライセンスの返金はできません
これまでのご利用、誠にありがとうございました。
自由には二種類あるものだと、“黒犬”と呼ばれた男は信じていた。 混沌と、秩序だ。その両方の中に自由はあった。あるいは、自由の中にその二つがあるのかもしれない。 とにかく男は自由には二つの種類があるのだと考えるに至った。彼が二十にも満たぬ年だった頃にはすでに、そのような鋭く忌々しい諦観に支えられた思想をきっぱりと刻み込んでいた。以来十数年その結論は揺るぐことがなかった。 男は自由を二つに選り分け、そしてそのうちの一方を激しく憎悪した。混沌の上に成り立つ自由を嫌悪し、そして排除しなければならないと決意していた。 それは思うままに殺し、生娘を犯し、貧しい者から盗みを働くことを咎めぬ自由だった。何もかもの悪辣が野放しにされ、法は死に絶え、君主が放逸を極めた時代に、民衆の間で蔓延した病のような自由だった。その悪徳は腹が空けば平気で盗み、口喧嘩の先に決闘を起こし、裏路地に泥にまみれた半死半生の娘を転がした。疫病は流行るままにされ、薬は常に足りず、薪さえ満足に手に入らない。だが、どんな罪さえも咎める者はいない。それも自由の形だといえた。 だが男は肉親を混沌のもたらした自由によって奪われていた。無計画な戦で父を、病で母を亡くし、そして最愛の妹は悪徳の栄えにあやかった貴族に辱められ、少女のうちに命を絶った。 当然の帰結として、まだ少年だった男は混沌を純粋に憎むに至った。そして病理を取り除き、秩序による自由をもたらさなければならないと誓ったのだ。 だがその時、彼自身がまだ吹きすさぶ嵐のような理性なき怒りに囚われていた。煮詰まった鬱屈と義憤の境目を見分ける術を持ってはおらず、またそれを自覚してもいなかった。 「なにを言おうと無駄だ、ジルキオ。今のお前を認めるわけにはいかん」 激しく打ち据えられて全身の感覚が滅茶苦茶になっていた。腕が痛むのか背が痛むのか判別がつかず、頭に直接脚の疲労が接続されているかのようだった。 革命派の暗い地下の隠れ家では、時間の経過も曖昧だった。物騒な炎を燃え立たせる炉のせいで部屋は熱が篭り酷く息苦しい。窒息しそうな視界がぐらぐらと揺れ、ぐずりと膝が萎え、手を突き出す間もなく前のめりに床に崩れ落ちる。地を掻いて立ち上がろうとするジルキオの腹に容赦なく硬いブーツのつま先がねじ込まれ、勢いよく跳ね飛ばされた体は受身も取れずに転がった。 “狼”が自分をなんの感慨もない目で見下ろしているのを感じて、ジルキオは遠のきかけた意識をなんとか捕まえる。 “狼”―この壮年の厳しい男は革命派の中でも選りすぐりの戦闘員を鍛え上げ、特殊な任務に当てるための手駒として育てていた。“狼”は見込みのない者を掬い上げてでも手勢に加えるほど寛容ではなかった。ここで自失して倒れ込んだままでいれば、“狼”は自分を見限るに違いない。そう考え、なけなしの気力をかき集め、床に落ちた訓練剣を拾ってがくがくと震える脚に鞭打ち立ち上がる。汗にまみれてべったりとまとわりつくクシャクシャの黒髪がひどく煩わしかった。 「やめにするか?お前には無理かもしれんな。可哀想に、立つだけで精一杯だな」 「…いいえ…まだ、やれます…!まだ…!」 懇願するように絞り出しながら、なぜそうまでしてしがみつくのだろうと自問した。軋む体の苦しさが意志をだらしなく引き伸ばし、限界に近い疲労のせいで強烈な眠気のような虚脱がまとわりついて来るのを必死に払いのける。 ジルキオ自身は同じように訓練を受けている者たちの内で誰よりも飲み込みが早く上達も群を抜いているという自信があったが、何が気に食わないのか、“狼”は度々彼をひどく叩きのめし、ほかの誰も負ったことのないような怪我と精神的痛手を被るまで追い詰めることがあった。 「やめてもいいんだぞジルキオ。つらいだろう?」 「やめません、続けてください、お願いします」 負けを認めてなるものかとばかりに息せき切って食いつくと、“狼”は奇妙な、侮蔑のような色を微かににじませた。 「…そうまでして復讐したいか」 虚を突かれた。 「復讐のために使う技術などここにはないぞ」 「俺は、復讐をしたいのではありません…二度とあんなことが起きぬようにと…!」 「そのために悪逆な貴族の首を自分の手で刎ねたい、そうではないか?いずれお前の妹を辱めた連中に復讐できるなどと期待していないと言えるか?」 「…それは…」 言いよどんだジルキオを一瞥した“狼”の目はひどく寒々しい色をしていた。彼は背を向け赤々と高温で燃える炉に近づくと、焼き鏝と一緒に火にくべられた剣を引き抜いた。その拍子に黒い鉄の格子に刃が擦れ、ちりちりと火花がこぼれ落ちる。煤で黒光りする刀身は明るく赤熱こそしてはいなかったが、それでも暗がりの中でぼんやりと輝き、陽炎を生むほどにはきつく熱されていた。 「私怨を捨てよ、さもなくば…死ね」 平坦にそう告げると“狼”は一切の前動作なく踏み込み熱を孕んだ剣を叩き込んだ。咄嗟に剣を水平に構えて受け止める。だが疲れきった腕は容赦なく押し込まれる力に徐々に下がり圧倒される。耐え切れず片膝をついたジルキオに覆いかぶさるように“狼”は何のためらいもなく焼けた剣を押し付ける。ついに抵抗も虚しく、“狼”の刃がジルキオの肩に食い込んだ。 激しい動揺が一瞬息を締め上げた。次に耳をつんざくひび割れた悲鳴が迸り、まるで自分の声でないかのように響き渡った。肉を割り裂き血を焼く感触が思考を真っ白にする。剣を取り落とし、死に物狂いで腕を伸ばして“狼”の手を掴み抗う。死の恐怖をこれほどまでに身近に感じたことはなかった。 「がっ、ぁ、やめ…てっ…!ひぐっ…!い、や、しにたく、ない……!」 恐怖に歪んで咽び泣く。年相応の子供じみた命乞いが漏れた。 「耐えられぬなら死んだほうが幸いだ。死を恐れて改革など成せるものか」 無慈悲にそう言い放つ“狼”の手つきには一切の手心もなかった。何よりもその言葉が、彼にとって利己的な臆病者は虫ほどの価値もないのだと物語っていた。 そうと理解した瞬間、怯えた啜り泣きが出し抜けに凶暴な絶叫にかわった。そしてジルキオの表情は突然、ぱっと火が付いたように生存本能と怒りに燃え上がった。理不尽な死に直面したことで彼は奮起し、そして怒り狂った。自分の死を認めるわけにはいかない。そんな憤怒が噴き出したかのように見えた。 「…なにが!わかる!!!!何がわかるって言うんだ!」 ジルキオは残った力を振り絞り、剣が食い込み焼け爛れた傷から鮮血が噴き出すのも構わずに、掴んだ“狼”の腕にむしゃぶりついて血が出るほどに噛み付いた。その反撃は“狼”も予想していなかったのだろう。がむしゃらな突進に足元をすくわれ、二人は取っくみあいながら冷たい石の床に倒れ込んだ。“狼”は素早く平静さを取り戻し、馬乗りになって掴みかかるジルキオを得意の体術で投げ飛ばした。 「笑わせるな!自分が一番不幸だとでも言いたいのか…!」 “狼”は危うげもなく身を起こして鋭く叱責する。ジルキオは派手な音を立てて部屋の隅の机に激突し、椅子やランプを巻き込んで床にしたたかに打ち付けられた。だが堪えたふうもなく、まるで痛みを感じていないかのように機敏に跳ね起きると興奮した猛獣のように荒い息をつきながら低く唸り、ぎらぎらと底光りする青い目で“狼”を睨みつけた。 「そうだ…殺してやりたい!それが悪いか!あいつらも、皇帝も!全員首を刎ねてやる!!」 砕けた声音で吠える青年の癖の強い黒髪が無残に乱れて、殺意をむき出しにした顔を暗く縁る。 そして炉の炎に照らされて、赤紫に燃え上がる瞳に覗く純粋な暴威。 自身の保身すらも眼中にない、ただ相手を打ち倒すことのみを燃すその意志に正対し、“狼”は不意に背筋にかすかな寒気を覚えた。 四肢の血管が長虫となってのたうつような怖気は、“狼”の古い記憶を揺さぶった。 彼に、かつて帝都の墓地で見た大きな黒い犬を思い出させたのだ。 その犬は先帝の葬儀の日にどこからともなく現れて葬列に付き従い、これから訪れることになる現皇帝統治の苦難と荒廃を予見するかのように不気味な遠吠えを上げていた。 若き日の“狼”は犬のあまりに不吉な様子に葬列のそばから追い払おうとしたが、その犬は怖がる様子もなく、まるでにたりと笑うように“狼”に向けてはっきりと牙を見せ、それから喪に服する群衆の中に悠々と紛れて姿を消してしまった。それはもう随分と遠い昔のことであったが、なぜかくっきりと脳裏に焼き付き、忘れることのできない記憶となっていた。 あの日の黒犬が帰ってきたのだ、と“狼”は唐突に畏れに似た思いを眼前の青年に抱いた。 死の匂いを嗅ぎつけ、皇帝の葬列に再びあの嘲笑を捧げるために黒犬が舞い戻ったのだ、という根拠のない確信に襲われ愕然とした。 今は見境なく憤り吼えたてるばかりだが、もし彼に大義の首輪をつけることが出来たなら。そう考えて“狼”は昂ぶりを自覚する。野放しにすればこの青年は野犬のように見境なく周囲の者を噛み殺し、やがて自滅するだろう。 だがもし彼がこの純粋さと熱量、義憤と苛烈さを大義に捧げることを学べば、どれほどの戦果を挙げるだろうか。あるいは狼が率いる群れを継ぐことすらできるかもしれない。 “狼”はおもむろに落ちた剣を拾い上げ、傷を庇いながらも警戒心を隠さず刺々しく睨めつけてくる青年と向かい合う。力尽きれば殺されるとでも思っているかのように後退るジルキオに歩み寄り、手に持った剣の柄を差し出した。 「…わかった。チャンスをやろう。お前の妹の仇をとる機会を」 虚を突かれて言葉を失う青年に、“狼”は表情の薄い顔を近づけて、重々しい声で唸った。 「憎い者たちを皆殺しにしろ。そうして生きて帰って、お前が何を得たのかを示せ。復讐から何を得ることができたのかを」 有無を言わせず差し出した剣を握らせ、それからジルキオの傷つき血に濡れた肩を掴み爪を立てた。短いうめき声を漏らして歯を食い縛る彼にその痛みを刻み付けるように、きつく力を込める。擦り傷だらけの顔を歪めて、ジルキオはくぐもった声で吐き捨てた。 「殺さないのですか、俺を。従わぬ者は必要ないと言ったのは貴方だ」 「処分するかどうかは、お前の答え次第だ、“黒犬”よ」 「……!」 “狼”の言葉にジルキオは思わず顔を上げた。“狼”は自分の部下に決まって名を授ける。人間以外の生き物の名を。この扱いを受ける者は実力を認められた相手だけであることはジルキオもよく知っていた。 「事が済んだ後、お前がどんな答えを持ち帰るか。それがお前の命運を分けるだろう。それまで“黒犬”の名は預かっておく」 「では…!」 「焦るな。まだお前を認めたわけではない。焦らずとも直に機会をくれてやる」 自身の血で汚れた剣を両手で握ったまま立ち尽くす青年に“狼”は無愛想に言い捨てた。 「それまでに、傷を治しておけ」 ―――――――――――― (続くよ!たぶんね) (設定解説:“狼”はもと帝国軍人だったが先帝統治の世に膿み下野を決意。反帝革命派に合流してからは自身の戦闘技術を元手に、有望な若者を来る皇帝派制圧に備えて鍛え上げていた。歳は当時ですでに四十代半ばだったとみられる。彼が育てた戦闘員たちが諜報破壊工作のノウハウを組み立てて継承し、現在の特務隊の前身となる部隊を作った。という勝手な設定。ジルキオが27歳の時に“狼”が病に倒れたことで隊長の任を引き継いだ。)
さらさらと海が波打つ音と、口の中の砂の不快な感触が、切れていたヴラドの意識をゆっくりと引き戻してゆく。それにつれ、身体の節々が感覚を取り戻してゆくかのように痛み始める。 「う…」 ヤシの葉から洩れる陽の光がまぶしい。起き上がれるだろうか。その前に、自分がなぜ今こうしているかをぼんやりと思い出してみる。 海賊と城で公爵に喧嘩を売って、逃げる途中であの長い髪の騎士の足止めをして、窓から飛び降りて…あの高さからよく助かったものだと、自分でも思った。その時、ふとあの騎士に言われた言葉が、全く歯が立たなかった剣戟とともによみがえる。 「虚ろな剣だ」 「師と呼べるものがなかったのではないか」 ヴラドは顔をしかめた。腹が立ったのは、それを否定できなかった自分にだ。あの言葉を言われた時、真っ先に思い浮かべたのは兄ルカの顔であったが、思い返せばかつて師と仰いでいた筈の兄は、確かに自分に剣を教えたことは一度もなかった。自分はその殺しざまをひたすらに真似るしかなかった。相手より早く、多く斬りつける方法を。兄もまた誰にも何も教えてもらうことなく生きてきたのだろう。その傑出した才能は、ついに誰にも拾い上げられることはなかった。遺されたのは兄の影を追い続けた自分だけ。 もっと強くならねばならない。兄の真似でなく、「自分の戦い方」とその「使い道」を手に入れなければならない。理由はまだ見つからないが、ヴラドは確信めいた思いを持ち始めていた。あの騎士のようなやつらが他にもいるだろうか。もっと戦いたい。もっと、もっと知りたい。戦いに勝って聞きださねばならない。あの時に獣人から兄に助けられた理由はなんだ?闘技場から出るとき、あの魔術師がこうまでして自分の命を繋ぎとめたのは何故だ?それは自分が強くなりさえすれば、全部この剣が聞きだしてくれる、わからないことは全部。そんな確信。 思いを巡らせていると、ヴラドはあることを思い出した。自分の腕はどうなった?捨て身の一撃を加えるためにくれてやった腕。 目をやると、当たり前だがやはり腕はなかった。そこで妙なことに気が付く。妙に切断面がまっすぐで、何より出血も、痛みさえほとんどなかった。止血すらしていないのに。加えて浜辺に打ち上げられたのならこんな砂浜から離れた木陰にいるだろうか?おもわず起き上がる。すると少し痛みが走った。よく見ると、見覚えのない紋様が傷口の周りに刻まれている。刺青ではないようだった。 辺りを見回すと、すこし離れたあたりに城で見かけた赤い生き物が丸くなってすやすやと寝息をたてているのを見つけた。近くで見るとネズミというよりは猫のような姿形だが、とんぼのような羽と白い角が生えている。 「一体なんなんだあいつは?よっ…と」 とりあえずその場で立ち上がってみる。骨は不満そうに軋むが、折れてはいない、どうやら動き回る分には大丈夫そうだ。 なくなった腕の方の肩をさすりながら、ヴラドは赤い生き物に近づいてみた。しゃがみこんで覗き込む。生き物はよく眠っていた。 頭を鷲掴みにして持ち上げてみるが、起きない。よだれを垂らし、眠ったまま微笑んでいる。じつに幸せそうだった。 ヴラドは少し考えてから、生き物を持ち上げて胴体からかじりついた。 「うぎゃあー!?」 生き物は実に人間らしい悲鳴を上げた。 「イタイ!!なんで!?待って!!食べないで!イタイ!助けたの!吾輩!助けたのに!あイッタイ!痛い!いぎぎぎ…」 噛み切れないし、不味い。それに助けがどうとか言っている。 しばらく咀嚼を試みたが、しぶしぶ解放した。勢いよく宙に舞い上がる奇怪な生き物。 「喋るし飛ぶし食えないネズミ…」 ヴラドのもらした漠然とした感想に、生き物は空中を浮遊し腰に手(前足?)を当て、憮然として反論した。 「失礼な!吾輩はカーエデール卿!きみを助けたの!大変だったんだから!落ちるきみが海に叩きつけられる前に空中に印を展開して受け止めて、水の舟をあみこんで、潮の流れをよそくして、海の上で傷口を塞いで…ここまでやっと運んで、せいこんつきはててたというのに!全く!向こう何年か分の魔力ちょぞうがなくなっちゃったんだからね」 「…ありがとう、ハエ?」 とりあえず礼は言う。命を救われたのだ、 「あ、いやあ、たいしたことないよ…えへへ」 なぜか生き物は頬を赤らめて照れている。話を聞くに、ただの動物ではないらしく、自分を助けるために全力を尽くしたことはヴラドにもわかった。理由はさっぱりわからないが。 「で、ここはどこだか知ってるか?」 「ずいぶん流されたからね、魔力の濃さからして皇国ではないし、吾輩たちの後ろの森のにおいからして多分だけど『お腹』の辺りじゃないかな。多分ここは森を抜けた先の海岸だとおもうよ。あとハエじゃないよ」 「ち、やっぱ全然わかんねえ…あいつ、無事かな」 「船長たちは無事だよ。君はそれよりその腕を治さなくちゃいけないよ。吾輩の印も長くはもたないしね」 「わかるのか」 「わかるよ。みてたもん」 「そうか…で、やばいのか、この腕」 赤い生き物は口に片手をあてて考え込むように話し始めた。 「ふつうのけがだったら止血してれば傷口は癒えるんだけど、きみの全身にある印はどれも欠けちゃいけないものだったんだ。何を封じてるかは知らないけれど、こんなにふくざつでみごとな印は今までに見たことがないよ。吾輩にはむずかしすぎて判断がつかないけれど、腕が無くなったことで印の均衡が崩れてる。吾輩の止血の印も方式の全くちがうのを上書きしたものだし、いずれ『きょぜつはんのう』が起きるとおもう。はやく博士に見てもらわないと痛い!!なんで!?」 赤い生き物は頭をさすっている。 「何言ってるか全然わからん、要はそのハカセってのが何とかしてくれるんだな?」 「うくく…そうだよ。この森を抜けてかなり南にくだらなきゃいけないけどね。本当は吾輩が飛んで案内できればいいんだけど、もうあんまり高くはとべないんだ…森に一人吾輩の知り合いがいるから、もしその人に会えれば森の抜け方がわかるかも知れないよ」 「そうか、じゃあまずそいつに会いに行こう」 「えっ」 「案内しろって。この辺のこたあ全く知らねえんだ、俺より方角くらいはつかめるんだろ?」 「そうだけど…それって吾輩が一緒に行ってもいいってこと?」 赤い生き物はおずおずと尋ねる。ヴラドは赤い生き物に背を向けて、身体の節々を伸ばしながら答えた。 「他に誰がいんだよ」 「…わーい!!やった!やった!!やったあ痛っ!!なんで?」 赤い生き物は頭をさすっている。 「うるせえからだよ。…腹減ったな。」 頭をぼりぼり掻き乍ら、青い海を見つめる。 まずは食料を調達せねばならない。ここはどうやら人の住んでいる場所ではないらしい。「あれ」は食えなかったし、狩りなんてしたことがない。ヴラドが覚えていかなくてはいけないことは、戦いのほかにもまだ山のようにある。 「あー…はぁ」 思わずため息が漏れた。 「どうしたの」 「なんでもねーよ」 当てもなく、彼は浜辺を歩き出した。 自分が見つけるべき答えを迎えに行くために。 おわり 【ほそくといいわけ】 改行とか文節をもっと学校で真面目に習っておくべきだった。 Fsrpg世界地図で言う「竜のへそ」の辺りに流れ着いたヴラドは…的な話です。 これから続き物にできたらなあと思ったり思わなかったり。最後の方ちょっと面倒くさくなって無理やり締めたのは内緒ですねん。あと投稿が自分ばっかりになっていくのがはずかしいしさみしいので誰かなんかかけ。俺の自尊心の為に!
時は夜更け。降り出していた雨はいつの間にか勢いを増して大雨になっており、ざあざあと降り続けている。 …ここはとある国の市街の大通り。時間帯と降りしきる大雨のせいでひと気は全くないが、ふだんは大変な賑わいを見せる活気ある街である。住民の大半を占めるのは、およそ中流下流に位置する民衆。すなわち商人や工員、農夫たちである。その「民草たち」が毎夜ぎゅうぎゅうに集まっては安酒をやけくそにあおる、大きな古酒場があった。 嵐のようないつもの喧騒もようやく終わりをつげ、歌も注文のがなり声ももう聞こえない。外の大雨と今にも轟音とともに稲光を落としてきそうな雷雲の唸り、ジョッキを握ったままに酔い潰れカウンターに突っ伏した貧乏農夫の大いびきと、暖炉のぱちぱちとはぜる音、ひとり店に残った店主とみられる女のせっせとグラスと食器を片付ける音だけが響いている。 その酒場の真上に当たる二階には、八畳ほどで木造りの、二つのいすと小さなテーブル、かび臭いダブルベッドが一つ。あとは箪笥がひとつという古びた部屋があった。 そこに宿を取っていたのは、後ろに結わえた真っ白な長髪と顔の右半分の刺青が目を引く、二十代半ばほどの目つきの悪いが精悍な青年と、まだあどけなさの残る十四、五歳ほどの赤毛の少女。刺青の青年は窓際に置いた椅子に腰掛け、くわえた煙草から紫煙をくゆらせながら、窓の向こうの暗闇をじっと見つめている。窓枠は大粒の雨に打たれ頼りなくがたがたと音を立てて震えていた。少女はすでにベッドで眠りに落ちていた。 青年はしばらく窓のそばで座っていたが、ふと顔をしかめると小さく舌打ちをした。 「ち、撒ききれてねーな…昼前に片付けたハズなんだがな」 気配がする、三人。夜の暗闇と雨音に紛れて這い回る気配を、青年は深いため息とともに煙を吐き出しながら、容易く感じとっていた。 「三匹か。そろそろ来るなこりゃあ。この雨ン中ご苦労なこった…げほっむほっ!おええ!ぐぬぬ、火葬場の煙でもこんなまずかねーぞあの野郎」 青年は苦虫を噛み潰したような顔をして、まだ慣れない煙草を握りつぶしてうしろへ放った。 「あ、途中ですてちゃだめだよ。博士におこられるよお?」 いつの間にか目を覚ましていた少女、いや、少女が寝ていた場所には白い角をはやした緋色の小さな猫のような妖精がいた。しかし猫と違って体毛はなく、大きさは先ほどまでいたはずの少女の頭ほどしかなかった。背中には薄い青色で半透明の羽が生えており、細長い尻尾をゆらゆらと揺らしている。 「ヴラド君のたましいを『ひきとめる』けむりなんだよ。それに、すごくいいにおいじゃない」 青年が妖精の方を振り向いた。全く驚くそぶりも見せない。 「うるせーな。起きたのか、丁度良かった。んなことよりすぐにお客さんが来るぜ。見たところ本職の方々だ。お前にはまだちょっとキツそうだな。終わるまでベッドの下にでも入ってじっとしてろ」 「え、でも昼間は森でどろぼうのおじさんやっつけたよ!」 「はあ、あんな雑魚と一緒にすんな!あいつ火掻き棒しか持ってなかったじゃねえか。まあ今回は見学がてら温存しとけ」 「はぁい。でも床からじゃ何にも見えないよ~、にしてもすごい雨だね!」 妖精はひとつ寝返りを打つとそのままストンと床に落ちて、ころころとベッドの下へ転がって行った。 「うえ!ほこりまみれだよ!クモの死体にねずみのふんもある!げええ~」 2人は追われている。それもずいぶんと長い間。もう三年近くになるだろうか。とうの昔に追われる理由はなくなってしまった筈だったが、青年は忘れられるには如何せん恨みを買いすぎていたし、少女(今は妖精だが)にも追われるべき「途方もない価値」があった。どれほど遠く離れていようとどこからともなく追手たちが現れ、その度に男が追手を手痛く撃退してきた。 つと稲光が輝き、雷鳴が轟く。雷光に照らされたゆらめく影を青年は見逃さない。 賊はどうやら早くも位置に着いたようだ。向かい側の建物の屋根に一人、窓の直線状にいる。おそらくは射手。加えて酒場の入り口に一人。そしてこの酒場の屋根にも一人。 青年は焦るそぶりもなく、足元に立てかけた、鞘に納まった幅広の曲刀のような武器を手に取って立ち上がり、窓の脇の壁にもたれかかった。 「ふう…」 深く息を吸い、ゆっくりと鞘からナイフを外してゆく。二度目の呼吸をし終わる前に、再び雷鳴が轟く。同時に窓ガラスが割れた。射手に放たれた矢弾が窓ガラスを突き破ったのだ。 矢はベッドとカモフラージュの為に丸めた毛布に深々と突き刺さり、さらにその下にいる妖精の頭をかすめた。 「どわあ!?」 続けてこの建物の屋根にいた一人が飛び降りて、割れた窓から器用に身を捻って侵入してきた。が、そこへ間髪入れず身を潜めていた青年が組み付き、三度の膝蹴りを敵の腹にめり込ませる。ひゅっ、という掠れた呻き声とともにうずくまった敵の腕と胸の辺りをつかみ、そのまま割れた窓をさらに破壊しながら外れた窓枠ごと投げ飛ばした。 「っし、あと二人」 土砂降りの雨が部屋になだれ込みはじめ、流れ込んで来た外の音でにわかに部屋の中が騒がしくなる。 豪雨と雷鳴に紛れ、酒場の人間に気付かれることなく侵入してきたのであろう二人目が部屋に躍り込んで来た。先ほどの敵もそうだったが、全身を黒装束で包んでいる。 「とうとう雇われまで使いだしやがったか。ウンザリだな。確かに退屈はしねえけどな?お前らもうちょっと場所と時間を考えろよ」 話しながら青年はベッドの枠につま先をかけている。 「…笑止」 敵は手に持っていた抜き身の長い倭刀を八相に構えた。 「そうかよ」 次の瞬間、青年は一気にベッドをつま先で蹴りあげた。もんどりうって目の前に倒れこんで来たベッドを敵はすばやくかつまっぷたつに叩き割ったが、割れたベッドの影から現れた青年の影まで捉えることは出来なかった。胸とみぞおちに拳を叩きこまれ、あばら骨が折れる音が聞こえる。 「くぉっ…」 かすむ視界にでたらめに刀を振ろうとしたが、後ろに回り込んだ青年に容赦なく蹴倒され、頭を鷲掴みにされて床にしこたま打ちつけられたあと、そのまま一人目と同じように窓から投げ捨てられた。 「今の死んでないよね?まったく、どうやったらあのベッドがけり上がるんだろ…」 いつの間にか角の箪笥の上に避難していた妖精がたずねる。 「ああ、いたんだっけなお前!ケガねえか?悪い悪い。まあ大丈夫だろ、あのくらいで死ぬようには見えねえし。窓の下見てみな、とっくにいねえと思うぜ?」 「もうひとりは?」 「とっくに逃げたろ。気配も消えた。いやあ今度のは大したことなかったなあ」 「傷一つないもんね。吾輩は死にかけたけど」 妖精はふわりと浮いて、窓枠だったであろう場所に着地した。 「つめたっ!…あらほんとだいない」 「だろ?…じゃ、とっととばっくれようぜ。こんなとこでおちおち寝られねえよ、明日には騒ぎになる」 「えー」 翌朝、竜巻が来たような水浸しで悲惨な状態の部屋と、酒場の前に散らばった血糊にまみれた窓枠の残骸が、その街のちょっとしたニュースになったのは言うまでもない。 2人は追われている。それもずいぶんと長い間… おわり ・・・いつもの恥ずかしい言い訳 (集中力が切れてしまって途中からずいぶんと乱文雑文になってしまいました。雰囲気だけお楽しみください。雰囲気だけ!)
(騎士は破られた窓の外を見やる、青い海がどこまでも広がっていた。 すると視界の端に、羽の生えた赤色に見える人間、のような姿のなにかが人を抱えて飛んでいくのがぼんやり見えた気がした。幻など柄でもない、だがまさか殴られて頭をやられてしまったのかとなどと考えたが、やがて首を横に振って踵を返し、立ち去った…。) それから数日後。 ヴラドと赤い妖精カーエデール卿は森の中にいた。大木に縛り上げられた数人の男たちを見下ろしている。 男らは口から血の泡を飛ばしながらなにやら口々に喚いている。 「Uradukag ikabasonirom in aramasik!!」 「Adnnanonominan azaw ihserariznnik onareraw ah ianizamonimak!!」 「うるっせーな。それにしてもなんだな、人間がいるんじゃねーか。何がミカイノトチ~だよ」 「元々ここに住んでいる人たちだね。いきなり襲ってくるなんて驚いたけど」 ヴラドは男らに背を向けて、剥ぎ取った革鎧や装備の類を選別しはじめた。 「ま、こいつら色々装備やら持ってたし、こっちは都合がよかったけどな…なぁ!」 つと立ち上がったヴラドはそのまま振り向きざま男たちのうち一人の顔に勢いよく回し蹴りを食らわせた。顎が砕け、瞼も裂けた。噎せた男の口からはボタボタと血と歯が滴り落ち、くぐもった悲痛な呻き声が洩れる。 「結構頑丈だな。おーい、足が汚れたぜ?おら、拭けよ。こっちは腕がなくてよ」 うなだれる男の胸を蹴り上げて押さえつけ、今度は顔面を踏みつぶそうと足を上げた。すると、 「だめ!!もうじゅうぶんだよ!死んじゃうって」 見かねた卿が半死半生の男の前に短い両手を広げて立ちふさがった。 「ああ?こっちはいきなり射かけられるわ斬りつけられるわ、もしやられてりゃあケツに串突っ込まれて丸焼きにして食われるところだったんだぞ!ハエネズミくんよ~」 妖精ごと男の顔面をぐりぐりと踏みつける。後ろの男はもがもがと苦しんでいる。 「あうあう…でもダメだって~、ほら!でもこうして吾輩が事前に察知できたわけだし!いたたた」 「くぬっくぬっ!どけコラ!ここで殺らねぇとまた……ハァ、くそ」 しばしの格闘ののち、ヴラドはしぶしぶ足をどけ、木の根に腹立たしげに座り込んだ。妖精が男から離れると、丁度背中を押し付けられていた男の顔の傷は卿の羽から漏れ出す魔力によって治癒され跡形もなく無くなっていた。 「Awu! Akazawim on imak!」 「何言ってるか全然わからん!殺すぞ!」 「どうどう。吾輩を神様だと思ってるみたいだね、すごく感動してるみたいだよ」 「わかるのかこいつらの言葉」 「言葉はわからないけど、言葉を発する前に心が読み取れるからね。かなり信仰心のつよい部族だよ、それにヴラド君、この森の出身なの?」 「俺が?言葉も知らねーのにそんなわけねーだろ。…にしても、それで襲ってくんのがわかったってのか?そりゃあ便利だな。ついでに森の事も探ったりできねえか。例の黒猫とか言う奴の居場所とか…お、これもうめえな!」 話しながらヴラドは森の住民の再び装備の選別を始めていて、使えそうなものをいくつか身につけていく。そして時々、なにかを口にしては喜んでいる。 「それは一時の気持ちじゃなく長期の記憶だからねー。大体この人が知ってるかはわからないし…全員の記憶を確かめるのには少し時間がかかるよ。ねえヴラド君、あっ…」 それまで男の方を見ていた卿が振り返ると、すっかり森の狩人の「てい」になっているヴラドがいた。相変わらず上半身は裸のようだが、たすき掛けに革のポーチ付きのベルトをし、破れかぶれになっていた浅葱色のズボンも、ぶかぶかな茶色の見るからに丈夫そうなものに変わっていた。足首の部分を革の帯で縛り上げ、腰には自分のククリナイフのほかに何やら鈍色の鉱石で作られた手斧を提げた。仕上げに深い緑色のマントを失くした腕の肩から羽織る。肌の見える部分には余すことなく刺青が彫られているためか、傍目には完全に妖しげな森の部族そのものだった。 「おれはこいつらの持ってた残りのモノを捨ててくる。それについては文句はナシだ。その間に頼むわ」 「…あぁうん!わかった…仕方ないね。というか凄くにあうね。そんでもって慣れてるね。へぇぇ~…」 卿はすっかり感心して見とれてしまっている。 「闘技場にいたころは強制支給があったしな。それに捕虜の捨て方とかこういう外で使う小物の扱いは船長が…それはもういいんだよ、頼んだぞ。ああそれとな」 話しながら余った不必要な荷物を手早くまとめていく。 「うん?なに」 はっとした卿が返事をした。 「俺の記憶はもう見たのか?なら…」 「いや、見てないよ!ど、どうしたの?」 「いや、ならいいんだ。忘れろ」 「うん…」 ヴラドがその場を離れると、卿は男らの方へ向き直った。 どことなく暗い面持ちだ。それも然り、卿はすでにヴラドの心へ潜ったことがあったからだ。そして卿はそれを強く後悔していた。あれほどのものを見るのは知識や教養は遥か人並み以上の卿とはいえまだ生まれて間もない者には恐怖が大きすぎた。それはヴラドが城を脱出した直後のことだった。 後半につづく。 あとがき。 会話回。 闘技場脱出編をかいてる時におもいついたおはなしです。新章、マインドダイバーカーエデール!!(ださい) 森編からのヴラド君の衣装、もしかしたら描いてくれたりとかあるんですかね~先生様方…チラッチラッ
くらいくらい黒の空に浮かぶひとつの光。日毎に丸くなってはしぼむ不思議なひかり。小さなけものはその光が大好きでした。暗闇でしかしっかりと見られない、そんな不思議なひかり…そのひかりを浴びるだけで心が満たされるのでした。 「卿、あれは月と言うのである」 ぼんやりと眺めていると後ろから聞こえる声。小さなけもののカーエデール卿を作ったツバキ博士の声でした。博士の声はいつも優しく自信に満ちているように思えます。彼はそんな博士が大好きでした。 「つき、か。いいねー、月。吾輩だいすきだよ」 「ウム。卿のエネルギーは月光を源にしてあるのである。よーく浴びておくである」 ニカッとご自慢のギザギザ歯を光らせて笑う博士。カーエデール卿も思わず笑ってしまいます。 博士や博士の助手であるDのいる科学班は、この世界にある大きな陸からすこしばかり離れた島にあります。周りの様相はどこの地域とも違う色をしているけれど、空から降り注ぐ白銀の光はどこにいても変わりません。 「月の力には諸説あって、古くから満月になると変身する生き物がいると言われているのである。吾輩、その説は大いにあり得ると思うである。なんとか使えれば或いは…」 ツバキ博士はたまに話しかけているのか、独り言なのかわからないトーンで呟きます。そんなときは決まっていいアイデアが浮かんでいるときです。卿はわくわくしながら、ふと博士の呟きにあった『変身』という言葉に思い当たる節がありました。 (あのとき、吾輩、へんしんしてたのかな?) 二人の見知った人たちが戦う。そんな瞬間を吾輩はただ窓の陰から見つめるしかなかった。 いろんな人たちが戦って怪我をして、息耐えていった。種族違いでケンカしていることは、前に黒い豊かな髪をもつ騎士さんから聞いていたけれど、あの日は違ったんだ。 (なんでおなじヒト同士なのに戦うの?) 吾輩にはきっともっと計り知れない何かがあったのかもしれない。 あの日も月がすごく丸くてきれいな日だった。海に映る光を見ながら月光浴をしていると、海の近くに佇む城にかけ上る、たくさんの兵士さんたちが見えた。松明を掲げ、駒に乗る兵士さんの中に見覚えのある緩やかに波打つ黒髪の騎士がいる。 (ジルキオさんだ。…すごく怖い顔してる) ブルッと震えながらも、一体何をそんなに急いでいるのか吾輩は気になって、その城の回廊奥で輝くステンドグラスまで飛んでいくことにしたんだ。 月光を照り返してキラキラ光るあのお城のステンドグラスは、吾輩のお気に入り。 (ステンドグラス、見に来たってわけじゃ…なさそうだよね) お城に近づくにつれて、鼻をつく鉄のような臭いが充満していた。 ーーーこれは、ヒトの、血の臭いだ。 やっぱり引き返そう。咄嗟にそう思い直したその時、ステンドグラスの前に人影が見えたんだ。なんとか中が見える場所に潜り込むと、そこには右側は白銀に流れる髪、その反対はすっぱりと剃りこんだ特徴のある髪型に上半身には入れ墨を持った人物の後ろ姿が見えた。 (あれってせんちょうの横にいた、ヴラドくん…だよね?) (ヴラドくん、ジルキオさんと戦うの?) (なんで?) 頭のなかで疑問符がグルグルしてしまう。お話をするだけじゃないことはすぐ雰囲気でわかった。あまりにも殺気と興奮と熱気が満ちていたからだ。 回廊からかけ上がる多くの足音が近づいてくる。 ヴラドくんを見つけて何やら話す声がして、兵士たちがざっと詰め寄るのが見える。…と、その時ジルキオさんの一声で彼の脇を抜けていくようだった。 (なんだ、戦わないんだね) 吾輩がほっとしたのもつかの間、兵士たちがいなくなってから、今度はヴラドくんとジルキオさんが対峙したんだ。そして… 吾輩はただ怯えながら、二人の戦いをみつめて、怯えながらもどこかで剣と剣のぶつかる音や飛び回る姿に興奮して見いる。 (どっちも…無事でいて) 幾度か交わす剣の音、空を切る音。そして。 互いに何かを話し、もう一度、鋭い一太刀。 吾輩は二人の殺気に気圧されて思わず目を抑えた。…恐る恐るもう一度、二人に視線を合わせると、ジルキオさんがしゃがんでるのが見えて、声を出しそうになった瞬間、今度はヴラドくんがこちらに駆け寄ってくるのがわかったんだ。 「ヴラドくん!」 吾輩が叫んだと同時にステンドグラスを割って城を飛び出す彼を、ただ救うことしか浮かばなかった。片腕があったはずの断面から多量の血が舞い、眼下の海に落ちていく。吾輩も必死で 落下速度に合わせて彼にしがみつく。 (このままじゃ海面にぶつかる!!) 必死に勢いを止めようと精一杯の力でヴラドくんを持ち上げようとするけれど、吾輩の非力さに涙がこぼれた。 (いやだ!いやだ、吾輩、ヴラドくんを助けたいよ!) 不意に羽が大きくなった気がした。いや、羽だけじゃない。さっきまで小さかった手足が、小さなケモノではないヒトの手足になっていたんだ。 これなら、きっと、飛べる! 海面スレスレを滑空して、すぅっと飛行する。抱えられた彼の爪先が水切りのように海面を跳ねる。もっと高く飛べればと思ったけれど、それは無理そうで、ギリギリを飛ぶのでやっとだ。両腕でヴラドくんを抱えながら、いつもよりは力が出たとはいえ、じわじわと支えている腕の痺れに、ヴラドくんとは違うか弱さを感じていた。 (なんとか…もうちょっと離れた陸地にいかなきゃ。) このまま飛びつづけられる気はしなかった。けれどここで海に落ちたら、腕のなかで気を失ったままの彼と肉食魚のエサになってしまうだろうことは必至だった。 未だに断面から流れる血も心配でならない。とにかく半泣きで飛び続けたんだ。 「…あ、あれ…陸だ!…陸だよ、ヴラドくん!」 「…」 一瞬、目がゆっくり開き、苦しげだった口元にいつもの不敵な笑みを浮かべて、また目を閉じた。 (よかった、まだ生きてる) ほっとした瞬間、突然力が抜け、ザバッと海に落下してしまう。低空飛行で浅瀬まで着ていたからよかったものの、二人ともいっぱい海水と砂を噛んでしまった。 ぐったりと浅瀬に寝転んで、波の泡立ちに濯がれる。吾輩の身体はもういつものケモノの姿に戻っていた。ふぅ、とため息をついて彼の右腕があった場所を見つめる。 (まだ、やることがいっぱいだ) 「博士、吾輩ってもしかしてへんしん、出来るのかな」 「…ん?卿はもう新月になると…」 博士は言いかけたところでみるみるばつの悪そうな顔を浮かべました。そして唇を真一文字にして言葉を飲み込みました。 「シンゲツ?って何?」 「ゴホゴホ!いや、何でもないである。そうであるな!卿なら変身できる可能性は大いにあるである!」 科学者の魂に火がついたのか、黄金色の瞳をキラキラさせて博士は話します。卿はぼんやりと思い出しながら、クスクス笑いました。 「えへへ、あのね。吾輩、実はもう変身したことがあるんだよ!今一緒に旅してるヒトを助けたときにね、今日みたいな真ん丸の月が出てて…それで多分変身できたんだ」 カーエデール卿の言葉にツバキ博士は目をぱちくりしました。 「なんと?!そ、それは本当であるか?!うむ、うむ、ちょっと待つである。」 博士はバタバタと資料を漁り、Dにも指示を出しながら目当てのものを見つけたようで嬉しそうに卿のもとへ駆けてきました。 「これである」 「これは、なあに?」 渡されたのは銀に光る丸い珠でした。 「これは、いま空に光っている月の石を圧縮して固め、研磨した珠である。月光浴をする時にはこれにも光を浴びせてやるといいのである。まだ効果はないやもしれないが、いつか肌身離さずもっていればいつでも変身できるようになるである」 話を聞きながら、卿はその珠をこねくりまわしては嬉しそうに抱きしめました。 「ありがとう、博士!これで吾輩もっとヴラドくんの役に立てるようになるかな!」 キラキラと嬉しそうに話す卿の頭をなでて、うなずきながら、うむと微笑みかける博士。 「ヴラドくんというと、ああ。卿が吾輩に腕を治してって言ってた子の名前であるな。ここへは生身のヒトが来れる道がないから如何にと考えていたのであるが、卿がこれで長く変身出来るようになれば、無事に連れてこられるかもしれないであるな。その時は吾輩も腕をふるうである!」 博士の言葉にまた嬉しくなって、えへへと笑う小さなケモノ。 ふと、博士はあることに気づきました。 「卿、先ほど『今日みたいな真ん丸の月』といっていたであるな?…ふむ。もしかしたら今日も変身できるかもしれないである。」 「え!…で、でも吾輩あのとき無我夢中だったからどうやってなったのかわかんないよ?」 博士の言葉に驚きが隠せない卿でしたが、どこかワクワクした様子で言葉じりが浮わついたようになっています。今日は満月の夜。海の上には綺麗な真円の月が浮かんでいました。 「一度変身出来たのなら、きっと出来るである。屋上で月光浴をしてみるである」 博士もどんな風に変身するのか、好奇心と探究心で一杯のようでした。 一人と一匹は急いで屋上に飛び出し、いつもより近くで月を浴びることにしました。 「きれいだねえ、博士」 満月をぼんやり見つめながら、いくらか時間がたった時。それは始まりました。月光につつまれて卿の身体は光を放ち、光のなかで羽が大きくなり、手足が延び、体や頭にも変化が見られました。 「これは…」 ごくりと、唾を飲み込み目の前で起きる奇跡にただ目をぱちくりするしかできない博士は、触れるのをぐっと我慢して変化の形態を見つめました。 月光を照り返す白い肌とふわりとした赤い髪と大きな角。薄朱色のひらりとしたドレスに包まれた少女がそこにいたのです。 「博士、吾輩変身…」 手のひらと甲を交互にみつめ、顔を撫でて自分自身の変化に驚く卿と、思わず口をあんぐりさせ、そしてすぐに嬉しそうに歓声をあげる博士。自分が作った生物の変化に研究者冥利につきたのか、本当に大喜びしています。 「大成功である!なんと…そうであったか。卿、ヒト型だとメスなのであるな」 「えっ。あ、あ、ほんとだね。」 へへ、と互いに笑いながらまた月を見上げて嬉しそうに月光を浴びるのでした。 ーーーーーーーーーーーー あとがきと言う名の言い訳 すんません、無駄に長くなりました。ヴラドくんの「初戦」らへんのとこの話と、卿が変身することの話をかこうと思ったらなーんかこう…まとまってんのかなあという感じに; ジルキオさんとも会ったことがあるていで進めてみました。あっちこっちいくからね、卿は! ヴラドくんと会話させるシーンいれるつもりがほぼ博士とのフリートークになってしまって。。いつもすんません。 科学班には普通にヒトが入ったりできないようになってて、他国との話も多分卿か別の通信手段で連絡してやりとりしてるのでヴラドくんを連れて腕直すのは卿がいつでも変化できるようになってから或いはエルフのアーティファクトかなんかで移動するかみたいな感じじゃないですかね。(ただ、エルフサイドからは危険地域だから閉鎖してる出入口とか…)とにかく普通に来ても実験体たちに襲われて腕治すだけで済まないはずです。 ちなみに卿はヒト型だとメス→ケモノ型だと雌雄同体です。ここ、テストに出るよ!(出ない)
海の上を漂流しているとき、彼女はヴラドの無茶な行動の理由と彼の人となりに強い興味を持ち、特殊なある種の「霊体化」を行いその心に入り込んだ。誰もが秘める胸の中の心と記憶。「心象風景」とでも呼べるだろうか。卿はほぼ自由自在にその中をくまなくのぞきこむことが出来た。その行動の是非はまだ幼い卿にはあずかり知らぬことである。 ヴラドの心の中に入った時、まずたどり着いたのは真っ暗な入口へ続く石造りの通路だった。時刻はおそらく昼間で、ホコリっぽく、高い位置に設けられた通気口から差し込むのは強い陽の光と砂埃。加えて半分程地下に位置しているようだ。卿の知識からしても、間違いなくこれは闘技場の通路だった。卿が入口へ近づくと、登りだという予想を裏切り、階段は地下深くへと潜っていくものだった。どこからかかすかに人々の歓声や悲鳴のようなものが聞こえる。観客たちだろうか。卿はゆっくりと階段の方へ近づき、下へと潜りこんでゆく。一定の間隔で明かりがともされている。入ってきた入り口からは明かりが差し込んでいたが、段々と暗くなり、かすかに照らされる石の段差が視界の下にちらちらと見えるまでになった。いつしか観客らの声も聞こえなくなっていた。 しばらく下っていくと突然、無数の棘のような影が壁を伝って行く先から現れ、光を飲み込んでゆき、何も見えなくなった。卿がおろおろしているうちに、遂には目下の階段が闇そのものに溶けた。浮遊していた卿は落ちることなどないはずだったが、完全に闇になった空間の下へと一気に落下した。卿はすぐにいつものように術式を解き、脱出を試みたが、何かが起きる気配は全くなかった。しばらくしてどすん、となにかの上へ落ちた。落ちてきた高さの割に、どこも痛まない。辺りを見渡すが、何も見えない。 すると卿は、だんだんと身の自由が利かなくなっていることに気が付いた。段々と影体中に巻き付いてきているのか。懸命に術式解除を唱えながら抵抗する。影が卿の小さい体を包み込んだ時、内側から花火のような光が湧いた。炎の呪文だ。続けて卿は蛍のような光の玉を頭上に発現させる。弱弱しく頼りがいのない光にも影は一時わらわらと燃えちぢれて卿を解放したが、また足元に這いよる機会をうかがっている。卿は角に「絡まった」影を取り除こうとしてはっとした。これは影でも闇の魔術の類でもない。 髪だ。途方もない量の髪の毛が、この空間をすき間なくみっしりと埋めているのだ。卿の眼にみるみる涙がたまる。灯明の呪文が映し出したのは、うねうねと流れはい回る髪の海だった。 するとその中から、なにか白い塊が髪をかき分けて現れた。人間の背丈ほどもある大きな白い塊、それは女の顔。目は落ちくぼみ瞳はなく、真っ黒なガラス玉のような眼球がはまっている。鼻はそぎ落とされ、口からはとめどなく髪の毛が吐き出されている。顔はどんどんこちらへ近づいてきていた。一歩も動けない。遂に鼻先まで卿に近づいた。声が出ない。女の顔は大口をあけて卿の身体を飲み込もうとする。めきめきと顎が鳴り、口が裂ける。裂けた傷口からまた髪の毛が噴出した。口の中の髪の渦が卿の身体に触れかけたその時、若い男の声が轟いた。 「やめろ!毎度毎度気色ワリーんだよこのクソババア!」 飲み込まれそうになっていた卿の後ろで強烈な光が巻き起こる。そして、卿の頭の上、丁度顔の上唇のあたりに、金色の短刀が突き刺さった。女の顔はそこで初めて大きすぎる悲鳴を上げた。頭が割れそうだ。卿は強く瞼を閉じて耳を塞いだが、とても耐えられそうにない。気が遠くなる。すると後ろから先ほどの声の主と思しき若者の腕が体にするりと手を回し、強く抱きかかえられた。 「上がるぞ!気ぃ失うなよ!戻れなくなんぞ!」 若者は膝を曲げてしゃがみこむと、そこから垂直跳びで一気に暗闇の上と飛翔した。ものすごい速さだ。眼下に絶叫する女の顔はみるみる小さくなる。卿は顔を上げて、自分を抱きかかえている若者の方を観た。現れた時から輝いているのは若者の金色の髪だった。長く腰まで伸ばしている。どこかで見たような顔立ちだった。誰かに似ている。そうだ、船長だ。若者はかつて卿が助けた船長に瓜二つであった。 「せんちょう・・・?」 卿は若者に尋ねた。 「ん?おれは船長なんかじゃないぜ。守り人ってやつだ!船になんて乗ったこともねーよ!おれは、おれのなまえは、ル…なんだっけ?なんてこった、忘れちまった!とにかく、おれはあのババアを見張るのが仕事だ!おまえなんだってこんなとこに来たんだよ!バカだなあ」 「ごめんなさい…」 「まあ、いいよ!あのババアがいなくなったら、また来いよ!ここはひどくさみしいからな。お、ついたぜ!とっととかえんな!」 暗闇の先から、ぼんやりと光をはなつ何かが見えた。巨大なステンドグラスか絵画のような人物画が暗闇にずらりと並んでいる。うち二人はすぐに分かった。髪は短いが美しい金色。端正な褐色の顔、船長だ。正面を向いてサーベルを抜き、高く掲げている。満面の笑みだ。もう一人は城で見た騎士だ。こちらはこちらに背をむけてこちらに目線だけを投げかけている。長い髪で表情はわからないが、固く結ばれた口元だけが見える。 二人のすきま間を抜けて飛んでいると、視界が突然真っ白になった。若者もまたけむりのように消えてしまい、またも卿は強烈な落下を感じる。ぎゅっと瞼を閉じ、衝撃に備えていると、若者の声だけが頭に直接だが優しく響いた。 「弟の事、頼むな」 落下感は突然に消え去り、元いた海の上で目が覚めた。 卿の手には一本の金色の長い髪が絡みついていたが、卿がそれに気付き握りしめようとする前にほどけて海のかなたに消えた。 つづく。 あとがき なんで書いたのかわからない上に文量が少なくて展開超早いしよくわからない良い感じに締めようとしたよくわからないオチ。でも書きたかったからええんや。満足! おおきなのステンドグラスの中にはもちろんグリモワール師などもいて、ヴラドの生きる道しるべになった人たちが描かれています。んでヴラドの作り出したルカの記憶や魂みたいなのがそれらを飲み込もうとしてる母親の呪いから護っている、的なイメージです。妄想にしてもキャラ愛半端ねえし臭いよ!臭い!このあとがきも臭い!臭いよ!
強い雨が降っている。先ほどの突き抜けるような青空が嘘のようだ。 翳る空は薄暗く、かつて乱気流の如く闘技場に吹き荒れていた熱気は勢いを強めてきた雨に冷まされ、生ぬるく不快な空気に変えられていた。かつて生気に満ちた剣奴たちの戦っていた地面に散らばっているのは切り裂かれ、潰され、叩きのめされた死体、死体、死体だ。雨と泥と血肉が混じり、もはや戦場の跡の如き様相を呈している。先ほど腹を踏み潰された兵士が胃袋の中の物をまき散らして死んでからというもの、普段の会場にはない重苦しい静けさが一帯を包んでいる。観戦者たちはまさかあれほどの人数が全滅させられるとは予想だにしていなかった。もはや辛うじて生き残った数人がゆらゆらとヴラドを取り囲むだけになっている。 「強い闘士が圧倒的な大人数に槍玉にあげられ敢闘するが見るも無残に殺される様」を期待していた観衆は、いつしか皆野次を飛ばす者も無く固唾を呑んで戦いの行く末を見守っていた。一方、真ん中で片膝をついているヴラド自身にももう生気も最初に放った溢れだすような怒気もない。肩で荒い息をする彼の身体は余す事なくどす黒く血に汚れていた。さっきから何故だか、首輪がひどく熱いような気がする。首輪を中心にして、言いようのない「熱」が体に帯び始めていた。何かがおかしい。が、今気にかけている余裕はない。 「うぅ、おおおっ!」 闘士の一人がついに沈黙を破り、泥を撥ねながらヴラドに向かって突進した。「チビ矛」のサムソン、一攫千金と成り上がりを夢見て外からやってきて試合に出た男。しみったれた傭兵稼業から足を洗おう。少し前に孕ませた酒場の女を買い上げて、その子供と3人で農場でも拓こう。そんな気持ちでここへ来た。立ち寄った街の酒場で募集を知った時はなんとも趣味の悪い試合だと思ったが、手傷を負わせるだけでも分け前は出ると聞き、その分け前だけでも自分の2年分の稼ぎはあると知って色めき立った。そして今彼が感じているのは、その時の選択が今まで渡り歩いた戦場でしくじって死にかけたどんなくそったれな場面よりも最悪にバカなものだということだ。伊達に戦場を生き延びてはいない。時々見かけるんだ、「こういう化け物」を。あの時は近づきさえしなければ生き残ることが出来たが、今回はそうはいかない。哀れなサムソン、お前もここまでか?ああ、死にたくない! 未だ動かない「悪魔」に向かって無我夢中で槍を突き込む。相手はそれを躱そうともせずに、うつむいたまま左の掌をすうっとこちらに向け、そのままどすん、と躊躇なく受け止めた。そのままゆっくりと立ち上がり、こちらへにじり寄る。掌を貫いた槍はその身を血で汚しながらずりずりと掌を貫き通してゆく。サムソンはすでに身動きもできず立ち尽くすのみであった。 「ふぐ…うぐ、ひぐっ」 足元から湯気が立ち上る。涙があふれる。ここで死ぬのか。いやだ、怖い!目の前に迫った悪魔は兜の下からもう片方の手を差し込んで、首を掴んだ。そしてギリギリと締め上げてくる。息が出来ず、泥まみれでもたつく重い足をばたつかせるが、すぐに自分の首の骨の軋む音が聞こえてきて意識が遠のく。苦しみに満ちた少しの間をおいて、ボキリという乾いた音を最後に、彼の生は終わった。 ――小柄な死体を地面に捨てて、ヴラドは空を見上げる。顔についた血が少し洗い流された。いつの間にか、敵もあと少しだ。まだ自分も五体満足に生きている。ヴラドは大きく深呼吸をした。やることは変わらない。そろそろ終わらせろ。 おもむろに左手を貫いた槍を右手で掴み、そのそばを膝で叩き折ってから一気に引き抜いた。折れた槍をそれぞれ両手に構え、そして倒れこむように残った敵に向かって突進する。 間もなく、試合の終わりが来た。ヴラドは一人その場に立っている。彼の周りはまさしく血の海が広がっていた。規模としては世紀の大試合になっているはずだが、歓声を上げる者はない。異様すぎる光景だった。みな呆然と眼下に広がる血の池に立つ青年を眺めている。彼は一人で、百人を超そうという相手を皆殺しにしたのだった。 ヴラドは歩き出した。本来退場すべき流血路とは逆の出入り口へ。そう、自分の雇い主のもとへ。まだ彼の相手は残っている。 天幕が張られている貴賓席で、ラガルトはそれを悠然と見下ろしている。 何か考えを巡らせているようだ。 「いや、もしかすると名乗り出る者がいるかもな…おい、用意しろ」 そばで控えていた侍女たちの一人が裏口へと消えていき、もう一人がラガルトの足元でまた「拡声の呪文」をつぶやいた。落ち着き払った、とどろく声。 「御集りの皆様!とんでもない結末になってしまいました!私を含め誰がかような結末を予測しましたでしょうか!いえ私も、このような結末は望んではいなかったし、思ってもみなかった!オオカミは悪魔となった!今ここに!邪悪なる悪鬼が誕生したのです!皆さま!新しい伝説に盛大な拍手と喝采を!」 始めはまばらだった拍手も、徐々に大きくなってくる。その喝采はヴラドをたたえるものではなく、この混乱に収拾がつけられないどよめきと言いしれない興奮に代えられているにすぎなかった。ヴラドはラガルトに一番近い塀の前まで歩み寄り、じっと一点を見つめている。そして、腰を落とし、何かを構えるような素振りをみせた瞬間、何かを投げた。それと同時に、ラガルトは足元にいる侍女をすばやく抱き寄せた。侍女の背中に突き立ったのは血まみれの剣。貴賓席から悲鳴が巻き起こる。ラガルトは顎をくいとあげて、じっと眼下の奴隷を見下ろしていた。 あとがき: ここでアイデアが腐ってきたので、後編としてまた後で書きます。むずい

(設定:どこかの帝国領の城から逃げる海賊団。海に面した崖に沿って建てられた背後は断崖絶壁の城。ヴラドは船長と殿をつとめていたが、時間稼ぎのために単独、ジルキオ率いる騎士団を迎え撃つ) 廊下の角を曲がると、全力で逃走する一団のなか、賊らしくない海賊団の中で唯一「悪党」然としていた白髪の青年がたった一人、曲刀のような異国の武器を抜いて立ち止っていた。その青年に対峙した追っ手たる騎士の一隊は相手が一人なのにもかかわらず、何故か思わず立ち止まってしまう。突然ひとり立ち止まっていた青年に意表を突かれたこともそうだが、青年が殺気か気迫か、形容しがたい「うねり」のような空気を発していたからだ。 「は、足止めにたった独りだけとは、無謀以下のもはや大馬鹿だな!見捨てられたか?あわれな下っ端め!」 兵士の一人が気を取り直し、挑発しながら槍を構える。青年は何も答えずにただゆっくりと腰を落とし、武器を逆手に持ち替えた。 「この・・・!」 兵士が動こうとした時、隊を率いていた騎士がそれを制した。 「あれの相手は私がする、手出しは無用。お前たちは行きなさい。あのような者どもは決して逃がしてはならない」 「まさかあのような下手人の挑発に乗るおつもりですか!?」 騎士は何も答えず、ただ視線の先にいる青年を見据えている。 「…わかりました。おい!行くぞ」 兵士は隊列に命令し、青年の脇を走り抜けていった。全員一切青年に手を出さなかったが、青年も兵士らを止めるそぶりを全く見せなかった。青年にとって、向こうが決闘の形式をとったことは僥倖であり、それに従うのが最善の選択でもあった。 ゆっくりと、しかし確実に騎士は青年へのほうへと歩を進め始める。どうやら青年の発する「うねり」はこの騎士には殆ど通用していなかったらしい。むしろ迎え撃つ青年の方が表情が険しくなってきている。騎士は腰に差していた二本の剣のうち一本を抜いた。美しい曲線を持つ柄の上質なレイピアだ。 騎士は精悍で整った、劇役者の二枚目のような流麗な顔立ちをしており、それを引き立てるように長くのばした黒髪はまるで物語の中の人物の様であった。ともすれば王の風格さえ持ち合わせているかのように見える。それに対峙している青年は、ぼさぼさの白髪を半分に刈り上げ、服もろくに着ておらず、全身には刺青。極めつけに黒い首輪まではめている。もはやそのいでたちは王の前に引き出された奴隷に等しかった。 先に動いたのは青年だった。全速力で騎士に突進し、直前で地面を蹴り騎士の顔面に向かって躍りかかる。 騎士はその場でほとんど動かずに、腰と腕の動きだけで淡々と青年の攻撃、二回の蹴りと三回の斬撃をいなした。 そして青年の隙をまるで決められていた動作をこなすかのように生み出し、青年のみぞおちに向かって的確にレイピアの柄をめりこませた。 普通の兵士なら悶絶するであろう一撃だったが、青年も素人ではない。痛みをいったん無視してすぐさまレイピアの切っ先の届く範囲の外へと飛びのいてから、改めてやって来る痛みをやり過ごす。まさか一撃も入らないとは予想もしていなかった。 「ぐう…」 青年は騎士と初めて会いまみえてからその力量の高さをびりびりと感じていたが、今の剣戟でそれを確信に変えていた。 格が、違う。理由はわからないが、手加減さえされているだろう。青年は自分がすべきは時間稼ぎであって勝つことではないのは十分にわかっていたが、出会ったことのない程の大きな力量差と意図のつかめない手加減、加えて涼しげな騎士の冷徹な視線に青年は苛立っていた。 「俺は上から見下ろされるのが嫌いなんだよ」 青年はしゃにむに飛びかかる。が、結果は同じ。 今度は真正面から頬に拳を叩きこまれ、もんどりうって倒れ伏した。 「何度やっても同じですよ?しかし、悪くない動きですね。それに異様なくらい殴られることに慣れている。独特の受け流し方だ」 騎士は視線を落とし白い手袋をはめた手の甲に染みた血を見ながら言う。 「そりゃどうも…げほっごほっ」 青年は切った口の中の血を勢いよく吐き出して答えた。 「殴られたダメージはさほどではないのでは?戦闘の経験で言えばおそらく私よりあなたの方がすこし上なのでしょうね。しかし、あなたには師と呼べるものがいなかったのではないですか」 「…なぜわかる」 「何故って、殆ど貴方の剣には守る動作がありませんよ。噛みつくだけなら犬でも知っていますが、守りと反撃の完成は独学できるものではない。型ですからね。貴方の剣はただ相手より早く、あるいは多く斬りつけようとするのみで、勝利の先にあるものへの欲求がない。勝って、生き残りたいという本来あるべき原理が存在しない。あるのは死への早すぎる道のりだけ。相手の、いやその死は自分にさえ向けられている。命を、試している。かつての奴隷仲間の真似でもしているのですか」 「グダグダとうんちく垂れてんなよカマ野郎。俺が誰の真似をしてるって?」 再び青年は騎士に突進するが、落ちる木の葉を叩こうとするが如く躱され、蚊を叩くが如く脇腹を剣の峰でしたたかに打ち据えられた。 先ほど殴られた二か所のようにごまかす余裕をあたえない、骨の軋むような一撃。 呻き声を上げながら後ずさる青年。ここまでか。青年は覚悟を決めかけていた。かすんで揺らぐ視界。口の中は血の味で一杯だ。もう力量差なんてどうでもいい。あとどれだけ長く立っていられるか…と考え始めた時、青年は「それ」を見た。 廊下に並ぶ大きなステンドグラスの窓枠のひとつに、赤いねずみだろうか、丸っこくてちいさな生き物が見える。見間違いだろうか?いや「それ」は間違いなくこちらを見ている。小さく震えながらおびえた目で二人の男の行く末を見守っている。ずっと後になっても本当に何故だかわからなかったが、青年はその時、自分の視界がすうっと晴れていくような感覚を覚えたという。自分がいま、すべき事。求めるものがわかったという。 「…要するにひとつ確かなことは、あなたの剣には我がまるでない、ということ。そのように空虚な牙では私には届くはずもない。如何せん軽すぎる。さて、うんちくはこれで終わりにしますよ。次は斬ります。残念ですが逃がしもしません」 膝をついている青年につかつかと歩み寄り始めながら、騎士は自分に驚いていた。たかが賊一匹に何故自分は講釈など垂れているのか。脱走奴隷を育ててどうする?地べたを這いずり回る凶暴な子供に自分と通ずるものでも感じたか。意味なんてないはずだろう。なによりもう殺してしまうのだから。 「くくく…なんでもかんでも見透かしてくれやがる」 青年は笑っている。血反吐にまみれた歯をむき出しにして。 「お前、犬に噛みつかれたことあんのかよ?」 騎士が最後まで聞き取る前に、青年はまた愚直に突進し仕掛けてきた。なにかが変わった様子もない。が、問題はそのあとだ。 先ほどと同じように、青年の見え透いた攻撃をいなそうと剣を動かした瞬間、そこにあったのは傷だらけの曲刀ではなく、青年の二の腕であった。短いフェイントを挟み、刀身に直接腕をぶつけて来たのである。これは騎士の予想外であったがもう遅い。肘を高く上げ、V字に曲げた腕の肘から上の部分と手首にみるみる刃が食い込み出血がはじまる。筋肉と骨に挟まれた剣は一瞬だが狼狽えた騎士の動きを阻害した。 青年は刃が食い込んだままの腕を捩って騎士の足を踏みつけて肉薄し、騎士の額に自分の額を押し当てて言った。 「噛みついてやるよ、騎士殿」 青年が思いきり千切れかけた腕を振るい、ついに騎士から剣を引きはがした。腕を犠牲にした代償にこじ開けた隙を逃さず、残った方の腕で騎士の顔に渾身の拳を見舞った。宙を舞った剣は高い音を立てて石の床に突き立つ。騎士が膝をついた瞬間、青年は踵を返して走り出し、ステンドグラスの大きな窓を突き破って遥か下の海に飛び込んだ。 ―そのしばらくのち、騎士は何も言わずに立ち上がり、剣を拾い上げて鞘に戻す。 「つっ…ふふ」 口元の血を拭うと、思わず笑みがこぼれた。顔を思いきり殴られたのは一体どれくらい振りだろうか。 「逃してしまったな。これは重大な失態だぞ、騎士殿?」 振り返ると、そこに笑みをたたえながら立っていたのは君主であるマシュー公であった。腕を組み、壁にもたれかかっている。 「…いつから見ておられたのですか殿下。恥ずかしながら後れを取りました。処罰は如何様にもお受けいたします」 「おや本当か。遊んでいたのではないのか?お前ほどの剣士があのような雑魚に手こずるとは思えんが…それに、最後に至ってはお前、わざと拳を受けたろう?」 「滅相もございません。殿下、まだ賊が潜んでいるやもしれません。早く奥へお戻りください」 「わかったわかった。それよりも早く冷やしておけよ?二枚目が台無しになるぞ。ははは」 マシュー公は両手を上げて、笑いながら立ち去った。 「やれやれ」 騎士は溜息をつき、破れた窓を見やる。生きていればいつかまた剣を交えることになるかもしれないと、騎士ジルキオは最後にもう一度うっすらと微笑んだ。 おわり あとがき 段落?何それ知らん キャラクター勝手にしゃべらせてすみません。(相変わらずジルキオの勝手なイメージが暴走してます) 剣術やその他うんちくは完全に雰囲気と思い付きで書いておりますゆえ中の人やお詳しい方は鼻で笑っておいてください。おこらんといて
小話「ある夜の再会」 ある城とある麗しの騎士 静寂。騎士は窓際で月を眺めていた。 仕事の為に客人としてこの城に立ち寄り、3日ほど滞在する予定だったが、どうやら早くも賊が入ったようだ。しかし最初に知らせを聞いてからどれくらい経ったろうか、まだこちらに伝令ひとつ寄越さない。 兵士も大した錬度ではなさそうだった。被害が広がる前に自分で始末する方が早いだろうが、小国の領主に恩を売ったところでこちらに大した益があるわけでもない。 半開きになっている窓のすき間から、冷たい風が吹き込んでいる。 騎士は小さくため息をつきながら、窓を閉めた。 すると突然、背後で扉が勢いよく開け放たれた。 騎士は驚くそぶりも見せず、半身だけ振り返り、肩から扉の方を見やった。 「…様!お伝えいたします!すでに20名近くの兵が…うっ!」 言い終わる前に、伝令と思われる兵士は扉の向こうの暗がりへ引きずり込まれた。短いうめき声のあと、再び静寂が戻って来る。少しの間をおいて、灰色の衣を纏った男が現れた。騎士はそれでも微動だにしない。 賊と思しき男はその場でためらいもなくフードを外した。が、未だ顔の下半分は黒い布で隠されたままだ。見覚えのある銀色の髪、そして意外にも彼は明るい調子で彼に話しかけた。 「よう、久しぶりだな、ねーちゃん。俺のこと、覚えてるかい?今から俺と一曲踊ってくれねえかな。」 騎士は男の顔を見て少しだけ微笑んだ。長く伸ばした黒髪と肩に隠れ、男にその表情は気取られない。騎士はそこでようやく男の方へ振り返り、言った。 「いいや。記憶力には自信があるが、礼を欠いた賊一匹の名まで覚える必要はあるまい。それに私と踊る相手はただ一人と決めているのでね」 おわり